前の10件 | -
黄昏のビギンを聴いたことがありますか [読後の感想]
一気に読み切った。久しぶりのことだ。同時代感、それにつきる。そのとき流れていた唄、メロデイ、詩、すべてがひとつひとつ蘇る。またひとつ心の糧となるすばらしい本と出合うことができた。佐藤剛氏に感謝。
上を向いて歩こう、黒い花びら、こんにちは赤ちゃん、帰ろかな、等々、作曲家中村八大の手になる作品群。その中で発表時にはあまり大きな反響が得られなかった「黄昏のビギン」という曲。この唄を中心にして、中村八大が関わった戦後日本歌謡史を解き開いていく。曲が世に出てからすでに半世紀、記録も失われ人々の記憶も薄れていく中で残された疑問に挑み、仮説を立てその検証をする。唄に隠された謎を少しづつ明らかにしていくステップは、良質の推理小説の趣がある。詳細はここで明かすことはできないが、戦後歌謡史に興味のある人ならば必読の書であろう。
曲のカヴァー。これがこの本のもう一つのテーマである。中村八大とその世代の作曲家作詞家が壊すまでは、誰かの持ち歌を他の歌手が歌うことなどできなかった。つまり、日本の歌謡曲はレコード会社の販売商品であり、作曲家・作詞家・歌手を専属で契約し囲い込むことによって始めて利益を独占できるシステムであった。当たり外れの多い商品を目利きの腕で仕入れるのだが、商材の多くは単なる金食い虫で利益には結びつかない。だからこそ、囲い込みの仕組みが必要だという理屈に誰も疑問を持たなかった。
“日本ではレコード会社が作詞家や作曲家と専属契約を交わして、出来てきた楽曲を各社がそれぞれに独占的に使用していた。他社の歌手に歌わせないのは、競争相手を利させることはないという理屈である。楽曲に商品的な価値しか見出さず、誰もが共有できる社会的な文化財産とは考えなかったのだ。”
中村八大は永六輔と組んで、次々にヒット曲を出していく。1959年の黒い花びらから1961年の上を向いて歩こう、1963年のこんにちは赤ちゃん、そして、そして... これらが専属契約を持たないフリーランスの作詞作曲によって成し遂げられたことで日本の歌謡界は大きな構造転換を迎えることになる。作家が相応しい歌手のために、TV番組のために、プロダクションのために楽曲を提供することが当たり前になっていった。レコード会社の独占が壊れることで、優れた楽曲を素材として、歌手の個性と歌唱力で新しい生命を吹き込むこと、すなわちカヴァーが普遍化した。そして、時を超えて歌い継がれる、スタンダード・ナンバーが生まれ出した。その代表的な楽曲が「黄昏のビギン」なのである。
試しに、iTunesで黄昏のビギンを検索するとたちまち30を越える歌手の作品が並んでおり驚かされる。
アン・サリー、石川さゆり、稲垣潤一&島健、岩崎宏美、小野リサ、和幸(加藤和彦、坂崎幸之助)、川上大輔、河口恭吾、佐々木秀実、さだまさし、渋さしらズ&Sandii、セルジオ・メンデスfeat Sumire、鈴木雅之with鈴木聖美、中森明菜、氷川きよし、薬師丸ひろ子...
実は、1959年に水原弘がB面で吹き込んだ黄昏のビギンは発売後ほとんどブレークすることなく、一部の愛好家にだけ知られていたのだが、それから30年後の1991年にちあきなおみがカヴァーアルバムの中で取り上げたことで、知られ始めたという経緯がある。だからこそ、余計にiTunesにちあきなおみ版が見当たらないのは極めて残念としか言いようがない。
自分を信じはい上がる [新聞記事]
「私の履歴書」日本の若手へ、トム・ワトソン、2014年5月30日、日本経済新聞朝刊を読んで
トム・ワトソンの「私の履歴書」、大変に読み応えのある内容が続き、そして最後に日本の若手選手、とくに松山そして石川遼への熱いメッセージである。
“石川について言えるのは、まず、あの若さで多くの注目を集めたことに伴う重圧は相当なものだったろう、ということだ。”
ここでワトソンは、石川遼が米国のメジャーの厚い壁にはね返され続けている現状を前提にして語っていることが明白である。重圧をエネルギーに転じて前進できていた時と、もがき苦しんでいる今はいったい何が違うのか。この難問の前に立ちすくむ石川遼に対して、ワトソンはあくまでやさしく語りかける。
“次に言えるのは、ゴルフには良い時と悪い時がつき物だということ。その繰り返しの中で、できるだけ好調を長引かせ、不調を短くすることが肝要だ。好不調の波を重ねながら、最終的には自分のゴルフが右肩上がりになっていけば、それでいい。”
「最終的には」という言葉から、焦ることは何もないよというワトソンの声が聞こえてくる。そしてさらに、具体的なアドバイスを述べている。
“できる限り、練習を重ね、何が自分に合っているかを突き止めろ”
探求とか追求とかいう言葉ではまったく足りないような世界がそこにあるということか。
“試合中でも自分のスイングを変えることを恐れてはいけない。そこから学ぶことは必ずあるからだ。”
機械のようにスイングしろというのとは違うらしい。人間が体を使ってボールを操ることの難しさ奥深さとでもいうことか。
“「こだわり」は時に重要だ。しかし、それがうまくいかない時には、変える勇気も持たなければならない。”
そして、ここで、ジャック・ニコラウスを引き合いに出し、
“ジャックはマスターズ選手権の最終日でもスイングを変えることを厭わなかった。”
変えることに対する「恐怖」に打ち勝つしかないのだと述べている。
最後に次のように語っている。
“ゴルフにおいて「己を知る」ということだ。そこに他人が入り込む余地などない。自分自身を信じ、皆、はい上がっていくしかない。”
信じるものは自分だけ、恐怖に打ち勝ち、はい上がる、それしかないという。煉獄の道だ。
この暗示に満ちたワトソンの記事が出たのが5月30日。そしてその翌々日の6月1日に新しいヒーローが誕生した。
「松山英樹、米ツアー初優勝 男子ゴルフ、日本勢で4人目」
なんという偶然、そしてあまりにも残酷で輝かしい希望。それでも、だからこそ、石川遼、がんばれ。
トム・ワトソンの「私の履歴書」、大変に読み応えのある内容が続き、そして最後に日本の若手選手、とくに松山そして石川遼への熱いメッセージである。
“石川について言えるのは、まず、あの若さで多くの注目を集めたことに伴う重圧は相当なものだったろう、ということだ。”
ここでワトソンは、石川遼が米国のメジャーの厚い壁にはね返され続けている現状を前提にして語っていることが明白である。重圧をエネルギーに転じて前進できていた時と、もがき苦しんでいる今はいったい何が違うのか。この難問の前に立ちすくむ石川遼に対して、ワトソンはあくまでやさしく語りかける。
“次に言えるのは、ゴルフには良い時と悪い時がつき物だということ。その繰り返しの中で、できるだけ好調を長引かせ、不調を短くすることが肝要だ。好不調の波を重ねながら、最終的には自分のゴルフが右肩上がりになっていけば、それでいい。”
「最終的には」という言葉から、焦ることは何もないよというワトソンの声が聞こえてくる。そしてさらに、具体的なアドバイスを述べている。
“できる限り、練習を重ね、何が自分に合っているかを突き止めろ”
探求とか追求とかいう言葉ではまったく足りないような世界がそこにあるということか。
“試合中でも自分のスイングを変えることを恐れてはいけない。そこから学ぶことは必ずあるからだ。”
機械のようにスイングしろというのとは違うらしい。人間が体を使ってボールを操ることの難しさ奥深さとでもいうことか。
“「こだわり」は時に重要だ。しかし、それがうまくいかない時には、変える勇気も持たなければならない。”
そして、ここで、ジャック・ニコラウスを引き合いに出し、
“ジャックはマスターズ選手権の最終日でもスイングを変えることを厭わなかった。”
変えることに対する「恐怖」に打ち勝つしかないのだと述べている。
最後に次のように語っている。
“ゴルフにおいて「己を知る」ということだ。そこに他人が入り込む余地などない。自分自身を信じ、皆、はい上がっていくしかない。”
信じるものは自分だけ、恐怖に打ち勝ち、はい上がる、それしかないという。煉獄の道だ。
この暗示に満ちたワトソンの記事が出たのが5月30日。そしてその翌々日の6月1日に新しいヒーローが誕生した。
「松山英樹、米ツアー初優勝 男子ゴルフ、日本勢で4人目」
なんという偶然、そしてあまりにも残酷で輝かしい希望。それでも、だからこそ、石川遼、がんばれ。
祈らずとても [新聞記事]
「私の履歴書」福地茂雄③、日本経済新聞、2014年6月3日朝刊を読んで
福地茂雄氏は、アサヒビールの社長会長を歴任された方だが、それよりその後NHK会長として活躍されたことの記憶が新しい。今回の「私の履歴書」は、まだ始まったばかりで、これからが楽しみなのだが、両親から受けた影響の大きさについて述べているところに強い印象を受けた。次のような書き出しである。
“両親の教えや振る舞いが私の人生に影響を与えたのは間違いない。とりわけ母の影は今でもつきまとっているような感じがする。”
「つきまとう」という表現が出るほどの典型的な、あるいは徹底的に厳しい「教育ママ」であったらしい。指導は小学校の卒業式の送辞文章にまで及び、母親の手による完全な添削指導を経て、次のようになったという。
“厳しい冬の寒さに耐えて、清く気高く咲き匂いし梅の花もいつしか散って、緋桃、白桃、木曽伊作弥生の候となりました。”
これはどうみても小学五年生の文ではないが、母親の際限のない愛情と熱心さは、まあよくわかる。げっぷの出るほどの深い愛ということか。
“母は長男である私を厳しくも、溺愛していた。こちらも反発することはなかった。実は社会人になっても帰郷するたびにお小遣いをくれた。特に断ることもないので、もらっていたが、さすがにアサヒビールの副社長になった頃には「もういいから」と小遣いはやめてもらった。”
もう一つ、福地氏が母親から受けた教えは「心」。
母親の口癖は、“心だに誠の道にかないなば祈らずとても神や守らん”、だったそうで、祈るという形ではなく心のありようだと。“母親が仏壇を前に手を合わせる姿は見たことがない。それでも朝3時には起きて、仏壇に水や花、ごはんを備えるなどが日課だった。”
祈らずとてもの句は、菅原道真の作と伝えられているのだが、大事なのは中身であり、形式に囚われてはいけないが、形もきちんと押さえなくてはいけないというのが、福地氏の母親の示した生き様だったのだろうか。
福地茂雄氏は、アサヒビールの社長会長を歴任された方だが、それよりその後NHK会長として活躍されたことの記憶が新しい。今回の「私の履歴書」は、まだ始まったばかりで、これからが楽しみなのだが、両親から受けた影響の大きさについて述べているところに強い印象を受けた。次のような書き出しである。
“両親の教えや振る舞いが私の人生に影響を与えたのは間違いない。とりわけ母の影は今でもつきまとっているような感じがする。”
「つきまとう」という表現が出るほどの典型的な、あるいは徹底的に厳しい「教育ママ」であったらしい。指導は小学校の卒業式の送辞文章にまで及び、母親の手による完全な添削指導を経て、次のようになったという。
“厳しい冬の寒さに耐えて、清く気高く咲き匂いし梅の花もいつしか散って、緋桃、白桃、木曽伊作弥生の候となりました。”
これはどうみても小学五年生の文ではないが、母親の際限のない愛情と熱心さは、まあよくわかる。げっぷの出るほどの深い愛ということか。
“母は長男である私を厳しくも、溺愛していた。こちらも反発することはなかった。実は社会人になっても帰郷するたびにお小遣いをくれた。特に断ることもないので、もらっていたが、さすがにアサヒビールの副社長になった頃には「もういいから」と小遣いはやめてもらった。”
もう一つ、福地氏が母親から受けた教えは「心」。
母親の口癖は、“心だに誠の道にかないなば祈らずとても神や守らん”、だったそうで、祈るという形ではなく心のありようだと。“母親が仏壇を前に手を合わせる姿は見たことがない。それでも朝3時には起きて、仏壇に水や花、ごはんを備えるなどが日課だった。”
祈らずとてもの句は、菅原道真の作と伝えられているのだが、大事なのは中身であり、形式に囚われてはいけないが、形もきちんと押さえなくてはいけないというのが、福地氏の母親の示した生き様だったのだろうか。
秀才は独創的でない [新聞記事]
「日本の生きる道」 私の履歴書、利根川進 (第30回)、日本経済新聞、2013.10.31 を読んで
この日で一か月続いた利根川進氏の連載が終了した。1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞し、現在もMIT教授など研究の第一線で活躍されている。研究は分子生物学や免疫学から始まって、現在では脳や神経の機能といった領域に対象を広げており、視野のきわめて広い知の巨人でもあることを連載から知ることができた。その連載の最終回では、科学者の適性という話題から入って、研究のような独創的な仕事をする者はどのようにして選ぶべきか、そうした視点では日本の大学の入試の仕組みはあまりに画一的に過ぎるとも述べている。
まず日本には人という資源しかないのだから、自ずと重きをおくべきは教育と研究であるとしている。
“日本は天然資源の限られた国です。世界の中でしっかりと認められて豊かな社会を維持していくには、人という資源を生かすしかないでしょう。そのためには教育と研究への投資が欠かせません。”
“21世紀はアジアの時代だといわれます。人口が多く経済発展の著しいこの地域では今、選ばれたリーダーたちが長期のビジョンを持って教育と科学技術に重点的に投資しています。”
表現は控えめだが、これに比べて日本には長期のビジョンがどこにあるかわからぬ状態で、教育にも研究にも力点が置かれていない惨憺たる状況であるとの厳しい指摘であろう。またMITでは、アジアの他の国から多くの若者が集まり競い合っている一方で、日本人留学生は激減しているという。
さらに、MITの学生の選び方は日本のように画一的ではなく、試験の点数の少しの多少よりも小論文と面接を重視し、MITが必要とする学生を見つけ出す努力を続けていること。さらには入学させた学生が本当にMITにとって必要な人材だったかを検証して、問題がある面接官はたちどころに交代させられるという。成績や点数も考慮はするが、MITの大学としての特徴を維持するためにはそれだけでは不十分というのがベースにあるという。
現在、日本でも大学の入学試験改革について試案が出されており、そこでも人物評価を面接で行うという考え方が示されてはいる。しかし、MITが行っているような方法に形だけ合わせても実質が果たして付いていくだろうか。それぞれの大学が歴史に裏打ちされた揺るぎない方針を掲げ、その維持と発展に必要な学生像が明瞭に示せるのであれば、そうした方法の意味はあるかもしれないが、はたしてどうか。極めて日本的に形態を充足して事足れりとしてしまう懸念がありはしないだろうか。
この点数至上主義から脱却する理由として、研究者としての資質について次のようにも述べている。
“研究のような創造的な仕事をする場合、試験で高得点を取れる秀才が適しているとは限りません。独創的であろうとすれば、かえってマイナス要因かもしれません。ある仮説を立てた時にどれくらい難しいかを予想できてしまい、高い目標に挑戦する強い意欲を持てなくなるからです。”
点数を取れることは必要条件だが、研究者としてはそれで十分ではないということなのだろう。人の能力と量るということは容易いことではない。あらためてそう感じた。
この日で一か月続いた利根川進氏の連載が終了した。1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞し、現在もMIT教授など研究の第一線で活躍されている。研究は分子生物学や免疫学から始まって、現在では脳や神経の機能といった領域に対象を広げており、視野のきわめて広い知の巨人でもあることを連載から知ることができた。その連載の最終回では、科学者の適性という話題から入って、研究のような独創的な仕事をする者はどのようにして選ぶべきか、そうした視点では日本の大学の入試の仕組みはあまりに画一的に過ぎるとも述べている。
まず日本には人という資源しかないのだから、自ずと重きをおくべきは教育と研究であるとしている。
“日本は天然資源の限られた国です。世界の中でしっかりと認められて豊かな社会を維持していくには、人という資源を生かすしかないでしょう。そのためには教育と研究への投資が欠かせません。”
“21世紀はアジアの時代だといわれます。人口が多く経済発展の著しいこの地域では今、選ばれたリーダーたちが長期のビジョンを持って教育と科学技術に重点的に投資しています。”
表現は控えめだが、これに比べて日本には長期のビジョンがどこにあるかわからぬ状態で、教育にも研究にも力点が置かれていない惨憺たる状況であるとの厳しい指摘であろう。またMITでは、アジアの他の国から多くの若者が集まり競い合っている一方で、日本人留学生は激減しているという。
さらに、MITの学生の選び方は日本のように画一的ではなく、試験の点数の少しの多少よりも小論文と面接を重視し、MITが必要とする学生を見つけ出す努力を続けていること。さらには入学させた学生が本当にMITにとって必要な人材だったかを検証して、問題がある面接官はたちどころに交代させられるという。成績や点数も考慮はするが、MITの大学としての特徴を維持するためにはそれだけでは不十分というのがベースにあるという。
現在、日本でも大学の入学試験改革について試案が出されており、そこでも人物評価を面接で行うという考え方が示されてはいる。しかし、MITが行っているような方法に形だけ合わせても実質が果たして付いていくだろうか。それぞれの大学が歴史に裏打ちされた揺るぎない方針を掲げ、その維持と発展に必要な学生像が明瞭に示せるのであれば、そうした方法の意味はあるかもしれないが、はたしてどうか。極めて日本的に形態を充足して事足れりとしてしまう懸念がありはしないだろうか。
この点数至上主義から脱却する理由として、研究者としての資質について次のようにも述べている。
“研究のような創造的な仕事をする場合、試験で高得点を取れる秀才が適しているとは限りません。独創的であろうとすれば、かえってマイナス要因かもしれません。ある仮説を立てた時にどれくらい難しいかを予想できてしまい、高い目標に挑戦する強い意欲を持てなくなるからです。”
点数を取れることは必要条件だが、研究者としてはそれで十分ではないということなのだろう。人の能力と量るということは容易いことではない。あらためてそう感じた。
出でよ大砲 [新聞記事]
「強打者を生む思想とは」豊田泰光、日本経済新聞、2013年9月19日朝刊を読んで
バレンティンのホームラン記録は止まらない。このままのペースがどこまで続くのかわからないが、少なくとも60本は容易に超えることは確実であろう。それはそれで素晴らしい成績なのだが、では日本人の長距離打者はどうやって育成すればよいのか、あるいは育ててもどこかに限界があるのか、一番気になるこの点について豊田氏はいつものように痛烈な辛口で指摘する。「日本からバレンティンは出てこない」と、そしてそれは決して「体格差の問題ではない」ともいう。
この結論を導いた典型的な例として、18歳以下のワールドカップの米国との決勝戦をあげている。日本代表はこの試合に敗れたのだが、その決定的な差は「スイングの強さ」であるという。この試合では、日本のエース松井裕樹に三振の山を築かれてはいたのだが、最後にはしぶとく安打を重ねて逆転している。「ハードヒット」できているか否かの差だというのだ。
“随分不格好な三振もあった。それでも米国の打者は振り続けた。三振を恐れないというより、フルスイングすることしか教えられずに育ってきた、とみえた。日本選手のスイングも相当なものだったが米国の迫力にはかなわない。”
この差は打撃に対する考え方の違いから来ると豊田氏は主張する。
“米国は「毎回クリーンヒットするのは難しい。打ち損じても外野の前に落ちるようなスイングをしよう」と考える。日本は「打ち損じをしないためにはどうするか」と考える”
“バットを振れるかどうかは人種の違いとか体格差の問題ではなく思想、教育の問題なのだ。”
“要は素材より育ち。少年野球まで遡って見直さないと、日本からバレンティンは出てこない。”
なるほどそういうものか、西鉄の大砲であった豊田氏が言うのだから技術的には正しいのかもしれない。でも、やや釈然としないところもある。最近ではイチローに代表されるような、安打製造機と呼ばれるくらいの打者をより贔屓するというところが日本の野球ファン全体にあるようにも思う。ブンブン振り回して、時々場外へ飛び出すような巨砲よりも、技巧派の打者が評価されるようなところがあるのではないか。宮本武蔵より佐々木小次郎を、弁慶より牛若丸を好む日本人の感性が、野球少年の未来を縛っているところがあるのではないか。まさに、文化の問題であり、未来永劫にバレンティンは現れないということになってしまう。しかし、それはそれでも良いように思っているのは私だけだろうか。
バレンティンのホームラン記録は止まらない。このままのペースがどこまで続くのかわからないが、少なくとも60本は容易に超えることは確実であろう。それはそれで素晴らしい成績なのだが、では日本人の長距離打者はどうやって育成すればよいのか、あるいは育ててもどこかに限界があるのか、一番気になるこの点について豊田氏はいつものように痛烈な辛口で指摘する。「日本からバレンティンは出てこない」と、そしてそれは決して「体格差の問題ではない」ともいう。
この結論を導いた典型的な例として、18歳以下のワールドカップの米国との決勝戦をあげている。日本代表はこの試合に敗れたのだが、その決定的な差は「スイングの強さ」であるという。この試合では、日本のエース松井裕樹に三振の山を築かれてはいたのだが、最後にはしぶとく安打を重ねて逆転している。「ハードヒット」できているか否かの差だというのだ。
“随分不格好な三振もあった。それでも米国の打者は振り続けた。三振を恐れないというより、フルスイングすることしか教えられずに育ってきた、とみえた。日本選手のスイングも相当なものだったが米国の迫力にはかなわない。”
この差は打撃に対する考え方の違いから来ると豊田氏は主張する。
“米国は「毎回クリーンヒットするのは難しい。打ち損じても外野の前に落ちるようなスイングをしよう」と考える。日本は「打ち損じをしないためにはどうするか」と考える”
“バットを振れるかどうかは人種の違いとか体格差の問題ではなく思想、教育の問題なのだ。”
“要は素材より育ち。少年野球まで遡って見直さないと、日本からバレンティンは出てこない。”
なるほどそういうものか、西鉄の大砲であった豊田氏が言うのだから技術的には正しいのかもしれない。でも、やや釈然としないところもある。最近ではイチローに代表されるような、安打製造機と呼ばれるくらいの打者をより贔屓するというところが日本の野球ファン全体にあるようにも思う。ブンブン振り回して、時々場外へ飛び出すような巨砲よりも、技巧派の打者が評価されるようなところがあるのではないか。宮本武蔵より佐々木小次郎を、弁慶より牛若丸を好む日本人の感性が、野球少年の未来を縛っているところがあるのではないか。まさに、文化の問題であり、未来永劫にバレンティンは現れないということになってしまう。しかし、それはそれでも良いように思っているのは私だけだろうか。
8000回の悔しさ [新聞記事]
「野球をするアスリート」武智幸徳氏、日本経済新聞2013年8月23日朝刊を読んで
イチローが日米通算で4千本の安打を積み重ねたその翌日のコラムである。「8000回以上は悔しい思いをしてきている」というイチローのインタビューがあまりに強烈で、誰が何を書いても、ほめようとけなそうと、この言葉の力にはかなわないだろうと勝手に考えていたのだが、武智氏の切り口は意表を突いていた。
イチローを野球選手だと思うなという。イチローはまずアスリートという定義で考えなければならないと。聞き違いかと確かめたくなるような主張だが、納得するところがある。つまり、従来のプロ野球選手は「職業」野球に従事する人のこと、さらに言えば野球で飯を食っている特殊技能の持ち主でしかなかったと。
“打撃術、投球術という言葉が表すように、ボールをバットの芯でとらえる、遠くへ飛ばす、狙ったところに投げる、といった術の習得こそ、この競技の肝。そのコツを体得する道のりは険しいが、投手以外は試合中にそれほど運動量は要求されない。メタボな体系になっても何かと許される範囲は大きい。”
武智氏は痛烈に書いているが、その技量は素人が届く類のものではないが、その一方で実はあまり体をいじめなくてもやっていける、要領さえわかれば、そして投手以外は試合中の体力はあまり要求されないのだと。
“「イチロー以前」のプロ野球には際どいタイミングで足を伸ばしてベースを踏むと肉離れを起こすとか、三塁打を放ってベースにたどりつくと肩でぜーぜー息をする選手がいた。「運動不足じゃないの?」と疑いたくなるようなスポーツ選手が。”
そう言えば確かに、巨漢の長距離打者や相撲取りかと見間違うような球界を代表する投手もいたような記憶がある。それでも素人にはできない術を操ることで、異人としての価値が認められてきたのだろう。それはそれで、否定するようなことでもないとは思う。
しかしアスリートとして人間の限界に挑むことが許されているほんの一握りのスポーツ選手達、その中に間違いなくイチローがいる。すべての人類から尊敬されうる領域のアスリートの一人が、たまたま選んだジャンルが野球だったということなのだ。
“私がスポーツ記者になりたてのころ、プロ野球選手は必ずしも他の競技者に尊敬されていなかった。喫煙、飲酒、有り余る運動能力を使い切っていない・・・・・・。五輪競技に打ち込む者たちの「やってもカネにならない自分たちの方がよほど厳しい練習をしている」という嘆きを何度も聞いた。イチローは今。プロ、アマ、競技の垣根を越えてアスリートとして尊敬されている。”
イチローが日米通算で4千本の安打を積み重ねたその翌日のコラムである。「8000回以上は悔しい思いをしてきている」というイチローのインタビューがあまりに強烈で、誰が何を書いても、ほめようとけなそうと、この言葉の力にはかなわないだろうと勝手に考えていたのだが、武智氏の切り口は意表を突いていた。
イチローを野球選手だと思うなという。イチローはまずアスリートという定義で考えなければならないと。聞き違いかと確かめたくなるような主張だが、納得するところがある。つまり、従来のプロ野球選手は「職業」野球に従事する人のこと、さらに言えば野球で飯を食っている特殊技能の持ち主でしかなかったと。
“打撃術、投球術という言葉が表すように、ボールをバットの芯でとらえる、遠くへ飛ばす、狙ったところに投げる、といった術の習得こそ、この競技の肝。そのコツを体得する道のりは険しいが、投手以外は試合中にそれほど運動量は要求されない。メタボな体系になっても何かと許される範囲は大きい。”
武智氏は痛烈に書いているが、その技量は素人が届く類のものではないが、その一方で実はあまり体をいじめなくてもやっていける、要領さえわかれば、そして投手以外は試合中の体力はあまり要求されないのだと。
“「イチロー以前」のプロ野球には際どいタイミングで足を伸ばしてベースを踏むと肉離れを起こすとか、三塁打を放ってベースにたどりつくと肩でぜーぜー息をする選手がいた。「運動不足じゃないの?」と疑いたくなるようなスポーツ選手が。”
そう言えば確かに、巨漢の長距離打者や相撲取りかと見間違うような球界を代表する投手もいたような記憶がある。それでも素人にはできない術を操ることで、異人としての価値が認められてきたのだろう。それはそれで、否定するようなことでもないとは思う。
しかしアスリートとして人間の限界に挑むことが許されているほんの一握りのスポーツ選手達、その中に間違いなくイチローがいる。すべての人類から尊敬されうる領域のアスリートの一人が、たまたま選んだジャンルが野球だったということなのだ。
“私がスポーツ記者になりたてのころ、プロ野球選手は必ずしも他の競技者に尊敬されていなかった。喫煙、飲酒、有り余る運動能力を使い切っていない・・・・・・。五輪競技に打ち込む者たちの「やってもカネにならない自分たちの方がよほど厳しい練習をしている」という嘆きを何度も聞いた。イチローは今。プロ、アマ、競技の垣根を越えてアスリートとして尊敬されている。”
コンサルタントの悪い癖 [読後の感想]
「不格好経営」南場智子、日本経済新聞出版社を読んで
読後感の悪い本に出会うことがときどきあるが、この本はかなり爽快だった。これからの南場さんの目指している世界のことも含めて、できれば続編を読みたいと感じた。ここでは、本筋であるDeNA成長のエピソードではなく、おそらく筆者は余談で書いたのだろうが、個人的にはいちばん受けてしまったところについて紹介したい。
それは、10年以上も世界有数のコンサルタント会社であるマッキンゼーに在籍していた南場氏ならではのコンサルタント批判である。批判と言っても、コンサルが不要だと言うのではなく、コンサルの陥りがちなケースを知っておくかどうかで、コンサルを使う側では大きな違いが生じうるということでもあろう。
事業を外から眺めて分析し提案するというコンサルの技法を身に着けてしまうと、いざ自分が事業を先頭に立って引っ張るときには、必ずしもそれがプラスには働かない、もっと言えば足を引っ張ることさえあるという。
“「するべきです」と「します」がこんなに違うとは”、と述べているが、これこそ実感だろう。
また、事業トップだけでなく、事業チームでも同じことが言えるという。
“迷いのないチームは迷いのあるチームよりも突破力がはるかに強いという常識的なことなのだが、これを腹に落として実際に身につけるまでには時間がかかった。”
チームを率いるリーダーに求められることについて次のようにも述べている。
“リーダーの胆力はチームの強さにそのまま反映される。それが、クライアントに「役立ったか」、クライアントを 「impress したか」を四六時中気にしていたコンサルタント出身者にとってはとても大きなジャンプなのだ。”
このコンサルティングの目的と顧客への配慮が必ずしも同じにはならないという点は少しわかりにくいが、これについては、さらに突っ込んで、南場氏はこれらを「事業にマイナスな姿勢」と呼んで以下のように厳しい指摘をしている。
第一は、できる限り「賢く見せよう」とする姿勢。確かにコンサルは切れ者でかつ賢いなあとクライアントに思わせないと、まず仕事はとれない。高額のフィーを払って、事業の抱える問題を洗い出してもらおうと考えるトップにしてみれば、自分よりも賢くは見えない相手をコンサルに使おうとは、普通は考えない。その結果として、コンサルは賢く見せてあたりまえということになる。しかし、この「賢い」態度が事業の現場ではなんの薬にもならない、アホをさらけだしても切り抜けなければならないことのほうがよっぽど多いのだと指摘する。しかし、これを逆にとれば、賢く見せようとしている事業トップがいたら(というかよく見かけるが)、その会社は危ないという黄信号を出しているともいえるかもしれない。
第二は、「上から目線」。コンサルティング会社ではよく、「あの事業部長はわかっていない」などという類の会話がストレス解消のつもりで口にされることがあるが、これを若手のコンサルタントが耳にしているうちに、たいがいのクライアントはアホと錯覚し、いつしか残念なことに目線が高くなってしまうという。先の「賢い」といい、「上から目線」といい、コンサルというのはいやな人種だと思われてなんぼということなのだろうが、外から見れば痛い話ではある。
第三は、クライアントの中で誰がキーパーソンかを素早く見極め、その人に「おもねる」発言をすることが多いという点。こういう提案はキーパーソンのA氏には必ず受けるという計算が自動的に働いてしまうということだろうか。おもねるというアクション、実はこの時点で第三者であるべきコンサルではなくなっているのだが、おそらく多くのコンサルタントはこれを認めないだろうとも南場氏は述べている。しかし、ここはかなり微妙かもしれない。キーパーソンが納得しないアイデアでは実行に移しがたいので、同化することを全否定するべきではないという意見もあるだろう。しかし、南場氏の言っているのは、そうした性癖が事業リーダーであるときに顔を出したらもうおしまいだという警告である。リーダーが自らの信念にこだわらずに、誰かに「おもねる」態度を見せた瞬間に組織は持たないということを経験として強調しているのだろう。
そんな癖を持っているであろうコンサル会社からも、その才能を信じてDeNAでは採用を続けているという。面白いのは、そうしたコンサル出身者への南場氏の具体的な次のアドバイスである。
・何でも3点にまとめようと頑張らない。物事が3つにまとまる必然性はない。 ・重要情報はアタッシュケースではなくアタマに突っ込む ・自明なことを図にしない ・人の評価を語りながら酒を飲まない ・ミーティングに遅刻しない
読後感の悪い本に出会うことがときどきあるが、この本はかなり爽快だった。これからの南場さんの目指している世界のことも含めて、できれば続編を読みたいと感じた。ここでは、本筋であるDeNA成長のエピソードではなく、おそらく筆者は余談で書いたのだろうが、個人的にはいちばん受けてしまったところについて紹介したい。
それは、10年以上も世界有数のコンサルタント会社であるマッキンゼーに在籍していた南場氏ならではのコンサルタント批判である。批判と言っても、コンサルが不要だと言うのではなく、コンサルの陥りがちなケースを知っておくかどうかで、コンサルを使う側では大きな違いが生じうるということでもあろう。
事業を外から眺めて分析し提案するというコンサルの技法を身に着けてしまうと、いざ自分が事業を先頭に立って引っ張るときには、必ずしもそれがプラスには働かない、もっと言えば足を引っ張ることさえあるという。
“「するべきです」と「します」がこんなに違うとは”、と述べているが、これこそ実感だろう。
また、事業トップだけでなく、事業チームでも同じことが言えるという。
“迷いのないチームは迷いのあるチームよりも突破力がはるかに強いという常識的なことなのだが、これを腹に落として実際に身につけるまでには時間がかかった。”
チームを率いるリーダーに求められることについて次のようにも述べている。
“リーダーの胆力はチームの強さにそのまま反映される。それが、クライアントに「役立ったか」、クライアントを 「impress したか」を四六時中気にしていたコンサルタント出身者にとってはとても大きなジャンプなのだ。”
このコンサルティングの目的と顧客への配慮が必ずしも同じにはならないという点は少しわかりにくいが、これについては、さらに突っ込んで、南場氏はこれらを「事業にマイナスな姿勢」と呼んで以下のように厳しい指摘をしている。
第一は、できる限り「賢く見せよう」とする姿勢。確かにコンサルは切れ者でかつ賢いなあとクライアントに思わせないと、まず仕事はとれない。高額のフィーを払って、事業の抱える問題を洗い出してもらおうと考えるトップにしてみれば、自分よりも賢くは見えない相手をコンサルに使おうとは、普通は考えない。その結果として、コンサルは賢く見せてあたりまえということになる。しかし、この「賢い」態度が事業の現場ではなんの薬にもならない、アホをさらけだしても切り抜けなければならないことのほうがよっぽど多いのだと指摘する。しかし、これを逆にとれば、賢く見せようとしている事業トップがいたら(というかよく見かけるが)、その会社は危ないという黄信号を出しているともいえるかもしれない。
第二は、「上から目線」。コンサルティング会社ではよく、「あの事業部長はわかっていない」などという類の会話がストレス解消のつもりで口にされることがあるが、これを若手のコンサルタントが耳にしているうちに、たいがいのクライアントはアホと錯覚し、いつしか残念なことに目線が高くなってしまうという。先の「賢い」といい、「上から目線」といい、コンサルというのはいやな人種だと思われてなんぼということなのだろうが、外から見れば痛い話ではある。
第三は、クライアントの中で誰がキーパーソンかを素早く見極め、その人に「おもねる」発言をすることが多いという点。こういう提案はキーパーソンのA氏には必ず受けるという計算が自動的に働いてしまうということだろうか。おもねるというアクション、実はこの時点で第三者であるべきコンサルではなくなっているのだが、おそらく多くのコンサルタントはこれを認めないだろうとも南場氏は述べている。しかし、ここはかなり微妙かもしれない。キーパーソンが納得しないアイデアでは実行に移しがたいので、同化することを全否定するべきではないという意見もあるだろう。しかし、南場氏の言っているのは、そうした性癖が事業リーダーであるときに顔を出したらもうおしまいだという警告である。リーダーが自らの信念にこだわらずに、誰かに「おもねる」態度を見せた瞬間に組織は持たないということを経験として強調しているのだろう。
そんな癖を持っているであろうコンサル会社からも、その才能を信じてDeNAでは採用を続けているという。面白いのは、そうしたコンサル出身者への南場氏の具体的な次のアドバイスである。
・何でも3点にまとめようと頑張らない。物事が3つにまとまる必然性はない。 ・重要情報はアタッシュケースではなくアタマに突っ込む ・自明なことを図にしない ・人の評価を語りながら酒を飲まない ・ミーティングに遅刻しない
生きねば。 [映画を見て]
「風立ちぬ」宮崎駿監督作品を観て
映画の見方はいろいろあるだろうし、人それぞれでよいのだが、観る前に必要な情報を頭に入れておくほうが感動がより深まる場合と、なんにも知らずにびっくり箱の蓋をあけるようにワクワクドキドキで観た方が良い場合とがあることだけは間違いない。宮崎駿版「風立ちぬ」の場合は、どうやらある程度の予習はしておいたほうが良かったかなというのが、観終えてからの感想だが、まったく白紙でも作品から受ける感動が薄っぺらになるというわけでもない。いいものは、とにかく、いいのだ。不足していた知識を加えてから、また観ればよいのだ。繰り返して噛むほど味が出るということ。それでも、なんにも知りません状態をぎりぎりで救ってくれたのは、映画鑑賞ビラの裏にあった宮崎駿の企画文書で、どんな作品を造ろうとしていたかが精緻にかつ熱く語られており、これを開幕の直前に読むことができたのは大きかった。
とくに、以下の部分が作品舞台の時代背景を知るには重要であろう。
“私達の主人公が生きた時代は今日の日本にただよう閉塞感のもっと激しい時代だった。関東大震災、世界恐慌、失業、貧困と結核、革命とファシズム、言論弾圧と戦争につぐ戦争、一方大衆文化が開花し、モダニズムとニヒリズム、享楽主義が横行した。詩人は旅に病み死んでいく時代だった。 私達の主人公二郎が飛行機設計にたずさわった時代は、日本帝国が破滅にむかってつき進み、ついに崩壊する過程であった。”
作品のストーリーやアニメとしての評価などをここで追いかけることはしないが、気になった二つのアイテムについてだけ触れておきたい。最初は、技術用の計算尺である。数値計算を必須としている設計屋には、なくてはならない道具で、対数表や三角関数表が埋め込まれたアナログ計算機なのだが、これを折れた足の添え木にするという登場のさせ方が面白い。しかも作品の後半の重要な場面でも繰り返し使われている。こんなに計算尺が出てくる映画作品は今までなかったのではないだろうか。主人公はとにかく計算の鬼なのだ。
もうひとつは、サバの骨である。主人公はとにかくサバが好物なのだが、食事中に口の中からサバの骨をすっと取り出し、しげしげと見つめ、いい形をしているとつぶやく。このシーンはかなり重要で、美しいものを造りだすことに徹底的にこだわる達人名人が生まれる予感を、小さな骨が暗示する。構造的に強いものは、姿も美しいはずという仮説から出発し、その先にある解答を探しているうちに、やがて美と真理の魔力に引き込まれていくのだ。
“美しすぎるものへの憬れは、人生の罠でもある。美に傾く代償は少くない。二郎はズタズタにひきさかれ、挫折し、設計者人生をたちきられる。”
それにしても、と思う。何年かのインターバルを置いてまた我々は新しい宮崎作品と出会うことができた。作品による評価の振れはあるのかもしれないが、そんなことはどうでもいい。宮崎駿という才能と同じ時代に生きていることそのものが、とてつもない幸福だと言い切ってよいのではないか。やがてすべてがライブラリとして蓄積されていても、新しい作品に出合う瞬間の輝きは、その時にしか味わえない贅沢の極みなのだ。
岩盤のごとき規制 [新聞記事]
「成長戦略の評価(上):経済教室」、八田達夫大阪大学招聘教授、日本経済新聞、2013.6.19 を読んで
安倍政権の打ち出した成長戦略、なかでも「規制改革」に対する市場の反応は必ずしも芳しいものではない。またぞろ規制改革か、民主党の仕分けとどう違うかとか、小泉改革の焼き直しか等々。八田氏によれば、規制改革が成長戦略の先頭に立つべき理由が詳細には語られていないことと作戦計画が示されていないことだという。いちばん大事なことは、わかりやすく説明しなければだめということだろう。
時代に合わないような、あるいは不合理な規制や仕組みは、すぐにでも廃止し改革すべきくらいのことは、正直誰にでも言えそうだし、反対をする理由などないように思える。ところが、日本の社会はどこを向いても規制だらけで、いつできたかさえ忘れられているほどその命を長らえている。なぜ、そうした規制が長く維持されているのか、まずそこに目を向けなければ、岩盤のごとき規制は破れないという。
“日本では戦後の成功神話に酔いしれているうちに国の至るところで既得権がうごめき、数多くの参入規制ができた。このため成長産業に資源が移動しなくなり成長がとまってしまった。”
すべてが灰燼に帰した戦後の日本、そこから復興への長く厳しい道を歩んで築き上げてきたもの、(会社、雇用、市場...)を喪う恐怖が最大の動機となり、徹底した守りの姿勢がムラを維持するルールを必要とした。いったん懐に入れたものは、限られた仲間とともに、できるだけ長く保持したい。これが既得権を手に入れた者が考えるきわめてわかりやすい論理である。
“しかし経済成長がある程度進んだ段階では、既得権を持つ成熟産業は新産業の成長を止めようとする。そのために既得権集団は、様々な口実をつくり、政治家を使って、参入規制を法制化する。参入規制は、新陳代謝を阻害し、成長を止める最大の要因である”
とにかく排除の論理が「制度」になってしまうと、もうどうしようもない、ガチガチの岩盤そのものだという。八田氏は岩盤法制の代表として、国家公務員制度と雇用法制をあげているが、とくに雇用法制は労働力の流動性を著しく低下させており、日本の成長への大きな阻害要因になっていると指摘する。
近年になって若年労働者の比率が低下する中で、不足する労働力を補うために有期雇用の比率が急速に高まっているのだが、労働の流動性は一向に高まらない。これは5年雇い止めルールが有期雇用とセットになっているためで、有期雇用になることは不利だと誰もが考えることにつながる。これでは会社にしがみついていたほうがずっとましだと誰もが考えるようになり、労働の流動化はいつまでも生じず、したがって有期雇用で優れた人を高い報酬で雇うことなどいつまでもできはしない。
雇い止めルールがあるので、企業の人件費負担が低く抑え込められると規制が評価されることもあるが、企業の競争力の源泉が人材であることを忘れた議論だと言わざるをえない。人的蓄積が企業の優勝劣敗を決定するという戦略要件が頭から完全に抜け落ちている。人に投資しない社会は衰退するしかないのだ。
規制の岩盤は、雇用ひとつとっても、かくのごとく厚く手ごわい。今の日本で、ほんとうにこれらを打ち破ることはできるのだろうか・・・
安倍政権の打ち出した成長戦略、なかでも「規制改革」に対する市場の反応は必ずしも芳しいものではない。またぞろ規制改革か、民主党の仕分けとどう違うかとか、小泉改革の焼き直しか等々。八田氏によれば、規制改革が成長戦略の先頭に立つべき理由が詳細には語られていないことと作戦計画が示されていないことだという。いちばん大事なことは、わかりやすく説明しなければだめということだろう。
時代に合わないような、あるいは不合理な規制や仕組みは、すぐにでも廃止し改革すべきくらいのことは、正直誰にでも言えそうだし、反対をする理由などないように思える。ところが、日本の社会はどこを向いても規制だらけで、いつできたかさえ忘れられているほどその命を長らえている。なぜ、そうした規制が長く維持されているのか、まずそこに目を向けなければ、岩盤のごとき規制は破れないという。
“日本では戦後の成功神話に酔いしれているうちに国の至るところで既得権がうごめき、数多くの参入規制ができた。このため成長産業に資源が移動しなくなり成長がとまってしまった。”
すべてが灰燼に帰した戦後の日本、そこから復興への長く厳しい道を歩んで築き上げてきたもの、(会社、雇用、市場...)を喪う恐怖が最大の動機となり、徹底した守りの姿勢がムラを維持するルールを必要とした。いったん懐に入れたものは、限られた仲間とともに、できるだけ長く保持したい。これが既得権を手に入れた者が考えるきわめてわかりやすい論理である。
“しかし経済成長がある程度進んだ段階では、既得権を持つ成熟産業は新産業の成長を止めようとする。そのために既得権集団は、様々な口実をつくり、政治家を使って、参入規制を法制化する。参入規制は、新陳代謝を阻害し、成長を止める最大の要因である”
とにかく排除の論理が「制度」になってしまうと、もうどうしようもない、ガチガチの岩盤そのものだという。八田氏は岩盤法制の代表として、国家公務員制度と雇用法制をあげているが、とくに雇用法制は労働力の流動性を著しく低下させており、日本の成長への大きな阻害要因になっていると指摘する。
近年になって若年労働者の比率が低下する中で、不足する労働力を補うために有期雇用の比率が急速に高まっているのだが、労働の流動性は一向に高まらない。これは5年雇い止めルールが有期雇用とセットになっているためで、有期雇用になることは不利だと誰もが考えることにつながる。これでは会社にしがみついていたほうがずっとましだと誰もが考えるようになり、労働の流動化はいつまでも生じず、したがって有期雇用で優れた人を高い報酬で雇うことなどいつまでもできはしない。
雇い止めルールがあるので、企業の人件費負担が低く抑え込められると規制が評価されることもあるが、企業の競争力の源泉が人材であることを忘れた議論だと言わざるをえない。人的蓄積が企業の優勝劣敗を決定するという戦略要件が頭から完全に抜け落ちている。人に投資しない社会は衰退するしかないのだ。
規制の岩盤は、雇用ひとつとっても、かくのごとく厚く手ごわい。今の日本で、ほんとうにこれらを打ち破ることはできるのだろうか・・・
はだかの王様 [新聞記事]
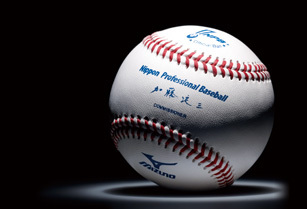 「コミッショナーの選び方」、“選球眼”、島田健(編集委員)、2013年6月17日、日本経済新聞朝刊を読んで
「コミッショナーの選び方」、“選球眼”、島田健(編集委員)、2013年6月17日、日本経済新聞朝刊を読んでいったい何を隠しているのか。真実を話せない理由はなんなのか。
突如として大きな話題となっている統一球問題だが、新聞、TVなど、どのメディアを見ても裏に隠されている「事情」がまったくわからず、首をかしげていた。それが、このコラムを読んで氷解した。
WBCなどを強く意識して採用した統一球があまりに飛ばないため、プロ野球の魅力を大きく損なってしまったという認識が最初にあった。野球の醍醐味はホームランにつきる。これを取り戻すために、球に少し手を加えて元のように飛ぶボールにしよう。ここまでは、そんなにおかしな動機ではないのだが、これを極秘に行うことにしたところですべてが歪んでしまった。
オーナー会議という日本野球機構の意思決定機関に諮ることなく進めたというのは、球の変更に同意が得られないと見込んだのか、あるいはガバナンス無視かよくわからないが、ボールの中身をちょっといじっても誰にもわかりはしないし、ホームランが量産されて文句を言うやつはいないはずだという勝手な決めつけがあったのだろう。この判断をコミッショナーがしたとすると、それはそれですごい(まったく同意できないが)決断だと思っていたのだが、島田氏の指摘するように球界の影の実力者がすべてを仕切っていたのだとすれば、なあんだそういうことかとストンと腹に落ちた。
“加藤氏の指示でないのが事実なら、球界で同氏を上回る力を持つ、誰か(またはグループ)が、変更に消極的だったとされる加藤氏に代わって指示したとしか思えない。”
つまり現在のコミッショナーはお飾りにすぎないということなのだ。島田氏は次のように書いている。
“まず、コミッショナーの選び方を公明正大にすべきだろう。加藤氏がどうして選ばれたか、実はよくわからなかった。野球好きの元駐米大使というのは有名だが、誰が推薦したのかわからないうちに決まっていた。球界の影の実力者が決めたというのが大方の見方で、それなら今回、統一球を「調整」しようとする動きがあったことを加藤氏が知っていたとしても、とやかく言えないのも納得できる。”
この辺りのことは噂だとしながらも、すべてが闇の中で決められている機構の怪しさと危うさを的確に突いている。こんなコラムは日経でないと載せられないし、もちろんTVでは絶対に取り上げられないのだろう。影の実力者というのは、十人が十人すぐにあの人とわかってしまうのだが、今回の件に限ってみれば、その「誰か」がすべての根源だとは思えないところもある。陰謀の「源」といった論説は分かり易いが、こうした決め付けはしばしば本質を見失う。むしろ、プロ野球という歴史の長い巨大業界に居座る「既得権益集団」が、絵を描き密かに実行に移したのだと考えるほうが自然であろう。
コミッショナー側にはなんの権限もない、さらに踏み込めば「はだかの王様」でしかなかったと素直に認めれば話は簡単なはずなのだ。もっとも、そんな芸当ができていれば今の混乱はないのだろうが。
島田氏は江川事件後のプロ野球界の混乱を裁いた下田武三コミッショナー(1979-1985年)を高く評価しており、こうした硬骨な人でなければ今後の改革は難しいと述べている。
“巨人の不祥事である「江川事件」の後、1979年から85年まで務めた下田武三氏は元最高判事。「正しいものは正しい、悪いものは悪い」と飛ぶボール、飛ぶバットなどの禁止や球場規模の適正化を進めた名コミッショナーだ。下田さんは厳正過ぎるほどのやり方でセ・リーグ側と相いれず、2期で辞任し、球界近代化の功績がありながら、殿堂入りも果たしていない。今、改革を期待するならひも付きでない、同氏のような硬骨の人こそ必要である。”
会津武士のように「ならぬものは、ならぬ」と、影の実力者の首に鈴を着けに行くのは、いったい誰になるのだろう。
前の10件 | -



