12月23日の刻印 [読後の感想]

「ジミーの誕生日」猪瀬直記著(「東條英機 処刑の日」に改題)を読んで
太平洋戦争が日本の敗戦で終わり、米軍による占領が始まって3年が経過した昭和23年12月23日の異様なできごとをプロローグとしてこの話しは始まる。極東国際裁判のA級戦犯28人の内、死刑を宣告された7人の刑が、22日の深夜から日付が23日に変わるころ、巣鴨プリズンにて密やかに執行された。こうした大きな事象の実行にこの日がなぜ選ばれたのか、これが大きなテーマとなってストーリーが進んでいく。ここから話しは一旦昭和20年8月の終戦受諾の時に戻り、終戦を挟んで起きたさまざまな事実を示しながら、徐々にミステリーのような展開をみせる。
第一章は筆者である猪瀬氏の許に届いた女性からの手紙から始まる。子爵婦人であったというその女性の祖母が住んでいた洋館から古い日記が見つかった。その日記の最後が昭和23年12月7日で終わっており、そこにはただ「ジミーの誕生日の件、心配です」とだけ書かれているというのだ。これは、いったい何のことか。占領という特殊な状況下で何が起きていたというのか。
調べていくと、日記の主である子爵夫人の息子は当時の皇太子と学習院初等科で同級生であったことが明らかになる。そこから、この深い霧のような謎が解け始めていく。米国のマッカーサーによる占領政策の下で、戦争の責任をどう取らせるか、そしてその効果を最大化させるにはどうすべきかという一点に向けて、すべてが明瞭に意図され企てられ、そして淡々と進められていたということを、もつれた糸を一つひとつほぐす様に浮かび上がらせている。
選んだ占領政策を深く浸透させるための最大の仕掛けは、すべての日本人がいつまでも忘れない刻印を残すことであるとマッカーサーは決意しそのとおりに実行された。その仕掛けが日本にとってどれだけ重いものであったか、敗戦から半世紀を経たいまだからこそ、すべての日本人の心の奥深く押された刻印の意味を噛みしめるときなのかもしれない。
それにしても、またあのチャールズ・ケーディスと出合ってしまった。前に白洲次郎を取り上げたときに、占領政策の実行部隊のキーマンとして日本国憲法の草案を作成したGHQのケーディスに着目していたのだが、まさか「ジミーの誕生日」でもこんなに重要な役を担っていたとは。しかも子爵婦人との関係など、あまりにドラマティックな展開。ここまで来ると、誰かケーディスを主人公にしたストーリーを書いてはくれないだろうかと思いたくなる。小説でなくとも映画化でもよい。マッカーサーの占領政策の背後でこんなことが動いていたなんて。
戦争は官吏の事務 [読後の感想]
「昭和16年夏の敗戦」猪瀬直樹、中公文庫版(2010年6月)、を読んで
太平洋戦争の開戦の半年ほど前の夏に、官僚・軍人・民間人から集められた若き俊才達35名が、やがて直面する戦争を精緻に机上演習(シミュレーション)し、最後に到達した結論は日米戦日本必敗という紛れもない敗北であった。
この本のあらすじをまとめるとこのようになる。事前に知識がないままに読み始めてしまうと、これはフィクションなのか実録なのかという疑問がすぐに湧いてくる。あたかも、パラレルワールドとしての太平洋戦争を見つめるもう一つの目が存在し、最悪の選択を避けようと歴史に抗ったもう一つの開戦史のようだ。ところが、これはまぎれもない史実なのだ。昭和20年夏の敗戦の4年も前に、はっきりと結末が見えていたにもかかわらず、この予測は一切顧みられることなく歴史の闇に沈んでいった。
この舞台となったのは、太平洋戦争直前の昭和15年に設置された「総力戦研究所」。名称からは軍事に特化したシンクタンクのようにもみえるが、むしろ養成学校といったほうが設立の目的には近かったかもしれない。この研究所は、英国の国防大学を範として計画されたという。英国国防大学とは、単なる軍事の高等教育機関ではなく、軍部と他の政府機関との連携強化をはかり、かつその要員を養成するために設けられている。学生は少佐中佐クラスの軍人と主要官庁の適任者からなり、教官は佐官クラスの将校と政治経済等の学識経験豊かな専門の文官からなる。この結果として、国の将来を託すような第一級の軍民エリートがここから連輩出することになる。軍部とシビリアンが一体となって国外の敵あるいは競争相手に対峙しなければ、国際競争の嵐に沈むしかないという危機感がその底流にある。それにしても、開戦の直前にならないとこうした機関を設けることにすらならなかったというのも日本の実力であったのだろう。
日米開戦の裏に隠された秘話のひとつだが、日本が抱える組織の病癖であり、そのまま現代に通じる問題と見ることもできる。この研究所に集められ予測を命じられたエリート達だけが日本の敗戦を見通していたのではなく、実は軍部も官僚も同じような見通しを持っていた。いつか形成されていく空気の流れが、開戦以外の可能性を順に消していき、やがて一つしかない答えに全体が少しずつ向かっていくことになる。
東京裁判における東条英機の口述に関連して当時の毎日新聞の「余録」は「これでは戦争は、最高の『政治』ではなく、官吏の『事務』となる。全く満州事変以来の戦争はそれ以外のものでなく、一人の政治家もいなかったのだ」と匙を投げているが、この指摘のとおりそこには官僚の生真面目な、まさに司つかさたる働きしか存在してはいなかった。事実に執着するあまり、やがて事実に畏怖をいだくようになり、本来の目的からいつか離脱しつじつま合わせに走るしかなくなる。これと唯一対立するのが政治であり、政治は目的のために事実を従属させるためにこそ存在するのだが「余録」が指摘するように、どこにも政治はなかったのだ。
この不思議な史実書(フィクションではなく)の最後は、総力戦研究所で机上演習を行った35名の人たちのその後で締めくくられている。後に大会社の経営を担った者や官僚の頂点を極めた者も少なくはないのだが、はっきりと全員に共通した点がある。それは、これだけの経験を積んだにもかかわらず、誰一人として政治の道には入ろうとはしなかったことだ。これは、あまりに象徴的に過ぎて言葉もない。
3.11から4ヶ月が過ぎてしまったが、やはりいまの日本にも政治の姿は見えない。
太平洋戦争の開戦の半年ほど前の夏に、官僚・軍人・民間人から集められた若き俊才達35名が、やがて直面する戦争を精緻に机上演習(シミュレーション)し、最後に到達した結論は日米戦日本必敗という紛れもない敗北であった。
この本のあらすじをまとめるとこのようになる。事前に知識がないままに読み始めてしまうと、これはフィクションなのか実録なのかという疑問がすぐに湧いてくる。あたかも、パラレルワールドとしての太平洋戦争を見つめるもう一つの目が存在し、最悪の選択を避けようと歴史に抗ったもう一つの開戦史のようだ。ところが、これはまぎれもない史実なのだ。昭和20年夏の敗戦の4年も前に、はっきりと結末が見えていたにもかかわらず、この予測は一切顧みられることなく歴史の闇に沈んでいった。
この舞台となったのは、太平洋戦争直前の昭和15年に設置された「総力戦研究所」。名称からは軍事に特化したシンクタンクのようにもみえるが、むしろ養成学校といったほうが設立の目的には近かったかもしれない。この研究所は、英国の国防大学を範として計画されたという。英国国防大学とは、単なる軍事の高等教育機関ではなく、軍部と他の政府機関との連携強化をはかり、かつその要員を養成するために設けられている。学生は少佐中佐クラスの軍人と主要官庁の適任者からなり、教官は佐官クラスの将校と政治経済等の学識経験豊かな専門の文官からなる。この結果として、国の将来を託すような第一級の軍民エリートがここから連輩出することになる。軍部とシビリアンが一体となって国外の敵あるいは競争相手に対峙しなければ、国際競争の嵐に沈むしかないという危機感がその底流にある。それにしても、開戦の直前にならないとこうした機関を設けることにすらならなかったというのも日本の実力であったのだろう。
日米開戦の裏に隠された秘話のひとつだが、日本が抱える組織の病癖であり、そのまま現代に通じる問題と見ることもできる。この研究所に集められ予測を命じられたエリート達だけが日本の敗戦を見通していたのではなく、実は軍部も官僚も同じような見通しを持っていた。いつか形成されていく空気の流れが、開戦以外の可能性を順に消していき、やがて一つしかない答えに全体が少しずつ向かっていくことになる。
東京裁判における東条英機の口述に関連して当時の毎日新聞の「余録」は「これでは戦争は、最高の『政治』ではなく、官吏の『事務』となる。全く満州事変以来の戦争はそれ以外のものでなく、一人の政治家もいなかったのだ」と匙を投げているが、この指摘のとおりそこには官僚の生真面目な、まさに司つかさたる働きしか存在してはいなかった。事実に執着するあまり、やがて事実に畏怖をいだくようになり、本来の目的からいつか離脱しつじつま合わせに走るしかなくなる。これと唯一対立するのが政治であり、政治は目的のために事実を従属させるためにこそ存在するのだが「余録」が指摘するように、どこにも政治はなかったのだ。
この不思議な史実書(フィクションではなく)の最後は、総力戦研究所で机上演習を行った35名の人たちのその後で締めくくられている。後に大会社の経営を担った者や官僚の頂点を極めた者も少なくはないのだが、はっきりと全員に共通した点がある。それは、これだけの経験を積んだにもかかわらず、誰一人として政治の道には入ろうとはしなかったことだ。これは、あまりに象徴的に過ぎて言葉もない。
3.11から4ヶ月が過ぎてしまったが、やはりいまの日本にも政治の姿は見えない。
麻薬の世界へようこそ [読後の感想]
"<麻薬>のすべて” 船山信次、講談社現代新書 を読んで
"破滅”や"終焉"といったことさらに刺激の強い言葉を、赤く巨大な文字で威嚇するように投げつける夕刊紙群。負けじと週刊誌などの雑誌がこれを追いかけ、いつのまにか新書の帯もこの路線に追随しているものが増えた。その理由はわからないでもないが、それにしても、いかにも売らんかなというのが多い、というかいつのまにか随分と下品になってしまったなあと感じることが多い。でも、きれいごとだけでは生きていけないのも確かだろう。
そんな過激な"売れさえすれば"いいというのと少し趣の異なる本を、古くからの友人である著者より献本頂いた。新書を包んでいる帯の下半分が植物図鑑を思わせる絵柄で、まずそこらの通俗的な麻薬本でないことをしっかりと主張している。よく見ると、表に麻とケシが、裏はタバコとチョウセンアサガオである。(タバコは麻薬じゃないなどと野暮なことは言わない)
この本が書かれた意図はなんだろうか。MDMAと押尾学の話にフォーカスした芸能界などの華やかな人脈に切り込むといった裏話的刺激はまったくない。そうしたことを期待する人は、この本を手にすることすらやめたほうがよい。祟りで目がつぶれるに違いない。
犯罪として麻薬の常用や人体への影響などがときたま取り上げられることはあっても、麻薬そのものの来歴や分類について啓蒙的な視点からまとめたものがほとんどないことが、実は結果として日本での麻薬の蔓延を助長しているという著者の考えに立ってまとめられたものだ。これについて著者は、寺田虎彦の「ものをこわがわらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしい」という言葉を引用して、麻薬の認識もまさにこれだと述べている。なるほど、"正当にこわがる”のは難しいね、確かに。原発に対するここのところの喧々諤々は、まさにこのことだと気がつく。
ちゃんと知っていますか? そう言われてみると、モルヒネ、コカイン、覚せい剤、大麻と並べられても、名前は聞いたことがあるが、なにが違うのか、なぜそんなにいろいろ存在するのかなど、ほとんど知らないということにすぐ気がつく。麻薬というと、悪魔の薬であり、とにかく近づいてはいけない、「禁」というのが第一勘。一方で、それだけ禁じられていても、人をひきつける魔力の秘密の匂いも気になるところだ。
内容は深すぎてとても要約できるような類のものではないが、章立て(1から5章まで)でおおよその流れを知ることはできる。
第1章 ケシと阿片とモルヒネ・ヘロイン
第2章 コカとコカイン
第3章 麦角とLSD
第4章 麻王と覚せい剤
第5章 アサと大麻
いずれも、由来となる植物から、如何にして麻薬が引き出されたかというヒトと麻薬の不思議な出会いの歴史を軸にして論を進めている。マフィアの道具といったステレオタイプなイメージがここで完全に覆ること請け合いである。麻薬と人類の遭遇について著者は次のように述べている。
ケシやコカや大麻のような植物がヒトの脳に何らかの作用をおよぼす化合物を作り出しているということは不思議なことである。なぜ、これらの植物がヒトの脳に作用する化合物を作り出しているのであろうか。この疑問に答えるすべはない。生物の多様性というが、生物はとにかく、生き抜いていく過程においてありとあらゆる方向に進化した。その中でたまたま、ヒトにとって麻薬と称される化学成分をつくり出す植物やきのこなどもあらわれたとしかいわざるを得まい。偶然という他ないのである。
さらに著者は本の最後で、"地球というこの孤独な星に、今日に至るまでの過酷な生存競争に打ち勝って生息してきた私たち人類の今後の存続を決めるのは、環境・食料・資源・疾病などに加え、皮肉なことに人類の英知がもたらした「ヤク(薬)とカク(核)」であると思っている”と述べ、さらに、"皮肉なことに今や人類によってこの世に生み出された麻薬と核の存在によって、自身がその存亡の瀬戸際にたたされているわけである。まさに、ヤクとカクの扱いは人類に未来があるか否かの鍵をにぎっていると言ってもよかろう。人類の知恵によって、麻薬も核も、何とか私たちの役に立てられるよう工夫していかなければならない。そのためにも、多くの人たちに麻薬とは何かを正確に知っておいてほしいと願っている。”、と結んでいる。
パンドラの箱のように、開いてはいけないものをヒトの英知という美辞のもとに開いてしまった。便利になること、幸せな気分になることがたやすく手に入るという甘い囁きにみごとに負けてしまったのだ。しかし、このまま幸せな気持ちになったまま滅んでいくことを私たちは選択してはならない。
著者がこの本をまとめたのは昨年のことのようで、もちろん今回の震災による原発の事故は考えることすらしていなかっただろうが、人類と核の危険性についてしっかりと言及している。しかも麻薬の持つ危険性と並べているところに、大変に不思議な感じがするのはなぜだろうか。
"破滅”や"終焉"といったことさらに刺激の強い言葉を、赤く巨大な文字で威嚇するように投げつける夕刊紙群。負けじと週刊誌などの雑誌がこれを追いかけ、いつのまにか新書の帯もこの路線に追随しているものが増えた。その理由はわからないでもないが、それにしても、いかにも売らんかなというのが多い、というかいつのまにか随分と下品になってしまったなあと感じることが多い。でも、きれいごとだけでは生きていけないのも確かだろう。
そんな過激な"売れさえすれば"いいというのと少し趣の異なる本を、古くからの友人である著者より献本頂いた。新書を包んでいる帯の下半分が植物図鑑を思わせる絵柄で、まずそこらの通俗的な麻薬本でないことをしっかりと主張している。よく見ると、表に麻とケシが、裏はタバコとチョウセンアサガオである。(タバコは麻薬じゃないなどと野暮なことは言わない)
この本が書かれた意図はなんだろうか。MDMAと押尾学の話にフォーカスした芸能界などの華やかな人脈に切り込むといった裏話的刺激はまったくない。そうしたことを期待する人は、この本を手にすることすらやめたほうがよい。祟りで目がつぶれるに違いない。
犯罪として麻薬の常用や人体への影響などがときたま取り上げられることはあっても、麻薬そのものの来歴や分類について啓蒙的な視点からまとめたものがほとんどないことが、実は結果として日本での麻薬の蔓延を助長しているという著者の考えに立ってまとめられたものだ。これについて著者は、寺田虎彦の「ものをこわがわらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしい」という言葉を引用して、麻薬の認識もまさにこれだと述べている。なるほど、"正当にこわがる”のは難しいね、確かに。原発に対するここのところの喧々諤々は、まさにこのことだと気がつく。
ちゃんと知っていますか? そう言われてみると、モルヒネ、コカイン、覚せい剤、大麻と並べられても、名前は聞いたことがあるが、なにが違うのか、なぜそんなにいろいろ存在するのかなど、ほとんど知らないということにすぐ気がつく。麻薬というと、悪魔の薬であり、とにかく近づいてはいけない、「禁」というのが第一勘。一方で、それだけ禁じられていても、人をひきつける魔力の秘密の匂いも気になるところだ。
内容は深すぎてとても要約できるような類のものではないが、章立て(1から5章まで)でおおよその流れを知ることはできる。
第1章 ケシと阿片とモルヒネ・ヘロイン
第2章 コカとコカイン
第3章 麦角とLSD
第4章 麻王と覚せい剤
第5章 アサと大麻
いずれも、由来となる植物から、如何にして麻薬が引き出されたかというヒトと麻薬の不思議な出会いの歴史を軸にして論を進めている。マフィアの道具といったステレオタイプなイメージがここで完全に覆ること請け合いである。麻薬と人類の遭遇について著者は次のように述べている。
ケシやコカや大麻のような植物がヒトの脳に何らかの作用をおよぼす化合物を作り出しているということは不思議なことである。なぜ、これらの植物がヒトの脳に作用する化合物を作り出しているのであろうか。この疑問に答えるすべはない。生物の多様性というが、生物はとにかく、生き抜いていく過程においてありとあらゆる方向に進化した。その中でたまたま、ヒトにとって麻薬と称される化学成分をつくり出す植物やきのこなどもあらわれたとしかいわざるを得まい。偶然という他ないのである。
さらに著者は本の最後で、"地球というこの孤独な星に、今日に至るまでの過酷な生存競争に打ち勝って生息してきた私たち人類の今後の存続を決めるのは、環境・食料・資源・疾病などに加え、皮肉なことに人類の英知がもたらした「ヤク(薬)とカク(核)」であると思っている”と述べ、さらに、"皮肉なことに今や人類によってこの世に生み出された麻薬と核の存在によって、自身がその存亡の瀬戸際にたたされているわけである。まさに、ヤクとカクの扱いは人類に未来があるか否かの鍵をにぎっていると言ってもよかろう。人類の知恵によって、麻薬も核も、何とか私たちの役に立てられるよう工夫していかなければならない。そのためにも、多くの人たちに麻薬とは何かを正確に知っておいてほしいと願っている。”、と結んでいる。
パンドラの箱のように、開いてはいけないものをヒトの英知という美辞のもとに開いてしまった。便利になること、幸せな気分になることがたやすく手に入るという甘い囁きにみごとに負けてしまったのだ。しかし、このまま幸せな気持ちになったまま滅んでいくことを私たちは選択してはならない。
著者がこの本をまとめたのは昨年のことのようで、もちろん今回の震災による原発の事故は考えることすらしていなかっただろうが、人類と核の危険性についてしっかりと言及している。しかも麻薬の持つ危険性と並べているところに、大変に不思議な感じがするのはなぜだろうか。
いかにして科学は人の命を救えるか [読後の感想]
7年前の1994年12月26日にインドネシアのスマトラ島沖で発生した地震は、震源の長さ1,000km幅200kmに及び、マグニチュード9.2という巨大なものだった。それに伴う津波はスマトラ島だけでなく、広くインド洋に広がり各地で大きな被害をもたらし、とくに震源に近い街バンダアチェは津波によって根こそぎに破壊された。この地震と津波によって30万近い人命が失われたとされている。人類が経験した最も悲惨な自然災害のひとつといえる。
カリフォルニア工科大学(当時)のケリー・シー(Kerry Sieh)教授は、長くスマトラ島の活断層や巨大地震・津波の歴史や発生機構を研究しており、その研究成果をもとにしてこれから生じるであろう将来の巨大な地震や津波に備えるための啓蒙教育活動を現地で開始したところであった。その活動の成果が災害の軽減につながったかどうかも含め、忸怩たる思いを抱えたままに研究者としての思いをまとめたもの"How Science Can Save Lives"がTIME誌に掲載されている。執筆は災害発生から一週間後、まだ現地の被災の詳細が十分にみえていない状況でまとめられたものであろう。
その中から、要約して紹介したい。
「たしかにアチェの甚大な災害を悲しんではいるが、研究による知見をもとにアチェの住民に対して事前の警告を与えられなかったことは驚きではない。われわれ地球科学者は、自然がその力を災害として人間にもたらすとき、いかに対応すべきかの答えをそこから見い出し社会にひろめていくのが役割である。その歩みは遅いけれど確実にすすんではいるのだ。」
「地震が地殻プレートの動きによって生じるということを知ったのは50年前のことだし、巨大地震が断層に沿って繰り返し起きるということを知ったのもわずか30年前、活動していない断層でも激烈な地震を起こすことがあることがわかったのも最近のことである。地球の動きを知るにも、科学としての発見に至るにも時間が必要だ。地震や津波による災害発生がそのメカニズムとともに体系付けられ、災害を軽減するための研究がようやく動き始めたところなのだ。」
「地球科学者は、『近くで巨大な地質学的変動が起きることを警戒しなさい、ただしそれが起きるのは明日かもしれないし数百年後かもしれない』といったことを人々に納得させることができないでいる。日々の暮らしに追われている人が、しかもそれが途上国であればなおさら、いつ起きるかさえ伝えられない忠告に、たとえどんなにうまく説明されたとしても、素直に耳を傾けるだろうか。」
そしてシー教授(現在はシンガポールの地球観測所に席を置いている)は、最後に次のような重い文章でこの寄稿をしめくくっている。
「あるいは、これまでと同じように、生じた災害に対してその場しのぎの対応を繰り返すのか?
だとすれば、またアチェと同じような悲劇が繰り返されるだろう。」
2011年3月11日、日本で起きた巨大災害は “さらなるアチェ” だったのか。
※本稿は、「2004.12.26 スマトラ-アンダマン諸島地震の特徴と地球科学者の役割」大矢暁、EAJ Information No.123/2005年5月 を参考とした。
カリフォルニア工科大学(当時)のケリー・シー(Kerry Sieh)教授は、長くスマトラ島の活断層や巨大地震・津波の歴史や発生機構を研究しており、その研究成果をもとにしてこれから生じるであろう将来の巨大な地震や津波に備えるための啓蒙教育活動を現地で開始したところであった。その活動の成果が災害の軽減につながったかどうかも含め、忸怩たる思いを抱えたままに研究者としての思いをまとめたもの"How Science Can Save Lives"がTIME誌に掲載されている。執筆は災害発生から一週間後、まだ現地の被災の詳細が十分にみえていない状況でまとめられたものであろう。
その中から、要約して紹介したい。
「たしかにアチェの甚大な災害を悲しんではいるが、研究による知見をもとにアチェの住民に対して事前の警告を与えられなかったことは驚きではない。われわれ地球科学者は、自然がその力を災害として人間にもたらすとき、いかに対応すべきかの答えをそこから見い出し社会にひろめていくのが役割である。その歩みは遅いけれど確実にすすんではいるのだ。」
「地震が地殻プレートの動きによって生じるということを知ったのは50年前のことだし、巨大地震が断層に沿って繰り返し起きるということを知ったのもわずか30年前、活動していない断層でも激烈な地震を起こすことがあることがわかったのも最近のことである。地球の動きを知るにも、科学としての発見に至るにも時間が必要だ。地震や津波による災害発生がそのメカニズムとともに体系付けられ、災害を軽減するための研究がようやく動き始めたところなのだ。」
「地球科学者は、『近くで巨大な地質学的変動が起きることを警戒しなさい、ただしそれが起きるのは明日かもしれないし数百年後かもしれない』といったことを人々に納得させることができないでいる。日々の暮らしに追われている人が、しかもそれが途上国であればなおさら、いつ起きるかさえ伝えられない忠告に、たとえどんなにうまく説明されたとしても、素直に耳を傾けるだろうか。」
そしてシー教授(現在はシンガポールの地球観測所に席を置いている)は、最後に次のような重い文章でこの寄稿をしめくくっている。
「あるいは、これまでと同じように、生じた災害に対してその場しのぎの対応を繰り返すのか?
だとすれば、またアチェと同じような悲劇が繰り返されるだろう。」
2011年3月11日、日本で起きた巨大災害は “さらなるアチェ” だったのか。
※本稿は、「2004.12.26 スマトラ-アンダマン諸島地震の特徴と地球科学者の役割」大矢暁、EAJ Information No.123/2005年5月 を参考とした。
大波、黒煙を立てて押し来る [読後の感想]
津波 -その発生から対策まで-
三好 寿、1977年、海洋出版株式会社、より
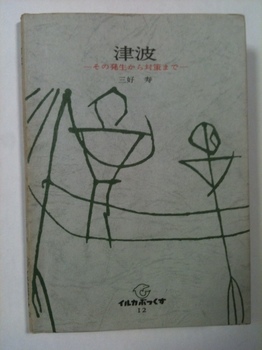
“朝五つ半時ごろ、空俄かに鳴り渡り、雷かと疑い候程に候処、忽ち地震おびただしく、人家破損し、老若残らず家を出て、あい凌ぎ候処、程なく海中沸蕩致し、大船綱ふつと切れ、矢の如く飛び来たり、陸地へ押し上げ、海面一円、水煙霧のごとく立ち昇り、水音百雷の如くと見る内に、烟浪ともに納まり、暫時まを置き、再度には凡そ三間余もこれあるべしと見えたる大波、砲丸の飛ぶが如く、黒煙を立て押し来る。人家・土蔵・石壁の嫌いもなく、ひた押しに転倒致させ、実に百雷の如く鳴り渡り、男女の逃げ惑う声おびただしく、その恐ろしきこと譬えうるに物なしとも申すべしと、今に思い出で候ては、毛穴逆立ち候程のことに御座候、その一波にて、千有余の民家、悉く流失し、漸く五十軒程半壊、あるいは水入りなどにて、目も当てられぬ次第に御座候。”
これは、安政元年(1854年)12月23日に生じた大地震と津波の様子を下田奉行組頭黒川嘉兵衛が手紙に記録したものであり、150年以上前のことだが、突然津波に襲われたときの様子がわかる貴重な情報の一つだと考えられる。この地震は安政東海地震と呼ばれるもので、震源域は伊豆半島の東沖から紀伊半島沖に至る広い範囲であり、地震の規模を示すマグニチュードは8.4であったとされている。なお、この地震の翌日の12月24日には今度は四国沖から紀伊半島にかけて地震が発生しこれも広い範囲で大きな被害を生じている。この地震は安政南海地震と呼ばれている。マグニチュードは8.4であった。
津波の挙動については、その最大の被害国である日本において研究が進み、コンピュータによるシミュレーションが現象の理解や予測に大きな成果を挙げている。また、それらを防災の観点から詳しく最新の情報で解説した書籍も数多いのだが、はるか遠い昔に読んだこの本の存在が気になり、古い書棚を探しようやく見つけ出した。
この本の著者である三好氏は著名な海洋物理学者で、特に津波の分野に多くの研究業績があり、関連した著作も多いが、この本は学生の副読本として読まれることを想定したもののようだ。また日本において、過去繰り返し深刻な被害を生じてきた津波に対する一般の認識が薄く、対策もおざなりになっていることに対する警告の書としての役割も与えている。それでも34年も前に出版されたこの本を書棚の奥からあえて引っ張り出してきたのは、今回の震災の最大の特徴である津波とその被害について、幾つか確かめたいことがあったからである。
一つは、今回の巨大地震によって生じた津波が「想定外」という簡単な言葉ですべて括られてしまっていること。自然科学というのはそんなに無力だったのかという疑問を自分なりに確かめたかったこと。もう一つは、これからの防災を考える上で抜け落ちている視点がなかったかどうかを知りたいと思ったからだ。
三好氏がこの本の中で繰り返し述べているのは、“津波を伴う地震では、被害の主体は津波による”という重い経験則である。しかし、直下型の地震などでは津波を伴わないか,伴っても被害が軽微なケースが多いため、津波の恐ろしさを忘れやすいとも指摘している。その典型的な例は関東大震災であり、横浜と東京を中心として地震後の火災などで10万人を越える人命が奪われたために、実は相模湾岸を襲った津波で数百人の人命を奪っていたことが印象としては刻まれずにいる。この点が関東地方南部の防災上の盲点になっていると警鐘をならしている。
もう一つは、今回のように大地震が大津波を引き起こすというパターンばかりでなく、小地震なのに大津波というパターンもかなりあり、地震が軽微なためにかえって避難が遅れるなど対策が難しいことが多いとも指摘している。その代表例は、1774年の八重山津波であり、地震がマグニチュード7.4と小規模であり震害もほとんどなかったにもかかわらず、津波については史上最激甚といわれる被害を生じた。被害の中心となった石垣島といくつかの島だけで、1万2千人の人命が失われたのだ。この津波の痕跡調査の結果によると、海岸から水平距離で少なくとも3km近く内陸に侵入し、高さも最大で85m駆け上がった(津波の高さとは異なることに注意)とされている。また1896年の三陸大津波でも死者が2万7千人を越え、津波の駆け上がり高も50mであったにもかかわらず、地震そのもののマグニチュードは7.6で地震そのものによる被害は僅少であった。
三好氏は他にも深い洞察と物理学的検証によって津波の歴史から学ぶべき教訓を示しているが、これらの事実を頭に入れていれば、今回の津波が決して「想定外」などというレベルのものではなく、過去に地球上のどこかで繰り返し起きていたものと変わらないということがたやすく理解できる。
災害を想定するときに確率論から出発して、○百年に一回程度の出現を想定して対策工の規模(高さや重さなど)を決定するのはごくあたりまえの工学アプローチなのだが、今回の震災はそうした確率論的な基準の考え方を完膚なきまでに破壊してしまったように思う。生じる災害が人命にとって苛烈過ぎるときには、従来から用いられてきた手法では、実はなんの解決策も提示できていないことが万人の前に曝されてしまったのだ。
ハワイ島にあるヒロ市はホノルルに次ぐ第二の大きな街だが、他の街と異なり沖合いのサンゴ礁に守られていない島の北部に位置しているため、歴史上繰り返し北からの津波の被害を受けていた。湾奥にある“砂地には家を建てるな”という戒めが土着民の古くからの言い伝えであったにもかかわらず、時代の推移と共に新しい人々が低地に降りるようになり、大きな災害を被ったという。近年ではその教訓を生かし、被害を受けた海岸沿いの低地をほぼすべて公園として利用するようにしているようだが、街が海から退くことによる街の衰退を危惧する声も依然として根強いともいう。
今回の津波で大きな被害を受けた東北の街でもこれからヒロ市と同じような議論が始まるのだろうが、その時には津波の挙動の原点に立ち戻ることが他のなにより求められるように思う。その上で新しい街づくりを考えるべきだ。もう二度と「想定外」などと言わないために。
三好 寿、1977年、海洋出版株式会社、より
“朝五つ半時ごろ、空俄かに鳴り渡り、雷かと疑い候程に候処、忽ち地震おびただしく、人家破損し、老若残らず家を出て、あい凌ぎ候処、程なく海中沸蕩致し、大船綱ふつと切れ、矢の如く飛び来たり、陸地へ押し上げ、海面一円、水煙霧のごとく立ち昇り、水音百雷の如くと見る内に、烟浪ともに納まり、暫時まを置き、再度には凡そ三間余もこれあるべしと見えたる大波、砲丸の飛ぶが如く、黒煙を立て押し来る。人家・土蔵・石壁の嫌いもなく、ひた押しに転倒致させ、実に百雷の如く鳴り渡り、男女の逃げ惑う声おびただしく、その恐ろしきこと譬えうるに物なしとも申すべしと、今に思い出で候ては、毛穴逆立ち候程のことに御座候、その一波にて、千有余の民家、悉く流失し、漸く五十軒程半壊、あるいは水入りなどにて、目も当てられぬ次第に御座候。”
これは、安政元年(1854年)12月23日に生じた大地震と津波の様子を下田奉行組頭黒川嘉兵衛が手紙に記録したものであり、150年以上前のことだが、突然津波に襲われたときの様子がわかる貴重な情報の一つだと考えられる。この地震は安政東海地震と呼ばれるもので、震源域は伊豆半島の東沖から紀伊半島沖に至る広い範囲であり、地震の規模を示すマグニチュードは8.4であったとされている。なお、この地震の翌日の12月24日には今度は四国沖から紀伊半島にかけて地震が発生しこれも広い範囲で大きな被害を生じている。この地震は安政南海地震と呼ばれている。マグニチュードは8.4であった。
津波の挙動については、その最大の被害国である日本において研究が進み、コンピュータによるシミュレーションが現象の理解や予測に大きな成果を挙げている。また、それらを防災の観点から詳しく最新の情報で解説した書籍も数多いのだが、はるか遠い昔に読んだこの本の存在が気になり、古い書棚を探しようやく見つけ出した。
この本の著者である三好氏は著名な海洋物理学者で、特に津波の分野に多くの研究業績があり、関連した著作も多いが、この本は学生の副読本として読まれることを想定したもののようだ。また日本において、過去繰り返し深刻な被害を生じてきた津波に対する一般の認識が薄く、対策もおざなりになっていることに対する警告の書としての役割も与えている。それでも34年も前に出版されたこの本を書棚の奥からあえて引っ張り出してきたのは、今回の震災の最大の特徴である津波とその被害について、幾つか確かめたいことがあったからである。
一つは、今回の巨大地震によって生じた津波が「想定外」という簡単な言葉ですべて括られてしまっていること。自然科学というのはそんなに無力だったのかという疑問を自分なりに確かめたかったこと。もう一つは、これからの防災を考える上で抜け落ちている視点がなかったかどうかを知りたいと思ったからだ。
三好氏がこの本の中で繰り返し述べているのは、“津波を伴う地震では、被害の主体は津波による”という重い経験則である。しかし、直下型の地震などでは津波を伴わないか,伴っても被害が軽微なケースが多いため、津波の恐ろしさを忘れやすいとも指摘している。その典型的な例は関東大震災であり、横浜と東京を中心として地震後の火災などで10万人を越える人命が奪われたために、実は相模湾岸を襲った津波で数百人の人命を奪っていたことが印象としては刻まれずにいる。この点が関東地方南部の防災上の盲点になっていると警鐘をならしている。
もう一つは、今回のように大地震が大津波を引き起こすというパターンばかりでなく、小地震なのに大津波というパターンもかなりあり、地震が軽微なためにかえって避難が遅れるなど対策が難しいことが多いとも指摘している。その代表例は、1774年の八重山津波であり、地震がマグニチュード7.4と小規模であり震害もほとんどなかったにもかかわらず、津波については史上最激甚といわれる被害を生じた。被害の中心となった石垣島といくつかの島だけで、1万2千人の人命が失われたのだ。この津波の痕跡調査の結果によると、海岸から水平距離で少なくとも3km近く内陸に侵入し、高さも最大で85m駆け上がった(津波の高さとは異なることに注意)とされている。また1896年の三陸大津波でも死者が2万7千人を越え、津波の駆け上がり高も50mであったにもかかわらず、地震そのもののマグニチュードは7.6で地震そのものによる被害は僅少であった。
三好氏は他にも深い洞察と物理学的検証によって津波の歴史から学ぶべき教訓を示しているが、これらの事実を頭に入れていれば、今回の津波が決して「想定外」などというレベルのものではなく、過去に地球上のどこかで繰り返し起きていたものと変わらないということがたやすく理解できる。
災害を想定するときに確率論から出発して、○百年に一回程度の出現を想定して対策工の規模(高さや重さなど)を決定するのはごくあたりまえの工学アプローチなのだが、今回の震災はそうした確率論的な基準の考え方を完膚なきまでに破壊してしまったように思う。生じる災害が人命にとって苛烈過ぎるときには、従来から用いられてきた手法では、実はなんの解決策も提示できていないことが万人の前に曝されてしまったのだ。
ハワイ島にあるヒロ市はホノルルに次ぐ第二の大きな街だが、他の街と異なり沖合いのサンゴ礁に守られていない島の北部に位置しているため、歴史上繰り返し北からの津波の被害を受けていた。湾奥にある“砂地には家を建てるな”という戒めが土着民の古くからの言い伝えであったにもかかわらず、時代の推移と共に新しい人々が低地に降りるようになり、大きな災害を被ったという。近年ではその教訓を生かし、被害を受けた海岸沿いの低地をほぼすべて公園として利用するようにしているようだが、街が海から退くことによる街の衰退を危惧する声も依然として根強いともいう。
今回の津波で大きな被害を受けた東北の街でもこれからヒロ市と同じような議論が始まるのだろうが、その時には津波の挙動の原点に立ち戻ることが他のなにより求められるように思う。その上で新しい街づくりを考えるべきだ。もう二度と「想定外」などと言わないために。
つながりをキュレーションが紡ぐとき [読後の感想]
「キュレーションの時代」佐々木俊尚著、ちくま新書、を読んで
新聞・TVなどのレガシーな集団・勢力が、ソーシャル化というパラダイムシフトの中で大きく変容しつつある。既存のメディアはあってもっよいが、自分には不要だと断言する人さえいる。同じことしか語らない、異様に均質なメディアに存在価値はないという意見もある。そうした騒然とした雰囲気に振り回されず、落ち着いた視点を維持している佐々木氏の言説には常に注目している。信頼しうる情報発信者は、この混沌とした時代にとってかけがえのない宝である。
さて、氏の新しい著作だが、とにかく魅力的だ。引き込まれる。これからの時代に最も必要なのがキュレーションという機能。簡単にまとめるとそれだけなのに、読み物としてとても面白い。どこがどのようにというのは、読んだ人にしかわからないというのが説明になるような感覚。この本については、すでに多くの人によって評が重ねられているので、内容の詳細に踏み込むことは避けたいと思う。腑に落ちるかどうかはあなたしだいということだ。
キュレーション(Curation) 無数の情報の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること。
キュレーターという役割が最も知られているのはやはり美術館ではないだろうか。展覧会を催すときに企画責任者として関わり、最初に全体の柱となるシナリオを構成する。そのシナリオに沿って作家とその作品を選び、さらに展示方法を考案する。映画でいう総製作者と監督を合わせたような機能かもしれない。作家や作品がそれぞれに持っている経緯や歴史的な意味、時間と空間の関係性をも含めて観客に提示する。キュレーターによって意味づけが明瞭になされることで作品が持つ深い背景が浮かび上がり、得られる感動の質を一層高めることになる。佐々木氏が述べているように、「見慣れた絵が違う姿に見えてくる」のだ。誰かに導かれない限り、決して目から鱗は落ちない。ある明瞭な視座を持った人だけが導きをあたえることができる。
いまがソーシャル・メディアの黎明期といってよいかはわからないが、情報のやりとりのほとんどがトップダウンであった時代は間違いなく終焉したといってよいだろう。ソーシャルなつながりに加わる人が限りなく増え続けているのは、それが便利だからという単純な理由だけでは決してない。情報を持っていることや情報を発信することだけに意味があるのではない。情報が次々につながり、共有され、結果として新たな意味づけを獲得していき、それがさらに次の連鎖を生み出す。これが世界中で同時にしかも爆発的に起こっているように感じている。
佐々木氏の今回の著書は、決して予言の書ではないが、この分野がこれからどの方向に進んでいくかを考察するときには欠かせない一冊だと思う。しかも変わりつつある時代を第三者として眺めるというより、そこでどのような態度を持つのかをはっきりと問いかける。ただ眺めているだけでもよいが、本当にそれだけでよいのかと。
この本が発売後かなりの売れ行きを見せていることに、正直、安堵している。ノウハウ本でもなんでもないこの類の著作が、実はしっかり評価されることは決して悪い兆しではないように思う。
これはと思う若い人に、この本を薦めようと思っている。そしてどう感じたかを聞いてみたい。
新聞・TVなどのレガシーな集団・勢力が、ソーシャル化というパラダイムシフトの中で大きく変容しつつある。既存のメディアはあってもっよいが、自分には不要だと断言する人さえいる。同じことしか語らない、異様に均質なメディアに存在価値はないという意見もある。そうした騒然とした雰囲気に振り回されず、落ち着いた視点を維持している佐々木氏の言説には常に注目している。信頼しうる情報発信者は、この混沌とした時代にとってかけがえのない宝である。
さて、氏の新しい著作だが、とにかく魅力的だ。引き込まれる。これからの時代に最も必要なのがキュレーションという機能。簡単にまとめるとそれだけなのに、読み物としてとても面白い。どこがどのようにというのは、読んだ人にしかわからないというのが説明になるような感覚。この本については、すでに多くの人によって評が重ねられているので、内容の詳細に踏み込むことは避けたいと思う。腑に落ちるかどうかはあなたしだいということだ。
キュレーション(Curation) 無数の情報の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること。
キュレーターという役割が最も知られているのはやはり美術館ではないだろうか。展覧会を催すときに企画責任者として関わり、最初に全体の柱となるシナリオを構成する。そのシナリオに沿って作家とその作品を選び、さらに展示方法を考案する。映画でいう総製作者と監督を合わせたような機能かもしれない。作家や作品がそれぞれに持っている経緯や歴史的な意味、時間と空間の関係性をも含めて観客に提示する。キュレーターによって意味づけが明瞭になされることで作品が持つ深い背景が浮かび上がり、得られる感動の質を一層高めることになる。佐々木氏が述べているように、「見慣れた絵が違う姿に見えてくる」のだ。誰かに導かれない限り、決して目から鱗は落ちない。ある明瞭な視座を持った人だけが導きをあたえることができる。
いまがソーシャル・メディアの黎明期といってよいかはわからないが、情報のやりとりのほとんどがトップダウンであった時代は間違いなく終焉したといってよいだろう。ソーシャルなつながりに加わる人が限りなく増え続けているのは、それが便利だからという単純な理由だけでは決してない。情報を持っていることや情報を発信することだけに意味があるのではない。情報が次々につながり、共有され、結果として新たな意味づけを獲得していき、それがさらに次の連鎖を生み出す。これが世界中で同時にしかも爆発的に起こっているように感じている。
佐々木氏の今回の著書は、決して予言の書ではないが、この分野がこれからどの方向に進んでいくかを考察するときには欠かせない一冊だと思う。しかも変わりつつある時代を第三者として眺めるというより、そこでどのような態度を持つのかをはっきりと問いかける。ただ眺めているだけでもよいが、本当にそれだけでよいのかと。
この本が発売後かなりの売れ行きを見せていることに、正直、安堵している。ノウハウ本でもなんでもないこの類の著作が、実はしっかり評価されることは決して悪い兆しではないように思う。
これはと思う若い人に、この本を薦めようと思っている。そしてどう感じたかを聞いてみたい。
環境ビジネスにありがちな思い込み [読後の感想]
「環境ビジネス5つの誤解」尾崎弘之:日経プレミアシリーズを読んで
低炭素社会の形成というキーワードに牽引されて、環境関連ビジネスに大きくスポットが当たってきている。そうした局面で、でもその考えはほんとに正しいか、思い込みではないのかという指摘を投げかけるのがこの本である。日本の主要自動車メーカーが次々に電気自動車を市場に投入するといった目の前の事象に振り回されずに、何をどう理解すべきなのかを、グリーン・ビジネスの視点から論じている。
東京工科大学教授である著者の尾崎氏は、野村證券からモルガンスタンレー、ゴールドマンサックスなどの金融系企業のマネジメントを経験した後、ベンチャー業界へ進んだ経歴の持ち主で、ウェブサイトを拝見すると、“How Can We Promote a Green Business of Next Generation ?”と明記されているように現在はグリーン・ビジネスにフォーカスしているようだ。
さて、この本で尾崎氏が指摘する「誤解」とは、次の5つである。
第1の誤解 クリーンエネルギーは増やせば増やすほどエコである
第2の誤解 電気自動車は異業種、中小、ベンチャー企業を中心に短期間で成長する
第3の誤解 太陽光発電は「固定価格買い取り制度」(FIT)によって健全に成長した
第4の誤解 バイオ燃料は環境にやさしいエネルギーである
第5の誤解 日本の技術力は世界の水ビジネスをリードしている
「誤解」という刺激的な言葉は、読者を“掴む”ためにあえて使っているのだろう。またその内容は決して挑戦的でも挑発的でもなく、全体に落ち着いたスタイルを貫いており、言い回しも丁寧である。よくある環境問題否定を大声で繰り返す“とんでも本”とは一線を画している。逆に言うとタイトルで少し損をしているかもしれないが。
著者が繰り返して述べていることは、グリーンの分野で失敗しないためには、思い込みで思考停止に陥らないことのようだ。日本の多くの不勉強なメディアの挑発に踊らされず、本質をきちんと聞き分けられる常識を持つべきだと説いている。
この分野の著作は、両極に振れているものが多く、読むべき本を選ぶのがやさしくないのだが、この本はグリーンをビジネスとして取り組もうとしている人には薦められる。ただし、本の構成としては、グリーンというキーワードでつながってはいるものの、必ずしもしっかり体系づけて書かれているわけではないように思うので、全体にこだわらず興味のあるところだけ切り取るように読んでも、十分に活用できるのではないか。
「誤解」の詳細については、ここではあまり触れないが、それぞれの要点を私なりにまとめるとこうなる。
第1誤解:エコと唱えるだけで豊かな未来が来る。わけがないよ、そりゃ。汚いエネルギー(化石燃料)を使うのを早く止めないと大変なことになる。かもしれないけど、もっと大事なことがあることを気づいてほしい。
第2誤解:EVになると、一般的な電気・電子部品組み立ての産業になるので、日本の競争力は急速に低下する。はずがない。なぜなら人命を運ぶ道具が担う責務は果てしなく重いから。それでも競争環境は大きく変化するし、なにより戦略それも国レベルの戦略が鍵。
第3誤解:太陽光発電にFITを導入して、欧州各国は大きな便益を享受した。ことになってはいるが、政策で強引に誘導したのでプラスもマイナスもある。市場を形成できたことは功績、加速が急すぎてバブルになったことは失敗。安易な批判や盲従だけはやめよう。
第4誤解:とうもろこしから生み出されるバイオ燃料が環境問題解決の決め手になる。なんてホラは誰が言ったんだ。森林破壊と穀物転換を加速させ、食料価格高騰まで引き起こした責任があいまいなまま、解決策が見いだされていない。もちろんバイオすべてがだめなのでもない。
第5誤解:膜技術に競争力があるのでこれから国全体で体制を組めば水ビジネスで海外に市場を求められる。かもしれないが、まず施設設置から運営までの経験が国内には決定的に不足。いまのところ官(地方自治体)にしか存在していない運用ノウハウを民間と重ね合わせることで人材やノウハウ提供のサービスの輸出ができるかどうか。
グリーン・ビジネスは、どうしても声の大きな「誰か」が引っ張りがちだ。そうした局面にこそ勢いに流されずに、いや待て本当にそうかと疑問を投げかけ、しっかり考えることのできる構えを作ることが大事だと著者は主張しているように私は受けとめた。
低炭素社会の形成というキーワードに牽引されて、環境関連ビジネスに大きくスポットが当たってきている。そうした局面で、でもその考えはほんとに正しいか、思い込みではないのかという指摘を投げかけるのがこの本である。日本の主要自動車メーカーが次々に電気自動車を市場に投入するといった目の前の事象に振り回されずに、何をどう理解すべきなのかを、グリーン・ビジネスの視点から論じている。
東京工科大学教授である著者の尾崎氏は、野村證券からモルガンスタンレー、ゴールドマンサックスなどの金融系企業のマネジメントを経験した後、ベンチャー業界へ進んだ経歴の持ち主で、ウェブサイトを拝見すると、“How Can We Promote a Green Business of Next Generation ?”と明記されているように現在はグリーン・ビジネスにフォーカスしているようだ。
さて、この本で尾崎氏が指摘する「誤解」とは、次の5つである。
第1の誤解 クリーンエネルギーは増やせば増やすほどエコである
第2の誤解 電気自動車は異業種、中小、ベンチャー企業を中心に短期間で成長する
第3の誤解 太陽光発電は「固定価格買い取り制度」(FIT)によって健全に成長した
第4の誤解 バイオ燃料は環境にやさしいエネルギーである
第5の誤解 日本の技術力は世界の水ビジネスをリードしている
「誤解」という刺激的な言葉は、読者を“掴む”ためにあえて使っているのだろう。またその内容は決して挑戦的でも挑発的でもなく、全体に落ち着いたスタイルを貫いており、言い回しも丁寧である。よくある環境問題否定を大声で繰り返す“とんでも本”とは一線を画している。逆に言うとタイトルで少し損をしているかもしれないが。
著者が繰り返して述べていることは、グリーンの分野で失敗しないためには、思い込みで思考停止に陥らないことのようだ。日本の多くの不勉強なメディアの挑発に踊らされず、本質をきちんと聞き分けられる常識を持つべきだと説いている。
この分野の著作は、両極に振れているものが多く、読むべき本を選ぶのがやさしくないのだが、この本はグリーンをビジネスとして取り組もうとしている人には薦められる。ただし、本の構成としては、グリーンというキーワードでつながってはいるものの、必ずしもしっかり体系づけて書かれているわけではないように思うので、全体にこだわらず興味のあるところだけ切り取るように読んでも、十分に活用できるのではないか。
「誤解」の詳細については、ここではあまり触れないが、それぞれの要点を私なりにまとめるとこうなる。
第1誤解:エコと唱えるだけで豊かな未来が来る。わけがないよ、そりゃ。汚いエネルギー(化石燃料)を使うのを早く止めないと大変なことになる。かもしれないけど、もっと大事なことがあることを気づいてほしい。
第2誤解:EVになると、一般的な電気・電子部品組み立ての産業になるので、日本の競争力は急速に低下する。はずがない。なぜなら人命を運ぶ道具が担う責務は果てしなく重いから。それでも競争環境は大きく変化するし、なにより戦略それも国レベルの戦略が鍵。
第3誤解:太陽光発電にFITを導入して、欧州各国は大きな便益を享受した。ことになってはいるが、政策で強引に誘導したのでプラスもマイナスもある。市場を形成できたことは功績、加速が急すぎてバブルになったことは失敗。安易な批判や盲従だけはやめよう。
第4誤解:とうもろこしから生み出されるバイオ燃料が環境問題解決の決め手になる。なんてホラは誰が言ったんだ。森林破壊と穀物転換を加速させ、食料価格高騰まで引き起こした責任があいまいなまま、解決策が見いだされていない。もちろんバイオすべてがだめなのでもない。
第5誤解:膜技術に競争力があるのでこれから国全体で体制を組めば水ビジネスで海外に市場を求められる。かもしれないが、まず施設設置から運営までの経験が国内には決定的に不足。いまのところ官(地方自治体)にしか存在していない運用ノウハウを民間と重ね合わせることで人材やノウハウ提供のサービスの輸出ができるかどうか。
グリーン・ビジネスは、どうしても声の大きな「誰か」が引っ張りがちだ。そうした局面にこそ勢いに流されずに、いや待て本当にそうかと疑問を投げかけ、しっかり考えることのできる構えを作ることが大事だと著者は主張しているように私は受けとめた。
データセンターは発電所だった (2) [読後の感想]
「クラウド化する世界」:ニコラス・G・カー:翔泳社を読んで
原著 "The Big Switch" by Nicholas G. Carr
著者は、「電力とコンピューティングには重要な類似点がある」と強調している。もちろん技術的にも事業モデルとしてもさまざまな違いがあることを認めながらも、その類似点を見落としがちだと指摘している。現在では電気があまりにたやすく壁のコンセントから使えるために“単純な”ユーティリティとみなされているが、最初からそうだったわけではない。電力の供給が始まったときには、それは制御しにくい予測不可能な力であり、すべてを変える力だった。電力を使うことそのものが高等な技術であり、今日のコンピュータシステムと同様に、企業は電力をどのようにどこへ使うかを徹底的に考えることが求められ、そのために組織や製造工程をすべて変更することもしばしばだった。電化するということは、個々の企業や産業全体にとって、広範で複雑な、途方にくれるような変化をもたらした。
経済レベルで比較すると、電力とコンピュータの類似はより鮮明だという。いずれも経済学で言う「汎用技術」なのだ。つまりあらゆる人々によってあらゆる目的に使用され、多くの機能を果たしている。鉄道の線路は列車を往復させてモノや人を運ぶことしかできないが、電力網を整備すれば、ありとあらゆることがその先で実現できる。水車も汎用技術なのだが、電力やコンピュータと決定的に異なるところがある。それは、場所にしばられること。つまり、規模のメリットを求めてどれだけ集中化しても遠方に送ることができない。ところが、電力とコンピューティングはいずれもネットワークを経由して遠方から供給することができる。場所に制限されないので、集中を高めて規模のメリットを最大に享受できる。
さらに著者は、現代の社会は電化が起きなければ出現しなかっただろうと述べ、中流階級の増加、学校教育の普及、大衆文化の隆盛、郊外への人口の移動、産業経済からサービス経済への移行... 発電所から供給される安価な電流がなければ、これら特徴のどれ一つとして生じなかった。これらの事象は、社会の永続的な特徴だと思いがちだが、幻想にすぎないとも言う。それらは時代のテクノロジーを反映した経済的取引の副産物であり、一時的な構造にすぎない。あのニューヨークの巨大な水車のように簡単に捨て去られてしまうのだとも。
ここまで著者の主張をならべてくると、この本があまたあるIT本とは大きくそのスタンスを異にしていることが明白である。電力とコンピューティングを並べることで、近代の産業がたどった激しい転換の歴史を認識し、そこから読み取れる人類の未来を冷徹に示していることがわかる。しかも、その未来は決して楽観主義に覆われた明るく単調な(著者に言わせれば電球の照明のような)ものではない。
著者はこの本の最後の部分を次のように締めくくっている。
「旧世代が世を去るにつれて、新技術が登場したときに失われた事物の記憶も失われ、獲得されたものの記憶だけが残るのだ。このようにして、進歩はその痕跡を覆い隠し、絶え間なく新たな幻想を生み出す... 我々がここにいるのは、我々の運命なのだという幻想を。」
原著 "The Big Switch" by Nicholas G. Carr
著者は、「電力とコンピューティングには重要な類似点がある」と強調している。もちろん技術的にも事業モデルとしてもさまざまな違いがあることを認めながらも、その類似点を見落としがちだと指摘している。現在では電気があまりにたやすく壁のコンセントから使えるために“単純な”ユーティリティとみなされているが、最初からそうだったわけではない。電力の供給が始まったときには、それは制御しにくい予測不可能な力であり、すべてを変える力だった。電力を使うことそのものが高等な技術であり、今日のコンピュータシステムと同様に、企業は電力をどのようにどこへ使うかを徹底的に考えることが求められ、そのために組織や製造工程をすべて変更することもしばしばだった。電化するということは、個々の企業や産業全体にとって、広範で複雑な、途方にくれるような変化をもたらした。
経済レベルで比較すると、電力とコンピュータの類似はより鮮明だという。いずれも経済学で言う「汎用技術」なのだ。つまりあらゆる人々によってあらゆる目的に使用され、多くの機能を果たしている。鉄道の線路は列車を往復させてモノや人を運ぶことしかできないが、電力網を整備すれば、ありとあらゆることがその先で実現できる。水車も汎用技術なのだが、電力やコンピュータと決定的に異なるところがある。それは、場所にしばられること。つまり、規模のメリットを求めてどれだけ集中化しても遠方に送ることができない。ところが、電力とコンピューティングはいずれもネットワークを経由して遠方から供給することができる。場所に制限されないので、集中を高めて規模のメリットを最大に享受できる。
さらに著者は、現代の社会は電化が起きなければ出現しなかっただろうと述べ、中流階級の増加、学校教育の普及、大衆文化の隆盛、郊外への人口の移動、産業経済からサービス経済への移行... 発電所から供給される安価な電流がなければ、これら特徴のどれ一つとして生じなかった。これらの事象は、社会の永続的な特徴だと思いがちだが、幻想にすぎないとも言う。それらは時代のテクノロジーを反映した経済的取引の副産物であり、一時的な構造にすぎない。あのニューヨークの巨大な水車のように簡単に捨て去られてしまうのだとも。
ここまで著者の主張をならべてくると、この本があまたあるIT本とは大きくそのスタンスを異にしていることが明白である。電力とコンピューティングを並べることで、近代の産業がたどった激しい転換の歴史を認識し、そこから読み取れる人類の未来を冷徹に示していることがわかる。しかも、その未来は決して楽観主義に覆われた明るく単調な(著者に言わせれば電球の照明のような)ものではない。
著者はこの本の最後の部分を次のように締めくくっている。
「旧世代が世を去るにつれて、新技術が登場したときに失われた事物の記憶も失われ、獲得されたものの記憶だけが残るのだ。このようにして、進歩はその痕跡を覆い隠し、絶え間なく新たな幻想を生み出す... 我々がここにいるのは、我々の運命なのだという幻想を。」
データセンターは発電所だった (1) [読後の感想]
「クラウド化する世界」:ニコラス・G・カー:翔泳社を読んで
原著 "The Big Switch" by Nicholas G. Carr
ある新年会で古くからの友人であるM君から、エネルギーと言えば“あれ”読んでますよねっ?と話題をふられた。ほら、カーの「クラウド化する世界」。発電事業の変遷と現在のクラウド化が同じ流れに沿っているという見方。え?ああ...すいません、まだ読んでません。ということで早速ゲット。これは久々に引き込まれた。幾つかの要点をまとめておく価値があると思えたので、時間をいつもよりかけて読み込んだ。
もう2年以上前の出版、しかも日本語訳にそれなりの時間を要しているはずなので、3年あるいは4年くらい前の状況で書かれた内容である。その証拠にFacebookやTwitterが出てこない。なので、普通に考えれば、そんなこともう知ってるよ本、かもしれない。要するにまたグーグルの話しでしょと決め付けたい。ところが、そうした時間差を全く感じさせないし安易な先入観はふっとんだ。というより、そもそもの視座がしっかりしているので、述べている内容に普遍性がある。単調な楽観論に依存しておらず、なにより揺るがない筆力がある。
プロローグは、不機嫌にしかも静かに始まる。フェンウェイパーク近くの古臭いビルの奥に案内され、そこで見せられた薄暗い倉庫に設置された巨大なサーバー群と停電用のディーゼル発電機と予備電源として積み上げられたバッテリー。空調のファンの音以外は聞こえない、この異空間こそが新しいタイプの「発電所」のプロトタイプであり、これこそ真のユーティリティであり、未来だと著者は断定する。
そして続く第一章で時間は1852年に飛ぶ。そこで現れるのは高さ20m、重さ250トンの巨大な工業用水車。ニューヨーク北部の鉄工所が、競合する他社に対する決定的な優位性を得るために必要な機械動力を得るために設けたものだ。そしてさらにその50年後。同じ場所でその巨大水車は、雑草に覆われ錆びつき放置されている。何が起こったのか。遠く離れた発電所が電力を生み出し、それが電線網を通して工場に送られ、その電流で機械を動かすことができるようになったのだ。
電気を動力に変える技術が生まれたときには、まず工場の中あるいはその近くに発電機を置き、工場とを一本の電線でつなげばよかった。食事を作るためにすべての家に七輪があるようなものだ。しかし電力の需要が増大していくなかで、効率を上げるために発電機を共用したり集約したりすることが生じ、それが送電線のネットワークを形成し共通に利用するというアイデアにつながっていく。ここで巨大な発電所が登場し、個人規模の工場では追いつかない「規模の経済」が確立される。
いったんこの仕組みができてしまうと、製造業で自前の電源を持つことが逆に弱みに転じ、競争に勝てるより安価なエネルギーを手に入れるため、配電網に工場をつながざるをえなくなっていく。発電所という形態の成功は、発電所自体の発展にもつながり、さらに「規模の経済」を実現して電気の価格を急速に引き下げることになり、短い期間で国中の事業所と家庭が電気利用という新しい道具を使えることになった。
電灯は生活の仕方もリズムも根本から変え、安い電力を自由に操ることのできる仕事場は、仕事のやりかたも意味も完全に変質させた。これが19世紀の終わりころに生じた一つの革命である。そこからわずか百年と少ししか経過していない。
(2)に続く
原著 "The Big Switch" by Nicholas G. Carr
ある新年会で古くからの友人であるM君から、エネルギーと言えば“あれ”読んでますよねっ?と話題をふられた。ほら、カーの「クラウド化する世界」。発電事業の変遷と現在のクラウド化が同じ流れに沿っているという見方。え?ああ...すいません、まだ読んでません。ということで早速ゲット。これは久々に引き込まれた。幾つかの要点をまとめておく価値があると思えたので、時間をいつもよりかけて読み込んだ。
もう2年以上前の出版、しかも日本語訳にそれなりの時間を要しているはずなので、3年あるいは4年くらい前の状況で書かれた内容である。その証拠にFacebookやTwitterが出てこない。なので、普通に考えれば、そんなこともう知ってるよ本、かもしれない。要するにまたグーグルの話しでしょと決め付けたい。ところが、そうした時間差を全く感じさせないし安易な先入観はふっとんだ。というより、そもそもの視座がしっかりしているので、述べている内容に普遍性がある。単調な楽観論に依存しておらず、なにより揺るがない筆力がある。
プロローグは、不機嫌にしかも静かに始まる。フェンウェイパーク近くの古臭いビルの奥に案内され、そこで見せられた薄暗い倉庫に設置された巨大なサーバー群と停電用のディーゼル発電機と予備電源として積み上げられたバッテリー。空調のファンの音以外は聞こえない、この異空間こそが新しいタイプの「発電所」のプロトタイプであり、これこそ真のユーティリティであり、未来だと著者は断定する。
そして続く第一章で時間は1852年に飛ぶ。そこで現れるのは高さ20m、重さ250トンの巨大な工業用水車。ニューヨーク北部の鉄工所が、競合する他社に対する決定的な優位性を得るために必要な機械動力を得るために設けたものだ。そしてさらにその50年後。同じ場所でその巨大水車は、雑草に覆われ錆びつき放置されている。何が起こったのか。遠く離れた発電所が電力を生み出し、それが電線網を通して工場に送られ、その電流で機械を動かすことができるようになったのだ。
電気を動力に変える技術が生まれたときには、まず工場の中あるいはその近くに発電機を置き、工場とを一本の電線でつなげばよかった。食事を作るためにすべての家に七輪があるようなものだ。しかし電力の需要が増大していくなかで、効率を上げるために発電機を共用したり集約したりすることが生じ、それが送電線のネットワークを形成し共通に利用するというアイデアにつながっていく。ここで巨大な発電所が登場し、個人規模の工場では追いつかない「規模の経済」が確立される。
いったんこの仕組みができてしまうと、製造業で自前の電源を持つことが逆に弱みに転じ、競争に勝てるより安価なエネルギーを手に入れるため、配電網に工場をつながざるをえなくなっていく。発電所という形態の成功は、発電所自体の発展にもつながり、さらに「規模の経済」を実現して電気の価格を急速に引き下げることになり、短い期間で国中の事業所と家庭が電気利用という新しい道具を使えることになった。
電灯は生活の仕方もリズムも根本から変え、安い電力を自由に操ることのできる仕事場は、仕事のやりかたも意味も完全に変質させた。これが19世紀の終わりころに生じた一つの革命である。そこからわずか百年と少ししか経過していない。
(2)に続く
地球は寒くなっていく? [読後の感想]
「眠りにつく太陽」桜井邦朋、2010、詳伝社新書を読んで
週間朝日12月3日号の書評「新書の小径」で、谷本束氏が「眠りにつく太陽」を、“地球は寒くなっている”というサブタイトルをつけ、「本書を読んで驚いた。温暖化どころかこれから地球はどんどん寒くなるという。本当か。」と桜井氏の結論を、気候変動に対する“他の仮説”だが非常に説得力があると紹介している。ということで、早速読んでみた。が、残念ながら谷本氏とはかなり違った印象を持った。
太陽活動についての基礎をとりあえずあげておくと...(昔取ったなんとやら)
1.太陽は、ほぼ11年の周期でその表面に発生する黒点が増減することが知られている。
2.太陽活動の活発な時期に黒点が多く生じ、活動が穏やかな時期には黒点の発生は少ない。
3.1645年から1715年にかけての70年間は、黒点が著しく減少したことが知られている。
4.この期間はマウンダー極小期と呼ばれるが、ヨーロッパや北米などの温暖地域において気温が低下していた時期と重なっていたため、太陽活動の低下と寒冷化現象との結びつきを指摘されている。
5.黒点の発生は2007年に活動の極小に至り、再び次のサイクルに向かって活発化すると目されていたが、これが数年遅れただけでなく、活動はその後徐々に活発化しているものの、これまでになく静穏な状況が続いている。
太陽活動がおかしくなったのか?ということから、すわこれが寒冷な時代の始まりか!という展開になっているということを前提として以下の感想をまとめたい。(これは学術ブログではなく、読後感想ブログですよ)
桜井氏は、太陽活動が地球の気象に及ぼす影響についての研究から、太陽活動が穏やかになると地球が寒冷化する可能性があると指摘し、現状の太陽活動はまさに「眠りにつく」寸前であり、この状態が長く続けば再び小氷期が到来するだろうと述べている。この仮説に至る論理の組み立ては省略する(というかできません)が、この説が「不機嫌な太陽:気候変動のもうひとつのシナリオ」スベンスマルク、コールダー著(2007年)、桜井邦朋監訳:2010年恒星社厚生閣にかなり影響されているのは間違いないように思う。(こちらは立ち読み程度にしか読んでないのでえらそうなことは言えないが)
この説のポイントは、太陽活動が弱まると地球に降り注ぐ宇宙線が大幅に増加し、そのため大気圏の空気のイオン化が進み雲凝結を促進し、これが太陽光を反射するため大気を冷やすというところである。太陽活動の低下によって太陽光そのものが低下する影響は少ないとしており、寒冷化の原因を飛来する宇宙線の増加に求めているところが特徴だ。
なるほどそんな考え方もあるかなとは思うが、地球の大気現象はそんなに単純だろうか。地球の現象を複雑にしている大きなポイントは、地球が水惑星であることだ。最も比熱の大きい水が地球表面の大半を占めていることで熱的に大きな緩衝効果を持つことと、二酸化炭素などの可溶性ガスを吸収できる巨大な液体の貯蔵庫であることが外部からの影響がどのように伝わるかを考慮するときに重要なはずだし、その機構は複雑で全容の解明にはほど遠い。
さらに桜井氏は、二酸化炭素の増加と地球の温度変化の関連は観測からほとんど認められないし、大気の微量成分にすぎないことからも重要でないとしているのだが、このあたりは繰り返し読んでもみてもなかなか納得できない。(素人にはわからないと一喝されそうだが)
もちろん、桜井氏の仮説を間違っているといっているのではないし、かなり長期的にみれば太陽の活動が地球に影響を及ぼしていることは間違いのない事実だと思う。特に、17世紀ころに生じた寒冷な気候の時代は太陽活動の停滞と結びついていたと考えるのが正しいように思う。しかしそのことと、人間が産業革命以降に、爆発的に化石燃料を燃やし続けてきたことの影響を軽んじることは、まったく別のことであろう。
谷本氏は新書の小径のなかで、「温暖化への疑念を口にするとひどいヤツだみたいな空気まである」と述べているが、それはこちらの台詞だ。「眠りにつく」とか「不機嫌な」とかの扇情的なタイトルをくくりつけて、あまたある仮説の一つをことさらに大きく取り上げてしまう出版サイドに問題はないのか。取り上げた桜井氏の著書の記述は、この分野の専門家としてかなり控えめであり、決してセンセーショナルではないのだが、「本当か」と飛びついた読者にはそのあたりの配慮はほとんど目に入らないのではないか。
太陽の様子がいつものようではないというのは、どうやら本当のようだ。かといって、目の前に人類の滅亡がきているということでもなさそうなので、そうした現象が生じたとしてもそれに対応する知恵をこれからひねり出すのがわれら人間の役目だろう。文明化と共に加速される人間活動によって生じる危険を察知し、策を講じていくしかない化石燃料の問題もこれと変わらない。
週間朝日12月3日号の書評「新書の小径」で、谷本束氏が「眠りにつく太陽」を、“地球は寒くなっている”というサブタイトルをつけ、「本書を読んで驚いた。温暖化どころかこれから地球はどんどん寒くなるという。本当か。」と桜井氏の結論を、気候変動に対する“他の仮説”だが非常に説得力があると紹介している。ということで、早速読んでみた。が、残念ながら谷本氏とはかなり違った印象を持った。
太陽活動についての基礎をとりあえずあげておくと...(昔取ったなんとやら)
1.太陽は、ほぼ11年の周期でその表面に発生する黒点が増減することが知られている。
2.太陽活動の活発な時期に黒点が多く生じ、活動が穏やかな時期には黒点の発生は少ない。
3.1645年から1715年にかけての70年間は、黒点が著しく減少したことが知られている。
4.この期間はマウンダー極小期と呼ばれるが、ヨーロッパや北米などの温暖地域において気温が低下していた時期と重なっていたため、太陽活動の低下と寒冷化現象との結びつきを指摘されている。
5.黒点の発生は2007年に活動の極小に至り、再び次のサイクルに向かって活発化すると目されていたが、これが数年遅れただけでなく、活動はその後徐々に活発化しているものの、これまでになく静穏な状況が続いている。
太陽活動がおかしくなったのか?ということから、すわこれが寒冷な時代の始まりか!という展開になっているということを前提として以下の感想をまとめたい。(これは学術ブログではなく、読後感想ブログですよ)
桜井氏は、太陽活動が地球の気象に及ぼす影響についての研究から、太陽活動が穏やかになると地球が寒冷化する可能性があると指摘し、現状の太陽活動はまさに「眠りにつく」寸前であり、この状態が長く続けば再び小氷期が到来するだろうと述べている。この仮説に至る論理の組み立ては省略する(というかできません)が、この説が「不機嫌な太陽:気候変動のもうひとつのシナリオ」スベンスマルク、コールダー著(2007年)、桜井邦朋監訳:2010年恒星社厚生閣にかなり影響されているのは間違いないように思う。(こちらは立ち読み程度にしか読んでないのでえらそうなことは言えないが)
この説のポイントは、太陽活動が弱まると地球に降り注ぐ宇宙線が大幅に増加し、そのため大気圏の空気のイオン化が進み雲凝結を促進し、これが太陽光を反射するため大気を冷やすというところである。太陽活動の低下によって太陽光そのものが低下する影響は少ないとしており、寒冷化の原因を飛来する宇宙線の増加に求めているところが特徴だ。
なるほどそんな考え方もあるかなとは思うが、地球の大気現象はそんなに単純だろうか。地球の現象を複雑にしている大きなポイントは、地球が水惑星であることだ。最も比熱の大きい水が地球表面の大半を占めていることで熱的に大きな緩衝効果を持つことと、二酸化炭素などの可溶性ガスを吸収できる巨大な液体の貯蔵庫であることが外部からの影響がどのように伝わるかを考慮するときに重要なはずだし、その機構は複雑で全容の解明にはほど遠い。
さらに桜井氏は、二酸化炭素の増加と地球の温度変化の関連は観測からほとんど認められないし、大気の微量成分にすぎないことからも重要でないとしているのだが、このあたりは繰り返し読んでもみてもなかなか納得できない。(素人にはわからないと一喝されそうだが)
もちろん、桜井氏の仮説を間違っているといっているのではないし、かなり長期的にみれば太陽の活動が地球に影響を及ぼしていることは間違いのない事実だと思う。特に、17世紀ころに生じた寒冷な気候の時代は太陽活動の停滞と結びついていたと考えるのが正しいように思う。しかしそのことと、人間が産業革命以降に、爆発的に化石燃料を燃やし続けてきたことの影響を軽んじることは、まったく別のことであろう。
谷本氏は新書の小径のなかで、「温暖化への疑念を口にするとひどいヤツだみたいな空気まである」と述べているが、それはこちらの台詞だ。「眠りにつく」とか「不機嫌な」とかの扇情的なタイトルをくくりつけて、あまたある仮説の一つをことさらに大きく取り上げてしまう出版サイドに問題はないのか。取り上げた桜井氏の著書の記述は、この分野の専門家としてかなり控えめであり、決してセンセーショナルではないのだが、「本当か」と飛びついた読者にはそのあたりの配慮はほとんど目に入らないのではないか。
太陽の様子がいつものようではないというのは、どうやら本当のようだ。かといって、目の前に人類の滅亡がきているということでもなさそうなので、そうした現象が生じたとしてもそれに対応する知恵をこれからひねり出すのがわれら人間の役目だろう。文明化と共に加速される人間活動によって生じる危険を察知し、策を講じていくしかない化石燃料の問題もこれと変わらない。



