隊列から離れるという挑戦 [講演を聞いて]
第一回日経スマートシティシンポジウム、2012年7月23,24日於東工大蔵前会館を聴いて
パネルディスカッション「環境未来都市、スマートコミュニティの実現に向けた北九州市の挑戦」より
北九州市は環境未来都市に選ばれ、エネルギーの新しい形を自治体として模索し続けている。最近では、実証実験として、電力料金にダイナミックプライシングを導入するなどきわめて先駆的な挑戦をしており(例えば、北九州スマートコミュニティ創造事業など)、この領域ではまちがいなくわが国の先進的役割を果たし続けてきている。今回のシンポジウムでは、特にこの北九州市の挑戦的な活動にスポットをあて、さらに今後の課題を見い出そうというとのが議論のねらいであった。
その議論や事例の内容についてはメディアの記事に譲りたい(例えば日経BPクリーンテックの記事など)。ここではパネルの最初に行われた話題提供で北九州市の松岡俊和氏:環境未来都市担当理事の話が印象に強く残ったので、ここに紹介しておきたい。ただし、録音をとらず会場での簡単なメモと記憶によっているため、言葉の使い方などについては実際と異なっていることがあることはご容赦いただきたい。
北九州は、産業都市としての急速な発展とその負の遺産としての公害を両手に抱え、戦後の経済成長路線の先頭を走り続けてきた。いつしか公害と戦いこれを制することが、この街に暮らす人にとって最も大事なことがらとなっていった。全国的にもまだ事例が少ない中で、自らの身を切り、血を流して取り組んできた。公害という当時の課題を克服したことは街に暮らす人の大きな自信でもあった。そうした街が環境・エネルギーへの新しい取り組みに再び立ち上がることになった。
2008年に国の環境モデル都市に選定されたことが節目となった。21世紀の抱える環境とエネルギーの課題は限りある資源と成長のバランスをどうとっていくかということに尽きる。そうした基本となる理念はよく理解できるのだが、さて、モデルの街に選ばれてみて愕然としたという。アイデアがなにも沸いてこない。国から示された美しいメニューは目には入るのだが、さて北九州でなにをやればよいのか、さっぱり浮かんでこない。
戦後の産業成長と公害を乗り越えてきた経験の深い街なのだから、なにもないはずはないのだが。新しい時代の環境と言われたとたんにやるべきことが思いつかないとは。これは正直、かなりショックだったという。要するに、自分たちの街を遠い将来まで含めて、どんな街にしていくのかという一番大切な命題について、実は真剣に考えてはいなかったのではないか。
新しい課題はこれだよと、お上が示してくれたものを眺めてから思考を逆に回転させることがあたりまえになっていた。これを一言で(自分たちは)「自立していなかった」と松岡氏は厳しく断じている。自らの頭で徹底的に考え抜く、与えられたメニューからお気に入りの素材と料理を選んで事たれりとするような甘えた、ぬるい環境に安穏としていただけではないか、と。
このとき初めて、自分たちの自治体運営が「自治」ではなかったと気づいたと。自分たちの街の将来への設計図を描くことこそが自治そのものであり、行政の仕事なのだと気づいた。その土地の文化や歴史に合った街の姿を描くことは、その土地に根ざした行政官にしかできないのだということを。そして同時に、これができていない自治体が多いということも明らかになったという。
この松岡氏の指摘は、行政の中で挑戦を続けている人の発言だけにきわめて重いものがある。街や大きく考えれば国がどの方向に向かうのかという、市民国民にとってもっとも重要なテーマについて、私たちはいったいどれだけ真剣に向き合い、そして考えてきただろうか。あるいはものごとの本質を突き詰めて考えるといった習慣、くせを、親や先達からしっかり引き継いできただろうか。誰かが描いてくれた美しい絵と言葉に共感し、納得した瞬間に思考を止める。議論はもうこれでおしまいにしよう、考えている暇があったら動け、と。
大事なことは夢そのものではなく、それをどうやって実現するかだ。だから、まず手を動かせ、歩き回れ、汗をかいてはじめて前に進むことができる。こうやってわれわれ日本人はずっと突き進んできたのではないだろうか。明治維新、日露戦争、太平洋戦争、そして3.11。これ以上思考を止めたまま歩き続けてはいけない。
考え続けることによって、問題の本質が解きほぐされ、場合によっては方針の修正や路線の変更さえもあってもおかしくはないはずだが、そういうアプローチは良くない、隊列を乱すなと厳しく叩き込まれてきたように思う、よく考えれば子供のころからそうだった。おい、そこのおまえだ、うろうろせず隊列から離れるな、足並みを揃えろと。
パネルディスカッション「環境未来都市、スマートコミュニティの実現に向けた北九州市の挑戦」より
北九州市は環境未来都市に選ばれ、エネルギーの新しい形を自治体として模索し続けている。最近では、実証実験として、電力料金にダイナミックプライシングを導入するなどきわめて先駆的な挑戦をしており(例えば、北九州スマートコミュニティ創造事業など)、この領域ではまちがいなくわが国の先進的役割を果たし続けてきている。今回のシンポジウムでは、特にこの北九州市の挑戦的な活動にスポットをあて、さらに今後の課題を見い出そうというとのが議論のねらいであった。
その議論や事例の内容についてはメディアの記事に譲りたい(例えば日経BPクリーンテックの記事など)。ここではパネルの最初に行われた話題提供で北九州市の松岡俊和氏:環境未来都市担当理事の話が印象に強く残ったので、ここに紹介しておきたい。ただし、録音をとらず会場での簡単なメモと記憶によっているため、言葉の使い方などについては実際と異なっていることがあることはご容赦いただきたい。
北九州は、産業都市としての急速な発展とその負の遺産としての公害を両手に抱え、戦後の経済成長路線の先頭を走り続けてきた。いつしか公害と戦いこれを制することが、この街に暮らす人にとって最も大事なことがらとなっていった。全国的にもまだ事例が少ない中で、自らの身を切り、血を流して取り組んできた。公害という当時の課題を克服したことは街に暮らす人の大きな自信でもあった。そうした街が環境・エネルギーへの新しい取り組みに再び立ち上がることになった。
2008年に国の環境モデル都市に選定されたことが節目となった。21世紀の抱える環境とエネルギーの課題は限りある資源と成長のバランスをどうとっていくかということに尽きる。そうした基本となる理念はよく理解できるのだが、さて、モデルの街に選ばれてみて愕然としたという。アイデアがなにも沸いてこない。国から示された美しいメニューは目には入るのだが、さて北九州でなにをやればよいのか、さっぱり浮かんでこない。
戦後の産業成長と公害を乗り越えてきた経験の深い街なのだから、なにもないはずはないのだが。新しい時代の環境と言われたとたんにやるべきことが思いつかないとは。これは正直、かなりショックだったという。要するに、自分たちの街を遠い将来まで含めて、どんな街にしていくのかという一番大切な命題について、実は真剣に考えてはいなかったのではないか。
新しい課題はこれだよと、お上が示してくれたものを眺めてから思考を逆に回転させることがあたりまえになっていた。これを一言で(自分たちは)「自立していなかった」と松岡氏は厳しく断じている。自らの頭で徹底的に考え抜く、与えられたメニューからお気に入りの素材と料理を選んで事たれりとするような甘えた、ぬるい環境に安穏としていただけではないか、と。
このとき初めて、自分たちの自治体運営が「自治」ではなかったと気づいたと。自分たちの街の将来への設計図を描くことこそが自治そのものであり、行政の仕事なのだと気づいた。その土地の文化や歴史に合った街の姿を描くことは、その土地に根ざした行政官にしかできないのだということを。そして同時に、これができていない自治体が多いということも明らかになったという。
この松岡氏の指摘は、行政の中で挑戦を続けている人の発言だけにきわめて重いものがある。街や大きく考えれば国がどの方向に向かうのかという、市民国民にとってもっとも重要なテーマについて、私たちはいったいどれだけ真剣に向き合い、そして考えてきただろうか。あるいはものごとの本質を突き詰めて考えるといった習慣、くせを、親や先達からしっかり引き継いできただろうか。誰かが描いてくれた美しい絵と言葉に共感し、納得した瞬間に思考を止める。議論はもうこれでおしまいにしよう、考えている暇があったら動け、と。
大事なことは夢そのものではなく、それをどうやって実現するかだ。だから、まず手を動かせ、歩き回れ、汗をかいてはじめて前に進むことができる。こうやってわれわれ日本人はずっと突き進んできたのではないだろうか。明治維新、日露戦争、太平洋戦争、そして3.11。これ以上思考を止めたまま歩き続けてはいけない。
考え続けることによって、問題の本質が解きほぐされ、場合によっては方針の修正や路線の変更さえもあってもおかしくはないはずだが、そういうアプローチは良くない、隊列を乱すなと厳しく叩き込まれてきたように思う、よく考えれば子供のころからそうだった。おい、そこのおまえだ、うろうろせず隊列から離れるな、足並みを揃えろと。
ここには津波は来ないと言われていた [講演を聞いて]
 「想定外を生き抜く力」片田敏孝群馬大学教授の講演を聴いて
「想定外を生き抜く力」片田敏孝群馬大学教授の講演を聴いて3.11後の巨大津波から釜石の子供たちを守った片田先生の津波防災教育のことは、前に紹介している。
巨大津波に繰り返し襲われるという宿命の土地でも、災害の恐怖から目を背けることなく、歴史が教える事実を学び、その中で生き残るすべを身に着ける努力を続けた結果が、3.11の巨大津波で確かな成果となって結実した。「奇跡」は幸運などではなく、必然であったということだろうか。
あの巨大津波から1年以上が経過し、3.11の「その時」に起きたことを住民一人ひとりへの聞き込みなどを重ねて精査し、住民の行動分析を加えた結果、津波災害に対する取り組みを考え直すべき点が少なからず明らかになったという。
津波は事前の想定をはるかに超えた巨大なものではあったが、巻き込まれ命を失った人と際どくも逃げ切った人との差はどこにあったのだろう。片田教授は、ハザードマップへの過度な依存がその一つの鍵になったと指摘している。津波のハザードマップは、その地域に将来生じるであろう災害の規模と範囲を過去の実績に基づいて推測し、災害時に選択すべき避難場所や避難手順を予め決めておくことを目的として自治体によって作成される。災害想定は科学的な知見に基づいた数値シミュレーションを用いて行われるのだが、ここに検証の難しい仮定がいくつも積み重ねられているにもかかわらず、そこから導き出された結果は間違いのない「真実」あるいは神の御宣託であるかのように見えてしまう。
岩手県のある湾奥に位置する街では、津波で多くの命が失われたのだが、その平面分布は決して一様ではなかった。被害者が集中していたのは、海に接した地区ではなく、むしろ海から離れた地区であり、ハザードマップ上では津波到達の可能性が低いと示された場所であった。津波が来る可能性が高いと言われていた地区に住む人は、地震のあとすぐに逃げることを試みたが、ここは大丈夫だろうと思っていた地区の人はすぐに逃げようとはしなかったのだという。マップ上の安全と危険の線引きが、皮肉なことに命の線引きになってしまったのだ。
「この場所は津波が来ないと言われていたので逃げなかった」と線引きの外側、つまり安全と色分けされていた場所に住んでいた住民は、災害後の調査で答えている。行政が作成したハザードマップの上で、危険側には入っていなかったという主張だが、結果的にいえばこれは思い込みでしかなかった。このことを片田教授は、防災に対する「主体性の欠落」が招いた事象と断じている。巨大災害に対する防災で最も重要なことは、行政(お上)に依存しない「主体的」姿勢の醸成にあるという。
自分の、家族のかけがえのない大切な命だからこそ、誰かに頼ればよいという他者依存からまず脱却しなければならない。防災の意識を広く普遍的なレベルに高めるための教育に必要なことは、単なる災害知識の詰め込みではなく、自ら主体的に取り組む以外には命は守れないという「姿勢」を重視した教育であるべきだという。
ここは大丈夫という思い込みは、絶えることのない災害の恐怖を和らげる精神安定剤なのかもしれないが、本当の危険への対応力を長い時間をかけて麻痺させていく毒薬でもあるということなのだ。人の心に関わるところだけに、ここを切り開くのは容易ではない。しかしこれこそが、日本の防災の本質なのだと悟るところからしか津波の教訓を生かせないということなのだろう。
地熱発電、15年間の断絶 [講演を聞いて]
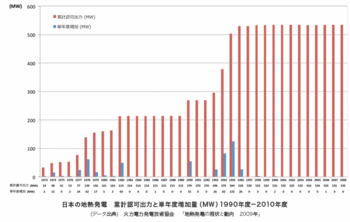 「地熱エネルギー開発の最新動向と地熱研究開発の必要性」弘前大学北日本新エネルギー研究所村岡洋文、東京大学エネルギー工学連携研究センター第14回CEEシンポジウムより
「地熱エネルギー開発の最新動向と地熱研究開発の必要性」弘前大学北日本新エネルギー研究所村岡洋文、東京大学エネルギー工学連携研究センター第14回CEEシンポジウムより石油などの地下資源が決定的に不足しているわが国は、とくにエネルギーについては、他国からそのほとんどを輸入によって賄わなければならない。エネルギーの自給率という指標でみるならば、ほとんどゼロに等しい状況にある。そうした環境下では、原発の停止のように、エネルギー構成の一角、しかも太い柱、が崩れる事態が一度生じると、これを急に代替することができないか、できたとしても多くの国富を国外に流出させることになってしまう。これは急ぎの料金だから、しっかりはずんで貰えますよねと足元を見られるのは必定であろう。
ところが、大事なことを見落としてはいませんかというのが、この村岡氏の講演だ。まず、そもそもわが国は、地熱資源大国であること。しかも、そのポテンシャルは世界第3位。狭い日本は誰にも常識だが、世界の陸域のわずか0.25%に過ぎぬ国土の上に、世界の活火山の7.56%もの活火山を擁しているという。米国、インドネシアに次ぐ世界の第3位の活火山を持ち、地熱資源量もわが国を含む上位3カ国が4位以下を大きく引き離している。にもかかわらず、開発されている地熱発電容量は世界の第8位(2010年)に止まっている。しかもこの10年で開発の進んでいるニュージーランドとアイスランドに相次いで抜かれている。
他にエネルギー資源を持たないわが国が、有力なポテンシャルを抱えていることを知りながら、なぜ開発が進まなかったのだろう。特に、1997年以降は電力開発も研究も途絶えており、世界の潮流からまったくかけ離れてしまっている。この点について、講演後の質疑で「失われた15年」の理由について、村岡氏は「原因はいくつかあるが、一つは財政危機で国の予算に余裕がなくなったこと、もう一つは電力供給の面で原子力がその中核を占めることが固まったこと。結果として、地熱発電はそれまでの開発援助によって実績も上げているので、独り立ちできると判断された」と回答している。
エネルギー政策の転換としては、1997年に地熱が「新エネルギー」から除外されたことが最も大きく、それとともに国の地熱政策予算が激減し、合わせて国立公園内での開発が事実上できなくなったことなどで、投資家が地熱発電開発への投資を躊躇する状況になったことが大きいという。
地熱開発は、それを止めてしまった日本は別として、それ以外の国では最新の技術開発が積極的に続けられている。特に注目すべきは、「涵養地熱システム(EGS)」の実用化が目前となっていることであろう。これは、地球の表面から10km近く深く掘り下がっていけば、世界中どこでも必ず温度が緩やかではあるが上昇するという点に着目し、資源開発で大深度掘削利用技術が進んだことを背景としたもの。深部の透水性の低い層まで掘削し、そこに注水し、そこで加熱された水を地表まで汲み上げる方式である。水のない温泉開発とでも呼ぶのが近いかもしれない。数年前にGoogleがこの開発に大きな投資をしたことで注目を集めているが、最大の特色は火山国でなくとも地熱発電が可能なことで、火山とはほとんど無縁なドイツではすでに大型のプロジェクトが複数動いているという。
実は、この地熱発電によって生み出される電力については、この7月から実施される日本版FIT(固定価格買取制度)の対象に入れられており、さらには環境面などの規制の緩和もあり、これで風向きが大きく変わり、15年ぶりに事業化が動き出すのではないか。特に地熱の潜在賦存量は東日本、特に東北に偏っており、この地域での今後の大きな伸張が期待できそうだ。
それにしても、15年は長い。誰がその償いをできるというのだろう。
つねに慰む [講演を聞いて]
朝日復興フォーラム 2012年2月16日における講演「『被災者』から『震災経験者』になる日 公立志津川病院での東日本大震災の体験を通して:菅野武」を聞き、強く印象に残ったところを会場でのメモと「寄り添い支える」菅野武著、河北新報出版センターを参考にまとめたもの。大変に貴重な体験を聴くことができたことを感謝すると同時に,少しでも多くの人にこの事実と教訓が伝わるべきと考え、不要な感想は挟まず紹介したい。
---
3.11のその時、志津川病院の内科医長であった菅野氏(31歳)は、いつものように回診を終えて二階の医局に戻ったところだった。午後2時46分大きな揺れに襲われ、壁際の本棚が倒れてその下敷きになったパソコンが火を噴いた。直後に停電となり、非常灯に変わった。揺れが収まったところで、3階4階の入院患者の様子を確認、スタッフにも患者にも怪我人はないことが確認。そのころ、町内の防災無線が大津波警報が発令されたことを繰り返し伝え始めていた。志津川病院は、1960年のチリ地震津波の際に2.8mの津波に襲われており、この経験からその倍の6mを想定して3階以上に非難することと、入院病棟も低層階ではなく3,4階のみとするなど対策を講じていた。
菅野氏は、地震動の激しさから従前の想定にこだわらず、少しでも上へ避難したほうがよいと考え、西館5階の会議室(隣接する東棟は4階建て)を目指し患者の搬送を開始した。病院には高齢で寝たきりや移動に介助が必要な入院患者が多く、自力で上階へ非難することができない人がほとんど。加えてエレベーターが地震で停止しており、搬送は車いすや担架に乗せ、あるいは背中におぶって人手ですべて行った。
15時28分、津波が町に到達。病院に到達してからわずか2分ほどで病院の周囲の家屋はほとんど流され、水位がさらに急速に上昇した。15時39分に最高水位に達し、病院の4階天井まで濁流に没した。遅れて搬送中だった患者やスタッフは呑みこまれ流された。目の前で多くの命が奪われた。その時、菅野氏は絶望感と無力感に打ちのめされ、悔しさで自らに怒りすら覚えたという。
津波が足元わずか数十㌢まで押し寄せる中で、菅野氏は死を覚悟し、普段は手術のためにはずしている結婚指輪を左手にはめた。もしもの時に家族が自分を見つけられるように。菅野氏の奥さんはそのとき妊娠中、しかも臨月で、三歳になる娘さんとともに出産準備のため、地震のほんの十日まえに仙台の実家に戻っており津波を免れていたのだ。
その後、津波はピークから三十分ほどかけて、徐々に水位を下げた。そのとき菅野氏は、「少し津波が引いてきたので、下の階に生きている人を探しに行こうと思う。もし良ければ一緒に来てくれる人はいませんか」とまわりにいたスタッフに声をかけた。「後悔したくない」という思いに突き動かされたのだという。まだ危険があるので「行かないほうがいい」という意見もあったし、それもまったく正しいとも思ったという。自分の意思で決めることで強制することではないとも。それでも菅野氏は数人のスタッフとともに動いた。4階のフロアに向かったのだ。
かつて見たこともない地獄がそこにあった。そのとき、生きている患者が見つかった。寝たきりでしかも天井まで水が来ている中でどうやって命を守ったのか。寝たきり患者はエアーマットを使うこともあるので浮きとなって救われたのか。他にもカーテンにしがみついて流されずにいた人やベッドに挟まれながら生きている人が見つかった。東西の四階病棟で、十人近く息のある人を見つけることができた。
こうして避難してきた五階は単なる会議室であり、医療資機材も医療用酸素もなにもない状況は一切改善してはいなかった。しかし資材がないからといってあきらめず、衣服の濡れている人は脱がし、図書室から持ってきたダンボールに寝たきりの患者を寝かせ、さらに窓からカーテンをはずして患者にかけ、保温に努めた。その夜は、周辺からの避難者を合わせた250人近くが、その五階で身を寄せ合って過ごした。
その中でできたことは、苦しみ嘆く人に寄り添い、支えることがほとんどだった。救えない悔しさは当然あるが、寄り添い支えることもそのとき与えられた大切な医師としての使命であったと菅野氏は振りかえる。
「時に癒し、しばしば支え、常に慰む」これは、米国で結核療養所を開いたエドワード・リビング・トルドー(1848-1915)の記念碑にフランス語で刻まれている言葉で、患者たちが感謝の気持ちを込めて捧げられたとされている。菅野氏は研修医を終え地域医療に取り組むようになったころにこの言葉に出会った。患者が医療に求めていることは、治すことばかりではなく、病や苦しみとの闘いを支え、慰めることも大切であることを医療の現場で知ったという。今回の津波で深い敗北感と無力感を突きつけられたが、治したいという気持ちは根底に持ちながら、目の前の困っている人を支え、慰めることの大切さを知っていたからこそ、「後悔したくない」と決意し、「普段の医療をしよう」と思ったという。
地震後の3月16日に生まれたお子さん(男子)の名前は「怜」。いかなる困難にも立ち向かう知恵という文字通りの意と、レイという読みに英語のray:暗闇を照らす一条の光線という意を重ねたという。
---
菅野氏は、震災直後の医療支援活動中の3月末に米TIME誌の取材を受け、それがきっかけで4月21日に発表されたTIMEの「世界の100人:The 2011 TIME 100」に南相馬市長の桜井勝延氏とともに選ばれている。
---
3.11のその時、志津川病院の内科医長であった菅野氏(31歳)は、いつものように回診を終えて二階の医局に戻ったところだった。午後2時46分大きな揺れに襲われ、壁際の本棚が倒れてその下敷きになったパソコンが火を噴いた。直後に停電となり、非常灯に変わった。揺れが収まったところで、3階4階の入院患者の様子を確認、スタッフにも患者にも怪我人はないことが確認。そのころ、町内の防災無線が大津波警報が発令されたことを繰り返し伝え始めていた。志津川病院は、1960年のチリ地震津波の際に2.8mの津波に襲われており、この経験からその倍の6mを想定して3階以上に非難することと、入院病棟も低層階ではなく3,4階のみとするなど対策を講じていた。
菅野氏は、地震動の激しさから従前の想定にこだわらず、少しでも上へ避難したほうがよいと考え、西館5階の会議室(隣接する東棟は4階建て)を目指し患者の搬送を開始した。病院には高齢で寝たきりや移動に介助が必要な入院患者が多く、自力で上階へ非難することができない人がほとんど。加えてエレベーターが地震で停止しており、搬送は車いすや担架に乗せ、あるいは背中におぶって人手ですべて行った。
15時28分、津波が町に到達。病院に到達してからわずか2分ほどで病院の周囲の家屋はほとんど流され、水位がさらに急速に上昇した。15時39分に最高水位に達し、病院の4階天井まで濁流に没した。遅れて搬送中だった患者やスタッフは呑みこまれ流された。目の前で多くの命が奪われた。その時、菅野氏は絶望感と無力感に打ちのめされ、悔しさで自らに怒りすら覚えたという。
津波が足元わずか数十㌢まで押し寄せる中で、菅野氏は死を覚悟し、普段は手術のためにはずしている結婚指輪を左手にはめた。もしもの時に家族が自分を見つけられるように。菅野氏の奥さんはそのとき妊娠中、しかも臨月で、三歳になる娘さんとともに出産準備のため、地震のほんの十日まえに仙台の実家に戻っており津波を免れていたのだ。
その後、津波はピークから三十分ほどかけて、徐々に水位を下げた。そのとき菅野氏は、「少し津波が引いてきたので、下の階に生きている人を探しに行こうと思う。もし良ければ一緒に来てくれる人はいませんか」とまわりにいたスタッフに声をかけた。「後悔したくない」という思いに突き動かされたのだという。まだ危険があるので「行かないほうがいい」という意見もあったし、それもまったく正しいとも思ったという。自分の意思で決めることで強制することではないとも。それでも菅野氏は数人のスタッフとともに動いた。4階のフロアに向かったのだ。
かつて見たこともない地獄がそこにあった。そのとき、生きている患者が見つかった。寝たきりでしかも天井まで水が来ている中でどうやって命を守ったのか。寝たきり患者はエアーマットを使うこともあるので浮きとなって救われたのか。他にもカーテンにしがみついて流されずにいた人やベッドに挟まれながら生きている人が見つかった。東西の四階病棟で、十人近く息のある人を見つけることができた。
こうして避難してきた五階は単なる会議室であり、医療資機材も医療用酸素もなにもない状況は一切改善してはいなかった。しかし資材がないからといってあきらめず、衣服の濡れている人は脱がし、図書室から持ってきたダンボールに寝たきりの患者を寝かせ、さらに窓からカーテンをはずして患者にかけ、保温に努めた。その夜は、周辺からの避難者を合わせた250人近くが、その五階で身を寄せ合って過ごした。
その中でできたことは、苦しみ嘆く人に寄り添い、支えることがほとんどだった。救えない悔しさは当然あるが、寄り添い支えることもそのとき与えられた大切な医師としての使命であったと菅野氏は振りかえる。
「時に癒し、しばしば支え、常に慰む」これは、米国で結核療養所を開いたエドワード・リビング・トルドー(1848-1915)の記念碑にフランス語で刻まれている言葉で、患者たちが感謝の気持ちを込めて捧げられたとされている。菅野氏は研修医を終え地域医療に取り組むようになったころにこの言葉に出会った。患者が医療に求めていることは、治すことばかりではなく、病や苦しみとの闘いを支え、慰めることも大切であることを医療の現場で知ったという。今回の津波で深い敗北感と無力感を突きつけられたが、治したいという気持ちは根底に持ちながら、目の前の困っている人を支え、慰めることの大切さを知っていたからこそ、「後悔したくない」と決意し、「普段の医療をしよう」と思ったという。
地震後の3月16日に生まれたお子さん(男子)の名前は「怜」。いかなる困難にも立ち向かう知恵という文字通りの意と、レイという読みに英語のray:暗闇を照らす一条の光線という意を重ねたという。
---
菅野氏は、震災直後の医療支援活動中の3月末に米TIME誌の取材を受け、それがきっかけで4月21日に発表されたTIMEの「世界の100人:The 2011 TIME 100」に南相馬市長の桜井勝延氏とともに選ばれている。
故郷に報いる [講演を聞いて]
「巨大水災害に関する国際フォーラム」2011年9月27日(於国際連合大学)で、立谷秀清相馬市長が「東日本大震災を経験して」という基調講演を行った。約30分の講演では、被災地の首長としての責務を果たすべく奮闘し続けている話しを直接に聴くことができた。その際のメモをもとにしてその概要をご紹介したい。
--------------------------
相馬市は人口3万8千人の農業と漁業を主とする典型的な地方都市。
3.11の地震がありその9分後には対策本部を市の中に立ち上げた。まず消防団に対して、とにかく津波から市民を逃がせ、逃げるように誘導しろと指示した。団員は、このときこそ消防の仕事と命をかけて弱者を守ろうとした。襲いかかる巨大な津波を確認し、躊躇しながらも役目を果たすために踏みとどまって、結果呑み込まれた者もいた。団員の子どもが母が止めたこともあったが、彼らは向っていった。10人の団員が犠牲となり還ってはこなかった。市全体で、残念ながら400人の市民の命が失われた。多くの遺児がこうして生まれてしまった。
対策本部を立ち上げ、まず打つべき手を考えた。指示を次々に出した。倒壊状況の確認、生存者の確認、火災... 避難をしてもらったあとは、避難所で住民基本台帳と避難者との突合を確実に行った。これがないと次の手が打てない。最初は水が重要になる。スーパーに供出可能な水と食料品の在庫を確認する。
次々に指示を出し続けて、4回目の本部会議は12時を回った12日の午前3時になる。それでも、手がすべて打てているか、抜けていることはなかったか、さらに頭をしぼる。すぐに夜が明ける。凄惨な状況を前に足がすくんでいてはいけない。まずやることはなんだ。毛布の備蓄が700枚しかなく、避難者に届かない。すぐに市内に毛布提供カンパを呼びかける。市内でも、被災の少ない地区であれば、空きアパートや空き住宅を手配できれば仮住まいに使えるだろう。仮設住宅を設けられそうな場所を想定し、県と協議を始める。瓦礫の山と化した街を立て直すために、まず撤去して復旧のための道路確保だが、さて重機は手配できるか。市内の建設業者に問い合わせる。
被災して体一つで逃げてしまった市民に、とりあえず必要な現金をわたそう。ひとり3万円ではどうか。しばらくして支援金を配ることができるようになったが、これは副次的な効果もあった。支給時に結果として生存確認ができる。住民基本台帳との突合が進む。
さらに時間が経過していくと、市民の心のケアが課題となる。とくに、経済的に自殺に追い込まれるケースと児童のPTSDに着目し、これをなんとか救うための対策チームを臨床心理士などを加えて立ち上げた。
震災で親を失った孤児の総数は51名。そのすべてに毎月3万円を18歳まで支給する教育義援金を募ったところたちまち全国から協力をいただきその必要な総額の確保はできた。さらに上積みの基金は大学まで進もうとする者への支援に回そうと考えている。
相馬は福島県の中ではセシウムなどの放射線の状況が深刻ではないが、ホットスポットなど除染に早く着手するなどで不安を取り除かなければならない。プロジェクトチームを編成してこの対策にあたっている。住民の不安をとにかく軽減させること。親の不安が子に伝染する。検査を繰り返し、必要な場所の除染を徹底し不安を消し去ること。子どもたちに不安を与えるようなことがあってはならない。
まだまだやらなければならないことがあるが、国の動きがどうとかできない言い訳をしていても始まらない。基礎自治体さらにいえば地方政府として自分たちのことは自分たちでやらなければならない。目指すのは、子どもは健やかに育つこと、老人は安心して暮らせること、壮年は今後の人生の再設計ができること。しかし、新しい地域づくりは相馬だけではできない。国の力、世界の力、社会の力を借りなければならない。そのためにも被災から復興への進捗状況を支援していただく方と共有していきたい。首長として故郷に報いるのは、相馬市を復興させること。皆さんの友情をいただき進めたい。
--------------------------
相馬市は人口3万8千人の農業と漁業を主とする典型的な地方都市。
3.11の地震がありその9分後には対策本部を市の中に立ち上げた。まず消防団に対して、とにかく津波から市民を逃がせ、逃げるように誘導しろと指示した。団員は、このときこそ消防の仕事と命をかけて弱者を守ろうとした。襲いかかる巨大な津波を確認し、躊躇しながらも役目を果たすために踏みとどまって、結果呑み込まれた者もいた。団員の子どもが母が止めたこともあったが、彼らは向っていった。10人の団員が犠牲となり還ってはこなかった。市全体で、残念ながら400人の市民の命が失われた。多くの遺児がこうして生まれてしまった。
対策本部を立ち上げ、まず打つべき手を考えた。指示を次々に出した。倒壊状況の確認、生存者の確認、火災... 避難をしてもらったあとは、避難所で住民基本台帳と避難者との突合を確実に行った。これがないと次の手が打てない。最初は水が重要になる。スーパーに供出可能な水と食料品の在庫を確認する。
次々に指示を出し続けて、4回目の本部会議は12時を回った12日の午前3時になる。それでも、手がすべて打てているか、抜けていることはなかったか、さらに頭をしぼる。すぐに夜が明ける。凄惨な状況を前に足がすくんでいてはいけない。まずやることはなんだ。毛布の備蓄が700枚しかなく、避難者に届かない。すぐに市内に毛布提供カンパを呼びかける。市内でも、被災の少ない地区であれば、空きアパートや空き住宅を手配できれば仮住まいに使えるだろう。仮設住宅を設けられそうな場所を想定し、県と協議を始める。瓦礫の山と化した街を立て直すために、まず撤去して復旧のための道路確保だが、さて重機は手配できるか。市内の建設業者に問い合わせる。
被災して体一つで逃げてしまった市民に、とりあえず必要な現金をわたそう。ひとり3万円ではどうか。しばらくして支援金を配ることができるようになったが、これは副次的な効果もあった。支給時に結果として生存確認ができる。住民基本台帳との突合が進む。
さらに時間が経過していくと、市民の心のケアが課題となる。とくに、経済的に自殺に追い込まれるケースと児童のPTSDに着目し、これをなんとか救うための対策チームを臨床心理士などを加えて立ち上げた。
震災で親を失った孤児の総数は51名。そのすべてに毎月3万円を18歳まで支給する教育義援金を募ったところたちまち全国から協力をいただきその必要な総額の確保はできた。さらに上積みの基金は大学まで進もうとする者への支援に回そうと考えている。
相馬は福島県の中ではセシウムなどの放射線の状況が深刻ではないが、ホットスポットなど除染に早く着手するなどで不安を取り除かなければならない。プロジェクトチームを編成してこの対策にあたっている。住民の不安をとにかく軽減させること。親の不安が子に伝染する。検査を繰り返し、必要な場所の除染を徹底し不安を消し去ること。子どもたちに不安を与えるようなことがあってはならない。
まだまだやらなければならないことがあるが、国の動きがどうとかできない言い訳をしていても始まらない。基礎自治体さらにいえば地方政府として自分たちのことは自分たちでやらなければならない。目指すのは、子どもは健やかに育つこと、老人は安心して暮らせること、壮年は今後の人生の再設計ができること。しかし、新しい地域づくりは相馬だけではできない。国の力、世界の力、社会の力を借りなければならない。そのためにも被災から復興への進捗状況を支援していただく方と共有していきたい。首長として故郷に報いるのは、相馬市を復興させること。皆さんの友情をいただき進めたい。
海ゆかば [講演を聞いて]
「災害と日本人のこころ」 山折哲雄氏講演,2011.9.8 を聞いて
震災後、宗教学者である山折氏は、前にも紹介しているように、東日本の震災についていくつかの論考を示している。とくに、被災者の「穏やかな表情」に大きく心を打たれ、その理由が何千年続く日本人の生き方の中にあること、そしてそれがこれからの復興を考えるときの大事なよりどころになることなどを述べている。
その山折氏の講演を聴く機会があったので、その概要を紹介したい。
氏は、3.11から1ヶ月経ち、被災地の東松島、石巻、気仙沼などに足を運んだ。そこにある見渡す限りの瓦礫に声を失った。仏の気配がまったくない、地獄だと思ったという。津波に襲われた街にはまだ無数の死体が残っているが、埋葬の儀礼がすめばそれで本当に心は癒されるのかと厳しく問いかける。
“海行かば 水清く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見はせじ” 万葉集の中で、大伴家持がこの歌にこめた思いは死者に対する静かな鎮魂であり、魂に深く思いをいたす日本人特有のこころの有様だというのだが、未曾有の災害を目前にしている現代の日本人には、家持が示したような死者の魂に対する思いやりが果たしてあるのだろうかと疑問を投げかける。
万葉集といえば相聞歌(恋の歌)を連想するが、挽歌(葬送の歌)が多いことも特徴となっている。挽歌の内容をみると、死者の多くは事故死によるもので、戦乱、飢饉、そして何より災害によるものが多い。万葉の時代から千数百年、災害と戦乱が繰り返し、多くの命が犠牲となってきた。日本は、地震・津波・台風・洪水などの自然災害の激しさと頻度が高く、この恐ろしさがまさに五臓六腑にしみわたっており、日本特有の危機管理の考え方が時代を越えて受け継がれているはずだ。そうした国に生きるものとして、死者の魂に深く思いをはせることがこの現代でもできているだろうか、と。
自然災害に対する深い思索を示した二つの代表的著作、寺田寅彦の「日本人の自然観」と和辻哲郎の「風土 人間学的考察」、いずれも昭和10年に出版されている。寺田寅彦は関東大震災を地震学者でもある自らの目で観察しその本質に迫ろうとした。日本人の災害観とは、抗いようのない大きな自然の力に対し、頭を垂れ、膝を屈していかにやり過ごすかを考えることにあり、仏教が伝来するはるか以前から天然の無常観が形成されていた。
しかし、西欧的には、無常観は単なる環境決定論と決め付けられ、それを克服することこそ文明の役割とされてしまう。これに日本として異議を唱えてこなかったことが今回の災害への取り組みを混乱させている理由の一つになっているのではと問いかける。災害を考えるときに、西欧的ではない違った尺度があってよいのだと。英国にもフランスにも地震はなく、台風も来ないのだから。
台風といえば、和辻哲郎は「風土」の中で台風災害を中心に論考を展開しており、地震については一言も触れていない。関東大震災の直後にまとめられたことを考えれば意外ともいえる。和辻は、理系の寺田と異なり、倫理学者で人と人のつながりや社会ネットワークの観点から日本の精神風土にいどんでいる。そして、日本はアジア独特のモンスーンで特徴づけられるとする。モンスーン(あるいは台風)の特徴は、寒帯的(大雨)かつ温帯的(熱暑)であること、そして季節的かつ突発的であること。この対比を和辻は“しめやかな激情”あるいは“戦争的恬淡”という言葉で表し、矛盾する二つの性格が並存することが日本のこころであると述べている。
山折氏の講演は最後に福島原発への対処という重い課題にいたり、犠牲論という深淵に踏み込むのだが、メモが不十分なこともありこの部分は割愛したい。
震災後、宗教学者である山折氏は、前にも紹介しているように、東日本の震災についていくつかの論考を示している。とくに、被災者の「穏やかな表情」に大きく心を打たれ、その理由が何千年続く日本人の生き方の中にあること、そしてそれがこれからの復興を考えるときの大事なよりどころになることなどを述べている。
その山折氏の講演を聴く機会があったので、その概要を紹介したい。
氏は、3.11から1ヶ月経ち、被災地の東松島、石巻、気仙沼などに足を運んだ。そこにある見渡す限りの瓦礫に声を失った。仏の気配がまったくない、地獄だと思ったという。津波に襲われた街にはまだ無数の死体が残っているが、埋葬の儀礼がすめばそれで本当に心は癒されるのかと厳しく問いかける。
“海行かば 水清く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見はせじ” 万葉集の中で、大伴家持がこの歌にこめた思いは死者に対する静かな鎮魂であり、魂に深く思いをいたす日本人特有のこころの有様だというのだが、未曾有の災害を目前にしている現代の日本人には、家持が示したような死者の魂に対する思いやりが果たしてあるのだろうかと疑問を投げかける。
万葉集といえば相聞歌(恋の歌)を連想するが、挽歌(葬送の歌)が多いことも特徴となっている。挽歌の内容をみると、死者の多くは事故死によるもので、戦乱、飢饉、そして何より災害によるものが多い。万葉の時代から千数百年、災害と戦乱が繰り返し、多くの命が犠牲となってきた。日本は、地震・津波・台風・洪水などの自然災害の激しさと頻度が高く、この恐ろしさがまさに五臓六腑にしみわたっており、日本特有の危機管理の考え方が時代を越えて受け継がれているはずだ。そうした国に生きるものとして、死者の魂に深く思いをはせることがこの現代でもできているだろうか、と。
自然災害に対する深い思索を示した二つの代表的著作、寺田寅彦の「日本人の自然観」と和辻哲郎の「風土 人間学的考察」、いずれも昭和10年に出版されている。寺田寅彦は関東大震災を地震学者でもある自らの目で観察しその本質に迫ろうとした。日本人の災害観とは、抗いようのない大きな自然の力に対し、頭を垂れ、膝を屈していかにやり過ごすかを考えることにあり、仏教が伝来するはるか以前から天然の無常観が形成されていた。
しかし、西欧的には、無常観は単なる環境決定論と決め付けられ、それを克服することこそ文明の役割とされてしまう。これに日本として異議を唱えてこなかったことが今回の災害への取り組みを混乱させている理由の一つになっているのではと問いかける。災害を考えるときに、西欧的ではない違った尺度があってよいのだと。英国にもフランスにも地震はなく、台風も来ないのだから。
台風といえば、和辻哲郎は「風土」の中で台風災害を中心に論考を展開しており、地震については一言も触れていない。関東大震災の直後にまとめられたことを考えれば意外ともいえる。和辻は、理系の寺田と異なり、倫理学者で人と人のつながりや社会ネットワークの観点から日本の精神風土にいどんでいる。そして、日本はアジア独特のモンスーンで特徴づけられるとする。モンスーン(あるいは台風)の特徴は、寒帯的(大雨)かつ温帯的(熱暑)であること、そして季節的かつ突発的であること。この対比を和辻は“しめやかな激情”あるいは“戦争的恬淡”という言葉で表し、矛盾する二つの性格が並存することが日本のこころであると述べている。
山折氏の講演は最後に福島原発への対処という重い課題にいたり、犠牲論という深淵に踏み込むのだが、メモが不十分なこともありこの部分は割愛したい。
遠方目標はどこだ [講演を聞いて]
日本再生シンポジウム「日本を元気に」いま私たちにできること、2011年7月25日三井日本橋ホールにて
(録音もメモも取っていないので、記憶に誤りがあるかもしれないが、大きくは違っていない。たぶん...)
シンポジウム後半のパネル討論に参加した村井嘉浩宮城県知事が戦場の現場指揮官として圧倒的な存在感をみせた。文字にしてしまうと普通のあるいは常識的な内容でも、人の言葉として投げかれられるものの力はすごい。人を束ね引っ張っていくというのはこういうことだということが直感的に理解できる。
村井知事は繰り返し、被災者だけでは復興はできないと訴えている。もともと、東北は農業と水産業に強みがあったが、政府の振興策が有効に機能しないままに高齢化と零細化が進行してしまったので、元に戻すだけでは抱えていた構造的な問題は解決しない、しないどころか、20年後30年後には若者がいなくなり産業が滅びかねない。だから、いま思いきって集約統合による規模拡大と民間活力の導入を進めるべきだ。既得権者からの反発も大きいが、この方向に対する理解を広げてなんとか進めたいと熱く語った。
現状の規制を乗り越える仕組みを準備すれば、復興に参加したい企業が必ず被災地に乗り込んでくれる。国内だけでなく国外の企業も資本も、そこに魅力とビジョンがあるとわかれば必ず参加する。だからスピードがとにかく大事、そして財源。これができないと何も前には進まない。さらに、日本の官僚はとても優秀だから、進む方向さえきっちり示せば必ず期待に違わぬ、いやそれ以上の結果を出してくれると強調する。だから復興はできる、日本は再生できると断言した。政治主導などという机上の言葉あそびにうつつをぬかしているどこかの集団に聞かせたい。
そして、知事がシンポジウムの最後のまとめで述べた次のエピソードは新しい内容ではないのだが、いまの日本の政治状況を思うと、要点まさにここにありと感じる。
「私は自衛官時代、ヘリのパイロットでした。ヘリを発進し、最初にやるのは遠方目標をとるということ、できるだけ遠くの山や鉄塔などを、最初に遠方目標とする。そうしておいて、その手前に中間目標を見つけこれを結んで軸線とする。風や霧で自分の位置を見失っても、まず遠方目標を見つける。そしてすぐ軸線に戻れば、目的地にたどりつけます。下ばかり見ていると、自分がいまどこを飛んでいるのかが分からなくなりますが、遠方目標にもどるという原則さえ保てれば進む道を失うことはありません。知事になって、将来ビジョンをつくった時に、分かりやすい遠方目標を掲げることで、県づくりに努めてきました。国にお願いしたいことは、この国の未来、例えば百年後の姿を示してほしいということです。」
菅さんの最大の強みはリアリズムにあるそうだが、ときにリアリズムを追いかけすぎて理念をなおざりにしがちだともいう。もちろん、そこには遠方目標などない。まったく残念なことに。
(録音もメモも取っていないので、記憶に誤りがあるかもしれないが、大きくは違っていない。たぶん...)
シンポジウム後半のパネル討論に参加した村井嘉浩宮城県知事が戦場の現場指揮官として圧倒的な存在感をみせた。文字にしてしまうと普通のあるいは常識的な内容でも、人の言葉として投げかれられるものの力はすごい。人を束ね引っ張っていくというのはこういうことだということが直感的に理解できる。
村井知事は繰り返し、被災者だけでは復興はできないと訴えている。もともと、東北は農業と水産業に強みがあったが、政府の振興策が有効に機能しないままに高齢化と零細化が進行してしまったので、元に戻すだけでは抱えていた構造的な問題は解決しない、しないどころか、20年後30年後には若者がいなくなり産業が滅びかねない。だから、いま思いきって集約統合による規模拡大と民間活力の導入を進めるべきだ。既得権者からの反発も大きいが、この方向に対する理解を広げてなんとか進めたいと熱く語った。
現状の規制を乗り越える仕組みを準備すれば、復興に参加したい企業が必ず被災地に乗り込んでくれる。国内だけでなく国外の企業も資本も、そこに魅力とビジョンがあるとわかれば必ず参加する。だからスピードがとにかく大事、そして財源。これができないと何も前には進まない。さらに、日本の官僚はとても優秀だから、進む方向さえきっちり示せば必ず期待に違わぬ、いやそれ以上の結果を出してくれると強調する。だから復興はできる、日本は再生できると断言した。政治主導などという机上の言葉あそびにうつつをぬかしているどこかの集団に聞かせたい。
そして、知事がシンポジウムの最後のまとめで述べた次のエピソードは新しい内容ではないのだが、いまの日本の政治状況を思うと、要点まさにここにありと感じる。
「私は自衛官時代、ヘリのパイロットでした。ヘリを発進し、最初にやるのは遠方目標をとるということ、できるだけ遠くの山や鉄塔などを、最初に遠方目標とする。そうしておいて、その手前に中間目標を見つけこれを結んで軸線とする。風や霧で自分の位置を見失っても、まず遠方目標を見つける。そしてすぐ軸線に戻れば、目的地にたどりつけます。下ばかり見ていると、自分がいまどこを飛んでいるのかが分からなくなりますが、遠方目標にもどるという原則さえ保てれば進む道を失うことはありません。知事になって、将来ビジョンをつくった時に、分かりやすい遠方目標を掲げることで、県づくりに努めてきました。国にお願いしたいことは、この国の未来、例えば百年後の姿を示してほしいということです。」
菅さんの最大の強みはリアリズムにあるそうだが、ときにリアリズムを追いかけすぎて理念をなおざりにしがちだともいう。もちろん、そこには遠方目標などない。まったく残念なことに。
被災地の医療崩壊に挑む [講演を聞いて]
震災から4ヶ月が過ぎた、あの時は雪が舞うような寒さだったのに、もう厳しい夏が来てしまった。そんなタイミングで、災害医療の現場で今も戦っている人々の存在を知った。里見進氏(東北大学病院長、東北大学副学長)の講演から概要を紹介したい:東日本大震災 ― 大学病院の対応と今後の課題 ― 7月10日、東北大学関東交流会での講演。
報道メディアの関心が被災者の置かれている環境改善に向いているためか、医療の視点で復興をとらえたものは少ない。貴重な話しを聞くことができた。
「前線の後方基地になる」
地震が発生し、大学の研究棟では棚や多くの設備が倒れる状況で、次に天井が落ちてきたら万事休すとまで覚悟したという。研究棟でこうであれば、患者のいる病棟は更に深刻な状況に陥っており、市内でも家屋倒壊が多発しているはずで、時を置かずに大学病院は野戦病院と化すに違いないと里見氏は判断した。しかも、市内すべて停電になった中で、非常用電源が動いて明かりのみえる病院には、近隣の人が避難して来るに違いない。そうなれば医療機関としての役割が果たせなくなるので、医療措置が必要な人を除いては近くの避難所へ回ってもらうよう敢えて指示をしたという。責任はすべて院長の自分が持つから。
この判断によって、病院ではトリアージ体制も準備し、担ぎ込まれる負傷者を待ったのだが、発災当日にはほとんど来なかった。肩すかしを食ったことになったが、これは次の宮城県沖地震が目前に近づいているという認識が県内特に仙台市内で徹底しており、耐震補強工事などが進んだことと、神戸のような直下地震ではなかったことによるのかもしれない。地震を意識して訓練を繰り返しており、これが役に立った。福島の放射線への対応についても、事前の準備はできており(女川原発の事故を想定したものだったが)あわてずにすんだ。こうして大学病院は前線の後方支援基地に変わった。
「専門を捨てろ」
時間の進行とともに、沿岸部が津波で甚大な被害を受けていることが明らかになってきたが、行政からの情報はほとんど得られず、週末に東北大から地方の病院に出向いていた医師が週明けに戻り始め、ようやく各地の病院や避難所の状況が見え始めた。医療体制が壊滅した地域が少なからずあることが判りはじめた時点で、大学病院が中心となって医師の派遣を開始することになった。このとき、「専門を捨てて総合医として活動」することを全員に要請した。さらに手が足りないことから、同時に全国に医療チーム派遣支援を要請した。
「エリアに権限を」
支援の手がそろってくると、次は全体の調整と統括を誰がするかという課題がたちまち持ち上がってきたが、県の災害対策本部との検討でまず大きくエリアを分け、その中での判断は中長期に滞在して支援してくれるエリアの責任者にゆだねること、重症患者への対応など全体の調整が必要な部分だけ大学病院が関与することなどをルール化した。大学病院から現地への派遣もできるだけ抑制し、被災地からの患者の受け入れに注力することで役割を明確に分けた。地域を支えていた病院が施設もスタッフも失った状況下で、医療をこれからも息長く継続させていくために、後方支援の形はどうあるべきかを最初に想定し、これを地道な行動で裏付けた。いまでも上からは見えにくいが、深く堅実な活動が進められている。
こうした医療の現場の壮絶な戦いが被災地の復興を支えている。もっと多くの場で知らされてもよいし、むしろ支援がその役目を果たす後の地域医療体制を再構築するためにもこうしたシステムの重要性を広く訴えるべきだ。ちなみに、7月2日のNHKスペシャルで「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」という放送があったようだ。里見氏の講演でも出ていた石巻赤十字病院における医療崩壊に立ち向かう医師チームの記録だ。見逃したのが悔やまれる。
報道メディアの関心が被災者の置かれている環境改善に向いているためか、医療の視点で復興をとらえたものは少ない。貴重な話しを聞くことができた。
「前線の後方基地になる」
地震が発生し、大学の研究棟では棚や多くの設備が倒れる状況で、次に天井が落ちてきたら万事休すとまで覚悟したという。研究棟でこうであれば、患者のいる病棟は更に深刻な状況に陥っており、市内でも家屋倒壊が多発しているはずで、時を置かずに大学病院は野戦病院と化すに違いないと里見氏は判断した。しかも、市内すべて停電になった中で、非常用電源が動いて明かりのみえる病院には、近隣の人が避難して来るに違いない。そうなれば医療機関としての役割が果たせなくなるので、医療措置が必要な人を除いては近くの避難所へ回ってもらうよう敢えて指示をしたという。責任はすべて院長の自分が持つから。
この判断によって、病院ではトリアージ体制も準備し、担ぎ込まれる負傷者を待ったのだが、発災当日にはほとんど来なかった。肩すかしを食ったことになったが、これは次の宮城県沖地震が目前に近づいているという認識が県内特に仙台市内で徹底しており、耐震補強工事などが進んだことと、神戸のような直下地震ではなかったことによるのかもしれない。地震を意識して訓練を繰り返しており、これが役に立った。福島の放射線への対応についても、事前の準備はできており(女川原発の事故を想定したものだったが)あわてずにすんだ。こうして大学病院は前線の後方支援基地に変わった。
「専門を捨てろ」
時間の進行とともに、沿岸部が津波で甚大な被害を受けていることが明らかになってきたが、行政からの情報はほとんど得られず、週末に東北大から地方の病院に出向いていた医師が週明けに戻り始め、ようやく各地の病院や避難所の状況が見え始めた。医療体制が壊滅した地域が少なからずあることが判りはじめた時点で、大学病院が中心となって医師の派遣を開始することになった。このとき、「専門を捨てて総合医として活動」することを全員に要請した。さらに手が足りないことから、同時に全国に医療チーム派遣支援を要請した。
「エリアに権限を」
支援の手がそろってくると、次は全体の調整と統括を誰がするかという課題がたちまち持ち上がってきたが、県の災害対策本部との検討でまず大きくエリアを分け、その中での判断は中長期に滞在して支援してくれるエリアの責任者にゆだねること、重症患者への対応など全体の調整が必要な部分だけ大学病院が関与することなどをルール化した。大学病院から現地への派遣もできるだけ抑制し、被災地からの患者の受け入れに注力することで役割を明確に分けた。地域を支えていた病院が施設もスタッフも失った状況下で、医療をこれからも息長く継続させていくために、後方支援の形はどうあるべきかを最初に想定し、これを地道な行動で裏付けた。いまでも上からは見えにくいが、深く堅実な活動が進められている。
こうした医療の現場の壮絶な戦いが被災地の復興を支えている。もっと多くの場で知らされてもよいし、むしろ支援がその役目を果たす後の地域医療体制を再構築するためにもこうしたシステムの重要性を広く訴えるべきだ。ちなみに、7月2日のNHKスペシャルで「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」という放送があったようだ。里見氏の講演でも出ていた石巻赤十字病院における医療崩壊に立ち向かう医師チームの記録だ。見逃したのが悔やまれる。
温暖化が冬の雷神を怒らせる [講演を聞いて]
「日本海側における冬季雷の増加傾向について」 高田吉治氏(株式会社応用気象エンジニアリング社長)の第32回風力エネルギーシンポジウムでの発表より
風力エネルギーシンポジウム(11月24日)で、冬の雷について興味深い発表があった。発表した高田氏によれば、日本海側の冬雷がこのところ増加を続けているが、地球温暖化がその原因ではないかという研究である。
金沢の雷日数は、1930年代から50年代にかけて年間20日ほどで推移したが、60年代から増加を始め、2000年代に入ると毎年40日以上に倍加。しかもその増分のほとんどは冬季雷によるもの。中でも豪雪となった2005年12月には、その一ヶ月間で18日の雷日数を記録している。これでは、いつもゴロゴロと空が鳴っているような穏やかならぬ状況だ。
北陸の城下町金沢で少年時代を過ごした(8年間)者としては、この冬季雷の話しは気になる。北陸の暗い空の下で、昼も夜もなく遠く地響きのように長くとどろく雷鳴。記憶の深い底にひっそりと刻まれたままだ。でも東京の人間に冬の雷の話をしてもまったく通じない、雷というのは夏の季語なのだ、ここでは。
しかし、ちょっとまてよ。温暖化は暖冬につながり、暖冬なら少雪になる、とすると雷も少なくなるのではないか?現象が逆じゃないか?
こうした疑念に高田氏は次のような説明をしている。まず、冬季雷はなぜ生じるのか。寒気がどんどん大陸に溜まり、これが吐き出されるように日本を襲うだけでは雷にはならない。寒気が日本へ到達する際に、越えていく日本海が十分に暖かいときにだけ雲が発達し、雷雲を生じる。日本海の水温も気温に引きずられて冬には低下するのだが、大気の変化のほうがどうしても早くなる。この差が3ヶ月近くになる(水の比熱が大きいから)ため、大気は本番並みに寒いのに海がとんでもなく暖かい(相対的に)という現象が生じることになる。
高田氏によれば、冬季雷の引き金となる大気と海水温の差は10℃。これまでの観測ではこの差が15℃を越えているときに雷が頻発しているという。メカニズムとしては、海水と大気の温度差が拡大することによって海表面からの蒸発が一層促進され、大陸を出たときにはカラカラに乾いていた寒気が、日本海を越えている間にたっぷり湿気を含み連続的な雪雲を形成するものと考えられる。
ここまで説明されると、温暖化が日本海を徐々に暖め、その水温が上昇することによって寒気と海水表面の温度差が拡大し、雷雲を激しく成長させるから冬の雷の頻度が高くなる、ということがなんとなく理解できる。その一方で、高田氏によれば、冬季雷の発生は徐々に増加しているが、降雪量は増加しているとは言えないという。ここが不思議なところだが、温暖化が寒気の総量を抑制する方向に働いているということの現われかもしれない。このあたりは議論がいろいろありそうだが。
ちなみに、冬季雷の多発は日本海側に設置する風力発電の風車にとって天敵である。風車本体や羽への落雷によって破損や機能低下が生じるため、これを回避する方策の研究が進められており、風力エネルギーシンポジウムで冬季雷の研究発表が行われたのはその一環である。
「冬の稲妻」といえばアリスの名曲だ。しかし、谷村、堀内の二人とも大阪人だったはずで、冬季雷のイメージはどこから拾ったのか。城之崎温泉でズワイ蟹を食べたときに遠くで雷が鳴っていたのだろうか。そういえばズワイのうまい季節だ、いまは。
風力エネルギーシンポジウム(11月24日)で、冬の雷について興味深い発表があった。発表した高田氏によれば、日本海側の冬雷がこのところ増加を続けているが、地球温暖化がその原因ではないかという研究である。
金沢の雷日数は、1930年代から50年代にかけて年間20日ほどで推移したが、60年代から増加を始め、2000年代に入ると毎年40日以上に倍加。しかもその増分のほとんどは冬季雷によるもの。中でも豪雪となった2005年12月には、その一ヶ月間で18日の雷日数を記録している。これでは、いつもゴロゴロと空が鳴っているような穏やかならぬ状況だ。
北陸の城下町金沢で少年時代を過ごした(8年間)者としては、この冬季雷の話しは気になる。北陸の暗い空の下で、昼も夜もなく遠く地響きのように長くとどろく雷鳴。記憶の深い底にひっそりと刻まれたままだ。でも東京の人間に冬の雷の話をしてもまったく通じない、雷というのは夏の季語なのだ、ここでは。
しかし、ちょっとまてよ。温暖化は暖冬につながり、暖冬なら少雪になる、とすると雷も少なくなるのではないか?現象が逆じゃないか?
こうした疑念に高田氏は次のような説明をしている。まず、冬季雷はなぜ生じるのか。寒気がどんどん大陸に溜まり、これが吐き出されるように日本を襲うだけでは雷にはならない。寒気が日本へ到達する際に、越えていく日本海が十分に暖かいときにだけ雲が発達し、雷雲を生じる。日本海の水温も気温に引きずられて冬には低下するのだが、大気の変化のほうがどうしても早くなる。この差が3ヶ月近くになる(水の比熱が大きいから)ため、大気は本番並みに寒いのに海がとんでもなく暖かい(相対的に)という現象が生じることになる。
高田氏によれば、冬季雷の引き金となる大気と海水温の差は10℃。これまでの観測ではこの差が15℃を越えているときに雷が頻発しているという。メカニズムとしては、海水と大気の温度差が拡大することによって海表面からの蒸発が一層促進され、大陸を出たときにはカラカラに乾いていた寒気が、日本海を越えている間にたっぷり湿気を含み連続的な雪雲を形成するものと考えられる。
ここまで説明されると、温暖化が日本海を徐々に暖め、その水温が上昇することによって寒気と海水表面の温度差が拡大し、雷雲を激しく成長させるから冬の雷の頻度が高くなる、ということがなんとなく理解できる。その一方で、高田氏によれば、冬季雷の発生は徐々に増加しているが、降雪量は増加しているとは言えないという。ここが不思議なところだが、温暖化が寒気の総量を抑制する方向に働いているということの現われかもしれない。このあたりは議論がいろいろありそうだが。
ちなみに、冬季雷の多発は日本海側に設置する風力発電の風車にとって天敵である。風車本体や羽への落雷によって破損や機能低下が生じるため、これを回避する方策の研究が進められており、風力エネルギーシンポジウムで冬季雷の研究発表が行われたのはその一環である。
「冬の稲妻」といえばアリスの名曲だ。しかし、谷村、堀内の二人とも大阪人だったはずで、冬季雷のイメージはどこから拾ったのか。城之崎温泉でズワイ蟹を食べたときに遠くで雷が鳴っていたのだろうか。そういえばズワイのうまい季節だ、いまは。
地球は ありがたい 星 [講演を聞いて]
北の丸の科学技術館で開催された宙博(そらはく)2010、今回のテーマは「宙(そら)から始まる環境エネルギー革命」。その最終日10月31日に催されたLiveStageでの竹村真一氏:京都造形芸術大学教授の講演を聴いた。会場に足を運んだ小学生を中心とした子供たちとその親に向けた竹村氏のメッセージ。以下にその要約を紹介するが、さらに深い内容については氏の著作である「地球の目線」PHP新書をお薦めしたい。
ありがたい:有難いの本意は、存在がありそうもなく珍しいこと、これが転じて、優れているとか、またとなく尊いとなり、さらに身にしみてうれしい、本当にうれしいという意味で使われるようになった。人類を含む極めて多様な生物の存在を可能にした星「地球」は、まさに極めて稀なる条件の下で生まれた文字通り「ありがたい」星。酸素と水素が結びついた「水」がほぼ液体の形で存在しているのは太陽系では地球だけであり、おそらく宇宙全体でもかなり稀な存在だといえる。アル・ゴアの「不都合な真実」が示すように、かけがえのない地球という惑星を痛め続ける人間の行為に焦点をあてることで、逆説的にではあるが、まさにありがたい「好都合な真実」をはっきりと認識するようになった。
しかし、これだけグローバルな時代になっていながら、地球上で起きている様々なことがらを、実は何も知らないともいえる。東京で起きていること、北京で起きていることの断片は知っていても、それらが地球という星の上でどんなつながりを形成しているかを知らない。インターネットの発達が情報共有という利便性をこれだけ全世界に広げ続けているのに、地球全体のありのままの姿を知る努力、伝える努力はほとんどなされていない。グローバル化が経済を中心に進行しているのに、情報をグローバルに把握する環境がほとんど追いついていないために、いま起きていることを本当は良く知らないままでいる。みんなが地球のことをもっとよく知ろう。そうした思いからデジタル地球儀「触れる地球」を作った。これが日本中のそして世界中の小学校に置かれるようになれば、誰もが地球という星のありがたさを直感できるようになるはず。
例えば、全地球の酸素の4分の1を生み出している母なるアマゾンの森林が、耕作地の拡大のために毎年2万6千平方キロづつ失われている事実などもメディア活動が後手に回っているために、ニュースとして目の前を通り過ぎることはあっても大事な事実として認識されてはいないのではないか。地球の未来を託すべき子供たちにも伝えられていない。それどころか、日本の子供たちは生まれたときから、環境破壊と温暖化で地球はあぶない、未来はないかもしれないとネガティブなイメージを与えられ続けている。人間は地球にとってガンのような存在と映っているのではないか。
日本は雨が多く地形が急峻であり、そのままで何も手をつけずに豊かな自然の恵みを受けていたわけではない。我々の祖先は、里山や水田を作ることでゆるやかな環境を生み出すという努力をずっと継続してきた。緩和帯を設けることで自然の荒々しさを抑えることができてきた。手つかずの自然が常によいというわけではない。人間は地球のガンでは決してない。
人類が世界中で費やしているエネルギーの総量は石油換算で約100億トン。この1万倍のエネルギーが太陽光として地上に注いでいる。自然エネルギーである風力も太陽光もバイオマスですらその源は太陽からのエネルギーである。こうした自然エネルギーの利用が進んでも高々1%だとされていたのは既に過去のことで、欧州では自然エネルギーが全体の数分の一を占める国が現れており、その勢いがさらに増している。地球のことをもっともっとよく知ること。深い理解から目指すべき地球の姿が見えてくる。
ありがたい:有難いの本意は、存在がありそうもなく珍しいこと、これが転じて、優れているとか、またとなく尊いとなり、さらに身にしみてうれしい、本当にうれしいという意味で使われるようになった。人類を含む極めて多様な生物の存在を可能にした星「地球」は、まさに極めて稀なる条件の下で生まれた文字通り「ありがたい」星。酸素と水素が結びついた「水」がほぼ液体の形で存在しているのは太陽系では地球だけであり、おそらく宇宙全体でもかなり稀な存在だといえる。アル・ゴアの「不都合な真実」が示すように、かけがえのない地球という惑星を痛め続ける人間の行為に焦点をあてることで、逆説的にではあるが、まさにありがたい「好都合な真実」をはっきりと認識するようになった。
しかし、これだけグローバルな時代になっていながら、地球上で起きている様々なことがらを、実は何も知らないともいえる。東京で起きていること、北京で起きていることの断片は知っていても、それらが地球という星の上でどんなつながりを形成しているかを知らない。インターネットの発達が情報共有という利便性をこれだけ全世界に広げ続けているのに、地球全体のありのままの姿を知る努力、伝える努力はほとんどなされていない。グローバル化が経済を中心に進行しているのに、情報をグローバルに把握する環境がほとんど追いついていないために、いま起きていることを本当は良く知らないままでいる。みんなが地球のことをもっとよく知ろう。そうした思いからデジタル地球儀「触れる地球」を作った。これが日本中のそして世界中の小学校に置かれるようになれば、誰もが地球という星のありがたさを直感できるようになるはず。
例えば、全地球の酸素の4分の1を生み出している母なるアマゾンの森林が、耕作地の拡大のために毎年2万6千平方キロづつ失われている事実などもメディア活動が後手に回っているために、ニュースとして目の前を通り過ぎることはあっても大事な事実として認識されてはいないのではないか。地球の未来を託すべき子供たちにも伝えられていない。それどころか、日本の子供たちは生まれたときから、環境破壊と温暖化で地球はあぶない、未来はないかもしれないとネガティブなイメージを与えられ続けている。人間は地球にとってガンのような存在と映っているのではないか。
日本は雨が多く地形が急峻であり、そのままで何も手をつけずに豊かな自然の恵みを受けていたわけではない。我々の祖先は、里山や水田を作ることでゆるやかな環境を生み出すという努力をずっと継続してきた。緩和帯を設けることで自然の荒々しさを抑えることができてきた。手つかずの自然が常によいというわけではない。人間は地球のガンでは決してない。
人類が世界中で費やしているエネルギーの総量は石油換算で約100億トン。この1万倍のエネルギーが太陽光として地上に注いでいる。自然エネルギーである風力も太陽光もバイオマスですらその源は太陽からのエネルギーである。こうした自然エネルギーの利用が進んでも高々1%だとされていたのは既に過去のことで、欧州では自然エネルギーが全体の数分の一を占める国が現れており、その勢いがさらに増している。地球のことをもっともっとよく知ること。深い理解から目指すべき地球の姿が見えてくる。
地球は ありがたい 星
もっと 地球から宇宙を見よう!
もっと 宇宙から地球を見よう!
そして 未来をデザインしよう!



