ミュージシャンの反対運動 [新聞記事]
シェールガス革命によって米国はエネルギー問題から解放された。こうした見方が主流になってきたのは、ほんのこの何年かのこと。天然ガスの埋蔵量の大半はロシアや中東の一部に限られており、石油と同じような地勢リスクを米国は抱え続けていたのだが、大深度ボーリング技術の開発と頁岩層に化学薬物を含む大量の水を注入することで新しいエネルギー源を手に入れる目処が立ったのだ。
“ニューヨーク州デラウェア郡の北部、キャッツキル山地の麓の小さな丘の間をオーレアウト川が緩やかに流れサスケハナ川に注いでいるところ、私が生まれる前に両親が購入した農場がそこにある。”
という書き出しで始まるこのニューヨークタイムズ紙の論説に投稿したのは音楽家のショーン・レノン。すなわち両親というのは、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのことである。
「天然ガスによる貴重な土地の破壊」という題が示すとおり、環境破壊に対する警告が主たる内容だが、ショーンはこの論説の発表と期を合わせて、Artists Against Frackingというシェールガス採掘反対運動を母親のオノ・ヨーコと共に主催し、今後活動を拡大することを発表している。
ショーンにとって、少年時代に最も大きな影響を受けた(ジョン・レノンは彼が5歳の時に亡くなっている)場所であるその農場を含む地域で、数ヶ月前唐突にガス会社による開発計画の説明会が開かれた。それは、シェールガス採掘のため、手つかずの自然を切り裂いてパイプラインを張り巡らせるという計画である。説明会に参加した住民(多くが有機農業に従事)は、強烈に反発姿勢を見せたが、ガス会社はそうした反応には気にもかけぬふりで、(反応がどうであれ)この小さな町で掘削開発を推進するという意図を見せつけた。
この説明会の後、ショーンはシェールガス採掘で深刻な汚染が生じたペンシルバニアの現状を自ら調べて、開発計画の中止を訴えるべきと考えるに至ったという。ショーンによれば、”天然ガスはクリーンなエネルギーとして売られているが、地中の頁岩層を大量の汚染水で破砕する手法を採っており、むしろダーティなエネルギーと呼ぶべきである。有毒な化学物質を大気と地下水にばらまくことになる”、という。さらにショーンは、ニューヨークの近辺は、きわめて清浄な地下水に恵まれており、ニューヨーク市民は世界一うまい水を享受できるのだが、これも地下水の汚染によって喪われると指摘している。
ショーンはさらに、ニューヨークのブルームバーグ市長の、“ガスの開発計画は、ガスの汲み上げは適切な場所を選定し、その作業は慎重に行われることを確認している”、という型どおりの発言にも、“ニコチンの少ないタバコを、適切な場所で適切な時間に吸えば、喫煙も安全だ“と言うのと変わらないと噛みついており、行政や政治にはまかせておけないという思いが運動をスタートさせたと述べている。
ショーンの批判のすべてが正しいかどうかは判断の難しいところだが、影響力のあるアーティストが何かに感ずるところがあれば忽ちに活動を立ち上げ、共鳴する仲間を募って世に問うていくという行動力は、高く評価すべきだと思う。このニュースが日本ではあまり積極的には取り上げられていない(朝日新聞のみ?)のは、芸術家の活動に対する社会の受け取り方の違いからくるのだろうか。あるいは、動機があまりに情緒的だと決めつけられているのだろうか。
それにしても、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの話を持ち出されると思わず身を乗り出してしまうのは、これも小生の年齢のなせるわざか。ちなみに、オノ・ヨーコは79歳だそうだ。
“ニューヨーク州デラウェア郡の北部、キャッツキル山地の麓の小さな丘の間をオーレアウト川が緩やかに流れサスケハナ川に注いでいるところ、私が生まれる前に両親が購入した農場がそこにある。”
という書き出しで始まるこのニューヨークタイムズ紙の論説に投稿したのは音楽家のショーン・レノン。すなわち両親というのは、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのことである。
「天然ガスによる貴重な土地の破壊」という題が示すとおり、環境破壊に対する警告が主たる内容だが、ショーンはこの論説の発表と期を合わせて、Artists Against Frackingというシェールガス採掘反対運動を母親のオノ・ヨーコと共に主催し、今後活動を拡大することを発表している。
ショーンにとって、少年時代に最も大きな影響を受けた(ジョン・レノンは彼が5歳の時に亡くなっている)場所であるその農場を含む地域で、数ヶ月前唐突にガス会社による開発計画の説明会が開かれた。それは、シェールガス採掘のため、手つかずの自然を切り裂いてパイプラインを張り巡らせるという計画である。説明会に参加した住民(多くが有機農業に従事)は、強烈に反発姿勢を見せたが、ガス会社はそうした反応には気にもかけぬふりで、(反応がどうであれ)この小さな町で掘削開発を推進するという意図を見せつけた。
この説明会の後、ショーンはシェールガス採掘で深刻な汚染が生じたペンシルバニアの現状を自ら調べて、開発計画の中止を訴えるべきと考えるに至ったという。ショーンによれば、”天然ガスはクリーンなエネルギーとして売られているが、地中の頁岩層を大量の汚染水で破砕する手法を採っており、むしろダーティなエネルギーと呼ぶべきである。有毒な化学物質を大気と地下水にばらまくことになる”、という。さらにショーンは、ニューヨークの近辺は、きわめて清浄な地下水に恵まれており、ニューヨーク市民は世界一うまい水を享受できるのだが、これも地下水の汚染によって喪われると指摘している。
ショーンはさらに、ニューヨークのブルームバーグ市長の、“ガスの開発計画は、ガスの汲み上げは適切な場所を選定し、その作業は慎重に行われることを確認している”、という型どおりの発言にも、“ニコチンの少ないタバコを、適切な場所で適切な時間に吸えば、喫煙も安全だ“と言うのと変わらないと噛みついており、行政や政治にはまかせておけないという思いが運動をスタートさせたと述べている。
ショーンの批判のすべてが正しいかどうかは判断の難しいところだが、影響力のあるアーティストが何かに感ずるところがあれば忽ちに活動を立ち上げ、共鳴する仲間を募って世に問うていくという行動力は、高く評価すべきだと思う。このニュースが日本ではあまり積極的には取り上げられていない(朝日新聞のみ?)のは、芸術家の活動に対する社会の受け取り方の違いからくるのだろうか。あるいは、動機があまりに情緒的だと決めつけられているのだろうか。
それにしても、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの話を持ち出されると思わず身を乗り出してしまうのは、これも小生の年齢のなせるわざか。ちなみに、オノ・ヨーコは79歳だそうだ。
「お迎え」の意味とは [雑誌記事]
“死ぬ間際に目にする風景” 三浦麻子:AERA編集部、AERA 2012.8.27より
仙台の南にある名取市、そこにある在宅緩和ケア専門の医院である岡部医院の院長、岡部健氏がこの記事の中心である。岡部氏は、元は呼吸器外科医、「自宅で最後を迎えたい」という患者の希望に応えるべく、1997年に自ら医院を開いた。多くの往診などの中で、死を間近にした患者が「お迎え」について口にするのをたびたび耳にするようになり、これを単なる幻覚の類として排除するのではなく、人間が自然に死を迎えるときに、実は「お迎え」が大きな役割を果たしているのではと考えるようになったという。
岡部氏は、看護師などの病院のスタッフ、東北大の研究者などの協力を得て、過去10年以上、遺族らにアンケートをとり、「お迎え」現象の解明につとめてきた。2011年の調査では国の補助金も受け、宮城、福島の6診療所の協力で、遺族1191件にアンケートを送付。575件で回答を得ている。この調査では、「お迎え」体験を「終末期患者が死に臨んで、すでに亡くなっている人物や通常見ることのできない事物を見る類の経験」と規定している。「お迎え」体験があったと遺族が答えたのは約4割。この数字は大きすぎるのではないかと疑うほどなのだが、本人の病状が重く家族に伝えられなかったケースもあるので実際にはもっと多いのではないかともみられているという。本当かどうかを確かめる術はないのだが、半数の人に「お迎え」が見えるとは...
アンケートによれば、「お迎え」に最も多く登場するのは、家族など縁深い人物で、既に亡くなった人。この真意は亡くなった本人にしかわからないが、半数の遺族には、「お迎えが」来て安らかになったように見えたという。調査にあたった社会学者の相澤出氏も、現象を恐れたり怪しんだりせず、「亡くなっていく過程の自然現象として受け入れていいのでは」と語っており、「お迎え」が見えた場合に医師が認識の調査をすると、意識の清明な(混濁していない)場合も多いという。
岡部医院で働く成田憲史さんは、最初は「お迎え」なんて信じられなかったが、「お迎え」を見ている患者をたびたび目にするうちに考えが変わったという。
“すぐそばを指さして『ほら、そこにいるでしょう』と患者さんが言うのを初めて聞いたときには、本当に驚きました。私には何も見えませんでしたから。そういうことが度重なるうちに、患者さんには見えているのだろう、と受け入れるようになりました”
末期にある患者の心が何に開かれているか、あるいはそのことが末期医療にどのように織り込まれていくべきなのか。「お迎え」が投げかける課題は静かに深い。
さて、ここまでの内容の記事であれば、緩和医療の視点から見た「お迎え」の意味の発見といったことなのだが、この記事の真髄は実はこの後にある岡部医師へのロングインタビューにある。
在宅緩和医療の第一人者で、十数年にわたり「お迎え」の調査に取り組んできた岡部氏は、いま自らががんを患い、自宅で在宅緩和ケアを受けている。東日本大震災後は被災地の支援にも取り組んだが、今年に入り容態が悪化した。その中での「あの世」と「お迎え」についてのインタビュー。大変に鮮烈な内容で心を撃つ。その一部をここで紹介したい。
“昭和20年代は、ほとんどの病人が自宅で亡くなっていました。家族は死んでいく人をみとるのが当たり前でした。病院で死ぬ人と自宅で死ぬ人の割合が逆転したのは1976年。今では病院が8割を占めます。本来、病院は病気を治す「医療」を受けるところ。もう治療する手段がないとなったら、自宅に帰って最期を迎えるべきです。「死」は自然現象なのですから。米国など外国では病院で死ぬのは半数以下。日本でも、患者本人は、本当は自宅で死にたいというケースが少なくありません。 なぜ、自宅で死ねないのか。ひとつは、みとる家族が、肉親の死を避けようとしている。見ているのがつらいという。だが、祖先たちはそのつらさを乗り越え、死を受け止めてきました。逃げ出してはいけない。死んでいく肉親をみとることは、いずれ来る自分の死を受け止めることにもなるのです。” 中略 “もう治療ができないのであれば、今まで生きてきた自分の歴史に包まれた自宅に帰り、普通に飯を食い、糞をし、寝る。だんだん食べられなくなり、「ぼちぼちかいね」と思っていると。お迎えが来て、この世からあの世へ行く。それなら死は怖くない。”
仙台の南にある名取市、そこにある在宅緩和ケア専門の医院である岡部医院の院長、岡部健氏がこの記事の中心である。岡部氏は、元は呼吸器外科医、「自宅で最後を迎えたい」という患者の希望に応えるべく、1997年に自ら医院を開いた。多くの往診などの中で、死を間近にした患者が「お迎え」について口にするのをたびたび耳にするようになり、これを単なる幻覚の類として排除するのではなく、人間が自然に死を迎えるときに、実は「お迎え」が大きな役割を果たしているのではと考えるようになったという。
岡部氏は、看護師などの病院のスタッフ、東北大の研究者などの協力を得て、過去10年以上、遺族らにアンケートをとり、「お迎え」現象の解明につとめてきた。2011年の調査では国の補助金も受け、宮城、福島の6診療所の協力で、遺族1191件にアンケートを送付。575件で回答を得ている。この調査では、「お迎え」体験を「終末期患者が死に臨んで、すでに亡くなっている人物や通常見ることのできない事物を見る類の経験」と規定している。「お迎え」体験があったと遺族が答えたのは約4割。この数字は大きすぎるのではないかと疑うほどなのだが、本人の病状が重く家族に伝えられなかったケースもあるので実際にはもっと多いのではないかともみられているという。本当かどうかを確かめる術はないのだが、半数の人に「お迎え」が見えるとは...
アンケートによれば、「お迎え」に最も多く登場するのは、家族など縁深い人物で、既に亡くなった人。この真意は亡くなった本人にしかわからないが、半数の遺族には、「お迎えが」来て安らかになったように見えたという。調査にあたった社会学者の相澤出氏も、現象を恐れたり怪しんだりせず、「亡くなっていく過程の自然現象として受け入れていいのでは」と語っており、「お迎え」が見えた場合に医師が認識の調査をすると、意識の清明な(混濁していない)場合も多いという。
岡部医院で働く成田憲史さんは、最初は「お迎え」なんて信じられなかったが、「お迎え」を見ている患者をたびたび目にするうちに考えが変わったという。
“すぐそばを指さして『ほら、そこにいるでしょう』と患者さんが言うのを初めて聞いたときには、本当に驚きました。私には何も見えませんでしたから。そういうことが度重なるうちに、患者さんには見えているのだろう、と受け入れるようになりました”
末期にある患者の心が何に開かれているか、あるいはそのことが末期医療にどのように織り込まれていくべきなのか。「お迎え」が投げかける課題は静かに深い。
さて、ここまでの内容の記事であれば、緩和医療の視点から見た「お迎え」の意味の発見といったことなのだが、この記事の真髄は実はこの後にある岡部医師へのロングインタビューにある。
在宅緩和医療の第一人者で、十数年にわたり「お迎え」の調査に取り組んできた岡部氏は、いま自らががんを患い、自宅で在宅緩和ケアを受けている。東日本大震災後は被災地の支援にも取り組んだが、今年に入り容態が悪化した。その中での「あの世」と「お迎え」についてのインタビュー。大変に鮮烈な内容で心を撃つ。その一部をここで紹介したい。
“昭和20年代は、ほとんどの病人が自宅で亡くなっていました。家族は死んでいく人をみとるのが当たり前でした。病院で死ぬ人と自宅で死ぬ人の割合が逆転したのは1976年。今では病院が8割を占めます。本来、病院は病気を治す「医療」を受けるところ。もう治療する手段がないとなったら、自宅に帰って最期を迎えるべきです。「死」は自然現象なのですから。米国など外国では病院で死ぬのは半数以下。日本でも、患者本人は、本当は自宅で死にたいというケースが少なくありません。 なぜ、自宅で死ねないのか。ひとつは、みとる家族が、肉親の死を避けようとしている。見ているのがつらいという。だが、祖先たちはそのつらさを乗り越え、死を受け止めてきました。逃げ出してはいけない。死んでいく肉親をみとることは、いずれ来る自分の死を受け止めることにもなるのです。” 中略 “もう治療ができないのであれば、今まで生きてきた自分の歴史に包まれた自宅に帰り、普通に飯を食い、糞をし、寝る。だんだん食べられなくなり、「ぼちぼちかいね」と思っていると。お迎えが来て、この世からあの世へ行く。それなら死は怖くない。”
伊達政宗の運河開削 [新聞記事]
 仙台平野の南端、阿武隈川の河口から海岸線に沿うように北へ向かって走る一本の水路がある。これは「貞山堀」と呼ばれている運河で、はるか50キロ先の石巻まで続いている。
仙台平野の南端、阿武隈川の河口から海岸線に沿うように北へ向かって走る一本の水路がある。これは「貞山堀」と呼ばれている運河で、はるか50キロ先の石巻まで続いている。作家で仙台出身の佐伯一麦氏が、日本経済新聞の夕刊コラム:あすへの話題で2回(2012年7月28日、8月4日)にわたって、この貞山堀のことを取り上げているので紹介したい。
「仙台で生まれ育った私には、海岸へと出る前には、小さな水路を渡るものだという感覚がある。水泳部だった高校生の頃、水泳大会で東北各地の海辺の町を訪れるようになり、競技が終わると、現地の海で泳ぐのが楽しみだった。そのときに、何の前触れもなしに突然海があらわれると、違和感を覚えることがあった。-中略- 私が、海の前には必ず存在しているもののように慣れ親しんできたのが、仙台平野の海岸線と並行して流れている日本最長の運河、貞山運河である。」
400年前に、伊達正宗が命じて開削した水路を正宗の諡(おくりな)である貞山にちなんで貞山堀と呼んだのは、明治の土木技師で後に仙台市長を務めた早川智寛だそうだが、この長大な水路は、成立の歴史などから次のように幾つかの堀に区分される。
木曳堀:阿武隈川河口から名取川河口閖上
新堀:閖上から七北田川河口蒲生
舟入堀:蒲生から塩釜市牛生(ぎゅう)
東名運河:牛生から松島湾経由で東名(とうな)から鳴瀬川河口野蒜
北上運河:野蒜から石巻
これらのうち、最初に着手されたのが木曳堀で慶長年間後半とされている、これに少し遅れて舟入堀の開削が続いたようだ。ここには戦国時代の終焉と伊達正宗の仙台築城が深く関わっている。
関ヶ原の戦いの後、慶長6年(1601年)に、政宗は居城をそれまでの岩出山から仙台へ移し、併せて城下町の整備・構築を急いだ。そのために、必要な物資、特に建築資材(木材)を南から大量にしかも急速に運ぶ必要に迫られていた。比較的平坦な仙台平野ではあるが、大規模な土木・建築工事の資材を運ぶには陸路より水路という選択になったのだろう。最も急ぐべきは、福島と仙台の連結、したがって阿武隈川と名取川を海岸沿いの水路による最短ルートで結ぶのが、時間的にも経済的にも最善策と判断したのだ。運河の活用というと、商都大阪や江戸を思い浮かべがちだが、東北の地にも大胆な発想があり、しっかりと実現されていたのだ。
この木曳堀の開削を指揮したのは、政宗がこの工事のために毛利家からスカウトしてきた川村孫兵衛重吉である。
「政宗から五百石で召し抱えると言われたときに、重吉は、それなら領内の荒地を賜りたいと答えた。それで与えられたのが、現在の岩沼市の阿武隈川河口に近い土地で、湿地だった荒地の溜まり水を阿武隈川へと排水することで広大な田畑を作ろうとした。その排水路が木曳堀であり、同じ時期に徳川家康より進上築城を許可された政宗が、仙台に城を築き、城下町を作るのに必要な木材の運搬にも役立つこととなった。」
使い道のない沖積平野の湿地に手を加え、耕地や居住地商業地として開発し、同時に運輸手段としての水路も確保するという、近代的な土地利用のさきがけが、江戸や大坂ではない東北の仙台平野にもあったということ。しかも、貞山堀がその歴史証拠だというのだが、これはぜひ仙台の誇るべき歴史の一つとして地元の教育カリキュラムに乗せてほしいものだ。
そして、佐伯氏はこうした運河開発譚に加えて、もうひとつの重要な事実に気づいたと記している。それは、木曳堀完成の前に慶長三陸津波(1611年)に襲われていたということである。津波によって、水路も被災したであろうが、なにより侵入した海水の排水に堀が機能したはずであり、さらには水路や周辺地の本格改修は江戸時代の震災復興でもあったのだろうと述べている。
実は小生の高校時代に、この貞山堀を競技用の四人漕ぎ艇(ボート)で毎週のように行き来していた。時には遠漕と称して松島を越え、野蒜まで足(?)を伸ばしたりしていたのだが、そこにまさか政宗の深い知略が埋まっていようとは露も知らなかった。
隊列から離れるという挑戦 [講演を聞いて]
第一回日経スマートシティシンポジウム、2012年7月23,24日於東工大蔵前会館を聴いて
パネルディスカッション「環境未来都市、スマートコミュニティの実現に向けた北九州市の挑戦」より
北九州市は環境未来都市に選ばれ、エネルギーの新しい形を自治体として模索し続けている。最近では、実証実験として、電力料金にダイナミックプライシングを導入するなどきわめて先駆的な挑戦をしており(例えば、北九州スマートコミュニティ創造事業など)、この領域ではまちがいなくわが国の先進的役割を果たし続けてきている。今回のシンポジウムでは、特にこの北九州市の挑戦的な活動にスポットをあて、さらに今後の課題を見い出そうというとのが議論のねらいであった。
その議論や事例の内容についてはメディアの記事に譲りたい(例えば日経BPクリーンテックの記事など)。ここではパネルの最初に行われた話題提供で北九州市の松岡俊和氏:環境未来都市担当理事の話が印象に強く残ったので、ここに紹介しておきたい。ただし、録音をとらず会場での簡単なメモと記憶によっているため、言葉の使い方などについては実際と異なっていることがあることはご容赦いただきたい。
北九州は、産業都市としての急速な発展とその負の遺産としての公害を両手に抱え、戦後の経済成長路線の先頭を走り続けてきた。いつしか公害と戦いこれを制することが、この街に暮らす人にとって最も大事なことがらとなっていった。全国的にもまだ事例が少ない中で、自らの身を切り、血を流して取り組んできた。公害という当時の課題を克服したことは街に暮らす人の大きな自信でもあった。そうした街が環境・エネルギーへの新しい取り組みに再び立ち上がることになった。
2008年に国の環境モデル都市に選定されたことが節目となった。21世紀の抱える環境とエネルギーの課題は限りある資源と成長のバランスをどうとっていくかということに尽きる。そうした基本となる理念はよく理解できるのだが、さて、モデルの街に選ばれてみて愕然としたという。アイデアがなにも沸いてこない。国から示された美しいメニューは目には入るのだが、さて北九州でなにをやればよいのか、さっぱり浮かんでこない。
戦後の産業成長と公害を乗り越えてきた経験の深い街なのだから、なにもないはずはないのだが。新しい時代の環境と言われたとたんにやるべきことが思いつかないとは。これは正直、かなりショックだったという。要するに、自分たちの街を遠い将来まで含めて、どんな街にしていくのかという一番大切な命題について、実は真剣に考えてはいなかったのではないか。
新しい課題はこれだよと、お上が示してくれたものを眺めてから思考を逆に回転させることがあたりまえになっていた。これを一言で(自分たちは)「自立していなかった」と松岡氏は厳しく断じている。自らの頭で徹底的に考え抜く、与えられたメニューからお気に入りの素材と料理を選んで事たれりとするような甘えた、ぬるい環境に安穏としていただけではないか、と。
このとき初めて、自分たちの自治体運営が「自治」ではなかったと気づいたと。自分たちの街の将来への設計図を描くことこそが自治そのものであり、行政の仕事なのだと気づいた。その土地の文化や歴史に合った街の姿を描くことは、その土地に根ざした行政官にしかできないのだということを。そして同時に、これができていない自治体が多いということも明らかになったという。
この松岡氏の指摘は、行政の中で挑戦を続けている人の発言だけにきわめて重いものがある。街や大きく考えれば国がどの方向に向かうのかという、市民国民にとってもっとも重要なテーマについて、私たちはいったいどれだけ真剣に向き合い、そして考えてきただろうか。あるいはものごとの本質を突き詰めて考えるといった習慣、くせを、親や先達からしっかり引き継いできただろうか。誰かが描いてくれた美しい絵と言葉に共感し、納得した瞬間に思考を止める。議論はもうこれでおしまいにしよう、考えている暇があったら動け、と。
大事なことは夢そのものではなく、それをどうやって実現するかだ。だから、まず手を動かせ、歩き回れ、汗をかいてはじめて前に進むことができる。こうやってわれわれ日本人はずっと突き進んできたのではないだろうか。明治維新、日露戦争、太平洋戦争、そして3.11。これ以上思考を止めたまま歩き続けてはいけない。
考え続けることによって、問題の本質が解きほぐされ、場合によっては方針の修正や路線の変更さえもあってもおかしくはないはずだが、そういうアプローチは良くない、隊列を乱すなと厳しく叩き込まれてきたように思う、よく考えれば子供のころからそうだった。おい、そこのおまえだ、うろうろせず隊列から離れるな、足並みを揃えろと。
パネルディスカッション「環境未来都市、スマートコミュニティの実現に向けた北九州市の挑戦」より
北九州市は環境未来都市に選ばれ、エネルギーの新しい形を自治体として模索し続けている。最近では、実証実験として、電力料金にダイナミックプライシングを導入するなどきわめて先駆的な挑戦をしており(例えば、北九州スマートコミュニティ創造事業など)、この領域ではまちがいなくわが国の先進的役割を果たし続けてきている。今回のシンポジウムでは、特にこの北九州市の挑戦的な活動にスポットをあて、さらに今後の課題を見い出そうというとのが議論のねらいであった。
その議論や事例の内容についてはメディアの記事に譲りたい(例えば日経BPクリーンテックの記事など)。ここではパネルの最初に行われた話題提供で北九州市の松岡俊和氏:環境未来都市担当理事の話が印象に強く残ったので、ここに紹介しておきたい。ただし、録音をとらず会場での簡単なメモと記憶によっているため、言葉の使い方などについては実際と異なっていることがあることはご容赦いただきたい。
北九州は、産業都市としての急速な発展とその負の遺産としての公害を両手に抱え、戦後の経済成長路線の先頭を走り続けてきた。いつしか公害と戦いこれを制することが、この街に暮らす人にとって最も大事なことがらとなっていった。全国的にもまだ事例が少ない中で、自らの身を切り、血を流して取り組んできた。公害という当時の課題を克服したことは街に暮らす人の大きな自信でもあった。そうした街が環境・エネルギーへの新しい取り組みに再び立ち上がることになった。
2008年に国の環境モデル都市に選定されたことが節目となった。21世紀の抱える環境とエネルギーの課題は限りある資源と成長のバランスをどうとっていくかということに尽きる。そうした基本となる理念はよく理解できるのだが、さて、モデルの街に選ばれてみて愕然としたという。アイデアがなにも沸いてこない。国から示された美しいメニューは目には入るのだが、さて北九州でなにをやればよいのか、さっぱり浮かんでこない。
戦後の産業成長と公害を乗り越えてきた経験の深い街なのだから、なにもないはずはないのだが。新しい時代の環境と言われたとたんにやるべきことが思いつかないとは。これは正直、かなりショックだったという。要するに、自分たちの街を遠い将来まで含めて、どんな街にしていくのかという一番大切な命題について、実は真剣に考えてはいなかったのではないか。
新しい課題はこれだよと、お上が示してくれたものを眺めてから思考を逆に回転させることがあたりまえになっていた。これを一言で(自分たちは)「自立していなかった」と松岡氏は厳しく断じている。自らの頭で徹底的に考え抜く、与えられたメニューからお気に入りの素材と料理を選んで事たれりとするような甘えた、ぬるい環境に安穏としていただけではないか、と。
このとき初めて、自分たちの自治体運営が「自治」ではなかったと気づいたと。自分たちの街の将来への設計図を描くことこそが自治そのものであり、行政の仕事なのだと気づいた。その土地の文化や歴史に合った街の姿を描くことは、その土地に根ざした行政官にしかできないのだということを。そして同時に、これができていない自治体が多いということも明らかになったという。
この松岡氏の指摘は、行政の中で挑戦を続けている人の発言だけにきわめて重いものがある。街や大きく考えれば国がどの方向に向かうのかという、市民国民にとってもっとも重要なテーマについて、私たちはいったいどれだけ真剣に向き合い、そして考えてきただろうか。あるいはものごとの本質を突き詰めて考えるといった習慣、くせを、親や先達からしっかり引き継いできただろうか。誰かが描いてくれた美しい絵と言葉に共感し、納得した瞬間に思考を止める。議論はもうこれでおしまいにしよう、考えている暇があったら動け、と。
大事なことは夢そのものではなく、それをどうやって実現するかだ。だから、まず手を動かせ、歩き回れ、汗をかいてはじめて前に進むことができる。こうやってわれわれ日本人はずっと突き進んできたのではないだろうか。明治維新、日露戦争、太平洋戦争、そして3.11。これ以上思考を止めたまま歩き続けてはいけない。
考え続けることによって、問題の本質が解きほぐされ、場合によっては方針の修正や路線の変更さえもあってもおかしくはないはずだが、そういうアプローチは良くない、隊列を乱すなと厳しく叩き込まれてきたように思う、よく考えれば子供のころからそうだった。おい、そこのおまえだ、うろうろせず隊列から離れるな、足並みを揃えろと。
丸子川にはホタルがいない [雑誌記事]
 「ドリトル先生の憂鬱」福岡伸一、AERA 2012.7.16号より
「ドリトル先生の憂鬱」福岡伸一、AERA 2012.7.16号より福岡先生の通勤路に丸子川という細い川があり、毎日そこを通るたびに、もしかして小魚が泳いではいないかと水面を覗き込んでいるのだが、丸子川の浅い流れに魚の黒い背を見つけたことはないそうだ。さらに福岡先生は帰り道に暗くなった川面を、もしかて丸子川にホタルがゆらゆらと飛翔していないかと目を凝らしたりしているらしい。これがむなしい夢であることは先刻ご承知なのだが、この気持ちはたいへんによくわかる。なぜなら、私もこの丸子川の辺を徘徊しており、毎朝、毎夕に川面を覗き込んでいるのだから。
丸子川は、東京の西にある特徴的な段丘地形である国分寺崖線に沿って、成城、岡本、瀬田、上野毛、等々力、尾山台、田園調布と続いており、崖からの湧水や雨水を集めて細いけれども清流を形作っている。東京の小河川のほとんどが蓋を被って暗渠となって人の目から消えていることを思うと、この丸子川の佇まいは大変に貴重だといえる。
ホタルがすむ清流にはいくつもの条件が必要で、なにより湿度を保った草と土に覆われた自然の岸を持っていることが必須だという。ホタルの卵は水辺のミズゴケに産みつけられ、微小なムカデのような姿をした幼虫はカワニナという淡水性の巻き貝しか食べないという。そこにカワニナがいなければ育ちようがないのだ。そうして大きくなった幼虫は、川底で冬を越し、春先に日照時間が長くなると岸辺に上陸し、土を掘ってその中でようやく蛹になる。そのためには自然の土手が必要なのだ。
コンクリートで護岸も川底も固められた都市河川では、こうしたホタルにふさわしい環境条件を与えることはほぼ絶望であろう。それならば、コンクリートを剥がして自然に戻せばよいという意見が出てくるのかもしれないが、大都市のど真ん中を流れる河川では、都市の治水という観点から旧に復することは容易ではない。ホタルは別のところで眺めてくださいということにならざるをえないだろう。実は、丸子川近隣の公園などではホタル成育に取り組んでいるらしいのだが。
福岡先生によれば、ホタルそのものよりさらに微妙で限定的な環境条件が必要なのは、その餌となるカワニナのほうであり、ホタルが発生するといういうことの背景には、生物と生物のあいだの複雑なせめぎあいが隠されており、だからこそ、ホタルの淡い光は、その動的な平衡がかろうじて成立していることの証しなのだという。自然を人間が守ろうとするのは決して簡単なことではないのだと改めて思い知らされる。
やっぱり、丸子川でホタルは飛ばないということか。それでも、丸子川にはサギやカモが餌を探して歩いている姿がけっこう当たり前に見られたりするので、もう少しの環境改善はできるように思えるのだが。これは単なる妄想に過ぎないのだろうか。
ここには津波は来ないと言われていた [講演を聞いて]
 「想定外を生き抜く力」片田敏孝群馬大学教授の講演を聴いて
「想定外を生き抜く力」片田敏孝群馬大学教授の講演を聴いて3.11後の巨大津波から釜石の子供たちを守った片田先生の津波防災教育のことは、前に紹介している。
巨大津波に繰り返し襲われるという宿命の土地でも、災害の恐怖から目を背けることなく、歴史が教える事実を学び、その中で生き残るすべを身に着ける努力を続けた結果が、3.11の巨大津波で確かな成果となって結実した。「奇跡」は幸運などではなく、必然であったということだろうか。
あの巨大津波から1年以上が経過し、3.11の「その時」に起きたことを住民一人ひとりへの聞き込みなどを重ねて精査し、住民の行動分析を加えた結果、津波災害に対する取り組みを考え直すべき点が少なからず明らかになったという。
津波は事前の想定をはるかに超えた巨大なものではあったが、巻き込まれ命を失った人と際どくも逃げ切った人との差はどこにあったのだろう。片田教授は、ハザードマップへの過度な依存がその一つの鍵になったと指摘している。津波のハザードマップは、その地域に将来生じるであろう災害の規模と範囲を過去の実績に基づいて推測し、災害時に選択すべき避難場所や避難手順を予め決めておくことを目的として自治体によって作成される。災害想定は科学的な知見に基づいた数値シミュレーションを用いて行われるのだが、ここに検証の難しい仮定がいくつも積み重ねられているにもかかわらず、そこから導き出された結果は間違いのない「真実」あるいは神の御宣託であるかのように見えてしまう。
岩手県のある湾奥に位置する街では、津波で多くの命が失われたのだが、その平面分布は決して一様ではなかった。被害者が集中していたのは、海に接した地区ではなく、むしろ海から離れた地区であり、ハザードマップ上では津波到達の可能性が低いと示された場所であった。津波が来る可能性が高いと言われていた地区に住む人は、地震のあとすぐに逃げることを試みたが、ここは大丈夫だろうと思っていた地区の人はすぐに逃げようとはしなかったのだという。マップ上の安全と危険の線引きが、皮肉なことに命の線引きになってしまったのだ。
「この場所は津波が来ないと言われていたので逃げなかった」と線引きの外側、つまり安全と色分けされていた場所に住んでいた住民は、災害後の調査で答えている。行政が作成したハザードマップの上で、危険側には入っていなかったという主張だが、結果的にいえばこれは思い込みでしかなかった。このことを片田教授は、防災に対する「主体性の欠落」が招いた事象と断じている。巨大災害に対する防災で最も重要なことは、行政(お上)に依存しない「主体的」姿勢の醸成にあるという。
自分の、家族のかけがえのない大切な命だからこそ、誰かに頼ればよいという他者依存からまず脱却しなければならない。防災の意識を広く普遍的なレベルに高めるための教育に必要なことは、単なる災害知識の詰め込みではなく、自ら主体的に取り組む以外には命は守れないという「姿勢」を重視した教育であるべきだという。
ここは大丈夫という思い込みは、絶えることのない災害の恐怖を和らげる精神安定剤なのかもしれないが、本当の危険への対応力を長い時間をかけて麻痺させていく毒薬でもあるということなのだ。人の心に関わるところだけに、ここを切り開くのは容易ではない。しかしこれこそが、日本の防災の本質なのだと悟るところからしか津波の教訓を生かせないということなのだろう。
胸に蛍を抱いて [雑誌記事]
 「暖簾にひじ鉄:連載第541回、91歳の詩人」内館牧子、週刊朝日 2012.6.29号より
「暖簾にひじ鉄:連載第541回、91歳の詩人」内館牧子、週刊朝日 2012.6.29号より作家の内館牧子氏が、秋田市の「あきた文学資料館」で、たまたま見つけた一冊の詩集。その横に置いてある新聞のコピー見出し「91歳の詩人、坂本梅子さん 老人ホームで創作、9作目出版」に引かれ、立ったまま拾い読みを始めたところ、忽ちに引き込まれ、途中から椅子に座ってさらに読み進んだ。もちろん、それでは足らず、東京に戻るなり出版社に連絡をして買い求めたという。
この詩集の作者坂本梅子さんは、今年の3月13日に101歳で亡くなられていたのだ。60歳過ぎまで秋田の特定郵便局員として働く中で、50歳過ぎから詩作を始めたもの。89歳の頃に田沢湖町に近い西木村(現・仙北市)の特別養護老人ホームに入ってからもその活動が続き、91年には秋田県芸術選奨を受賞するなどした。
詩集『いろはにほへどちりぬるを』は、坂本さんが入られた山奥の老人ホームでの暮らしや思いを描いているのだが、「一人で個室で暮らし、死について孤独について家族について、多くを思う日々であっただろう」と内館氏が指摘するように、同書には激しくも静謐な作品が数多いという。特に、内館氏が「衝撃的」と表現した詩集の最後の一篇を次に紹介したい。
「夜の山と老人」
山はたそがれ
ホームの老人もたそがれて
山は暮れ
ホームの日も暮れて
山は夜のいろ
老人は夜の舟に揺られ
胸に一匹ずつ螢を抱いて
光ったり 消えたり
山は闇に座したまま
光もせず 消えもせず
老人は胸に明滅する神さま
を抱いてねむる
「胸に一匹ずつ蛍を抱いて」いる老人たちの孤独と哀しみが心に染み入るようだ。内館氏によれば、「蛍」とは希望のことで、「きっと明日はホームで楽しいことがあるかもしれないとか、誰かが訪ねてきたり、手紙や電話が来るかもしれないとか、ポッと蛍が光る。だが、そんなことはないだろうなと蛍は消える。いや、あるかもと明滅する。そうやって、闇に溶ける山々と眠る日々」
そして最後に、「この一篇は、百万語を重ねて家族や老人を表現するものを駆逐する。91歳の詩人である」と断言している。
レバーがおいしい理由 [雑誌記事]
「ドリトル先生の憂鬱」福岡伸一,AERA 2012.6.18より
とうとう、牛の生レバーの飲食店での提供が、食品衛生法に基づき来月から禁止ということになった。この規制強化は、昨年夏に生の牛肉の中毒から始まったものだ。食文化の多様性という点で、日本には世界でも最もバラエティに富んだ食材があり、しかも新鮮でかつおいしい。そして、生食に味覚の価値を求めるという世界的にも珍しい国ということになっている。例えば、卵を生で食べるという習慣は、他にほとんどないという。そんなことを疑問にしないほど、清潔で安全な食が一つの極みに達しているということでもあろう。
生のレバーが一番かどうかは、置いておくとしても、レバーを食することを好む人は多い。レバーが生命体にとって代謝の中心臓器で、タンパク質と脂肪がミルフィーユのように折り重なっていると聞いただけでなんとなくおいそうではないか。それにしても、内臓を「おいしい」と感じるのはなぜだろう。そこに福岡先生はこう説明する。
「タンパク質や炭水化物はそのままでは味がしません。分解され始めると味成分が花開いてきます。おそらく進化の過程で、獲物が傷ついて弱っていたり、死にかけて動きが緩慢になっていたりする状態を、そこから漂ってくるアミノ酸や当のにおいを手がかりに探索する術を身につけたからこそ、それを『おいしい』と感じるようになったのでしょう。」
弱っている生き物に特有の「臭い」を嗅ぎ分けることが生存の必須条件だったという話しは、なるほどと頷かざるをえない。死臭が私を呼び寄せる、と言ってしまうとまるでハイエナのようだが、生き続けるため、家族を養うためには栄養分の高い食物を集め続けることが避けては通れない。
もう一つ、福岡先生は、ヒトの肝臓は臓器の中の「家父長」的な存在だという。
「一番最初にお膳に箸をつけるのも、一番風呂に入るのも肝臓の特権です。」
つまり、ヒトが摂取する食物は消化管で消化され栄養素として吸収されるが、それらが血管を通して肝臓の入口に集められ、いわば独り占めになる。肝臓はこうして集めた栄養素を使ってまず熱エネルギーを生み出すので、血液が温められ、これが全身に熱を送ることになる。肝臓は一番風呂に入るというより、風呂は自分が沸かしているのだそうだ。肝臓がちゃんと働かないとヒトは温かくならないということは、熱エネルギー発生装置であるということだ。体内の血流を維持する心臓が一番大事だと考えやすいが、エネルギー転換装置である肝臓の方が、確かにお父さん的だというのはよく理解できる。
福岡先生は、こうしたレバーの話の最後に次のように述べている。
「レバーを食べるのもいいのですが、まずは自分の肝臓をいつくしみたいものです。」
とうとう、牛の生レバーの飲食店での提供が、食品衛生法に基づき来月から禁止ということになった。この規制強化は、昨年夏に生の牛肉の中毒から始まったものだ。食文化の多様性という点で、日本には世界でも最もバラエティに富んだ食材があり、しかも新鮮でかつおいしい。そして、生食に味覚の価値を求めるという世界的にも珍しい国ということになっている。例えば、卵を生で食べるという習慣は、他にほとんどないという。そんなことを疑問にしないほど、清潔で安全な食が一つの極みに達しているということでもあろう。
生のレバーが一番かどうかは、置いておくとしても、レバーを食することを好む人は多い。レバーが生命体にとって代謝の中心臓器で、タンパク質と脂肪がミルフィーユのように折り重なっていると聞いただけでなんとなくおいそうではないか。それにしても、内臓を「おいしい」と感じるのはなぜだろう。そこに福岡先生はこう説明する。
「タンパク質や炭水化物はそのままでは味がしません。分解され始めると味成分が花開いてきます。おそらく進化の過程で、獲物が傷ついて弱っていたり、死にかけて動きが緩慢になっていたりする状態を、そこから漂ってくるアミノ酸や当のにおいを手がかりに探索する術を身につけたからこそ、それを『おいしい』と感じるようになったのでしょう。」
弱っている生き物に特有の「臭い」を嗅ぎ分けることが生存の必須条件だったという話しは、なるほどと頷かざるをえない。死臭が私を呼び寄せる、と言ってしまうとまるでハイエナのようだが、生き続けるため、家族を養うためには栄養分の高い食物を集め続けることが避けては通れない。
もう一つ、福岡先生は、ヒトの肝臓は臓器の中の「家父長」的な存在だという。
「一番最初にお膳に箸をつけるのも、一番風呂に入るのも肝臓の特権です。」
つまり、ヒトが摂取する食物は消化管で消化され栄養素として吸収されるが、それらが血管を通して肝臓の入口に集められ、いわば独り占めになる。肝臓はこうして集めた栄養素を使ってまず熱エネルギーを生み出すので、血液が温められ、これが全身に熱を送ることになる。肝臓は一番風呂に入るというより、風呂は自分が沸かしているのだそうだ。肝臓がちゃんと働かないとヒトは温かくならないということは、熱エネルギー発生装置であるということだ。体内の血流を維持する心臓が一番大事だと考えやすいが、エネルギー転換装置である肝臓の方が、確かにお父さん的だというのはよく理解できる。
福岡先生は、こうしたレバーの話の最後に次のように述べている。
「レバーを食べるのもいいのですが、まずは自分の肝臓をいつくしみたいものです。」
道路に礼を言う人はいない [雑誌記事]
「社会安全哲学の構築に向けて」丹保憲仁北海道立総合研究機構理事長に聞く、土木学会誌 vol.97 no.6 June 2012より
北海道大学総長、放送大学学長などを歴任された丹保氏は、環境工学を専門とする土木界賢人の一人だが、今回の震災における土木屋の社会からの評価という点について興味深い意見を述べられている。
「土木というのは、もともとはメソポタミアやエジプトなどで文明が誕生して人が集まり、灌漑や洪水など水をコントロールしなくてはならなくなり始まった学問です。・・中略・・本来的に土木は中央集権型の技術であり、学問です。・・中略・・大型の仕事を上からやる技術者集団で、下から立ち上がってくるシビルエンジニアというのは、近代になってからのヨーロッパの発想です。・・中略・・黙っていれば上から見てしまいます。それに対する反省は常に現代の土木には必要です。」
この土木に対する指摘は重要だ。国家発展を目的として、社会のインフラを大規模に形成するのは“お上”の仕事だから、下々の者はその内容を知る必要はないという立ち位置が最初にあるという。中央集権で上からの目線をよしとするのは、全体の効率を最も重視するからであって、激しい国造り競争を戦い抜くにはこれしかなかった。しかし工業化が進み国が豊かになるとともに、社会を支えるのは集中権力から自立した個人の集まりへと変わっていく。
「現代の土木はシビルエンジニアリング、市民土木ということですから、個人個人へのサービスを提供する・・中略・・サービスは受けるもので、受けていることに対する意識がない方が上です。サービスされていると思うのは、まだサービスのレベルが低いのです。・・中略・・お母さんが子どもの面倒を見るのに、サービスという意識はありません。それがサービスの根源です。ですから、サービスの対句は無意識系です。・・中略・・最高の質のものをいつでも供給できることが要求されるのが、シビルエンジニアリングです。」
あまりにあたりまえになっていて、存在さえも意識から消えうせているようなもの。蛇口から出る水や、コンセントの先にある電気、遠い昔から存在しているような気がする鉄道や橋梁など。
「サービスは行き着くところは無意識系ですから、道路を走って、1回1回つくった人にお礼は言いません。建築屋だったら、家をつくった人にお礼を言います。土木と建築は同じようで全然違うのです。」
確かに、橋を渡るときにそれをつくった人に礼は言わないし、トイレを使うときに下水道をつくった人に礼は言わない。インフラを構築するということは、結果として提供することの規模感が日常性をはるかに越えていたり、そのシステムが漠としてつかみ難いために、直接の便益がつかみにくく、わかりにくい。そのくせ、サービスがなんらかの理由で破綻したり遅延しようものなら、徹底的に糾弾される。場合によっては社会の敵だとさえ言われかねない。かくも大変なことを担うのが土木屋なのだ。これでは割に合わないと考える若者が増えても少しもおかしくはない。
丹保氏はインタビューの最後でも、次のように土木屋を叱咤している。
「エンジニアは自分が死ぬ思いでやらないといけない・・中略・・土木学会の会長も務めた廣井勇は、自分が設計した鉄道の橋を列車が渡るときに、ちゃんと渡ってくれるだろうかと、初めから終わりまで橋のたもとで震えていたといいます。それくらいの緊迫感と恐れを今のエンジニアは持っているのでしょうか。」
命を刻むような努力を放棄しておいて、想定外などという甘ったれた言葉を弄するなということであろう。小生も技術屋の端くれとして、丹保氏のこの叱正をしっかり受けとめたい。
北海道大学総長、放送大学学長などを歴任された丹保氏は、環境工学を専門とする土木界賢人の一人だが、今回の震災における土木屋の社会からの評価という点について興味深い意見を述べられている。
「土木というのは、もともとはメソポタミアやエジプトなどで文明が誕生して人が集まり、灌漑や洪水など水をコントロールしなくてはならなくなり始まった学問です。・・中略・・本来的に土木は中央集権型の技術であり、学問です。・・中略・・大型の仕事を上からやる技術者集団で、下から立ち上がってくるシビルエンジニアというのは、近代になってからのヨーロッパの発想です。・・中略・・黙っていれば上から見てしまいます。それに対する反省は常に現代の土木には必要です。」
この土木に対する指摘は重要だ。国家発展を目的として、社会のインフラを大規模に形成するのは“お上”の仕事だから、下々の者はその内容を知る必要はないという立ち位置が最初にあるという。中央集権で上からの目線をよしとするのは、全体の効率を最も重視するからであって、激しい国造り競争を戦い抜くにはこれしかなかった。しかし工業化が進み国が豊かになるとともに、社会を支えるのは集中権力から自立した個人の集まりへと変わっていく。
「現代の土木はシビルエンジニアリング、市民土木ということですから、個人個人へのサービスを提供する・・中略・・サービスは受けるもので、受けていることに対する意識がない方が上です。サービスされていると思うのは、まだサービスのレベルが低いのです。・・中略・・お母さんが子どもの面倒を見るのに、サービスという意識はありません。それがサービスの根源です。ですから、サービスの対句は無意識系です。・・中略・・最高の質のものをいつでも供給できることが要求されるのが、シビルエンジニアリングです。」
あまりにあたりまえになっていて、存在さえも意識から消えうせているようなもの。蛇口から出る水や、コンセントの先にある電気、遠い昔から存在しているような気がする鉄道や橋梁など。
「サービスは行き着くところは無意識系ですから、道路を走って、1回1回つくった人にお礼は言いません。建築屋だったら、家をつくった人にお礼を言います。土木と建築は同じようで全然違うのです。」
確かに、橋を渡るときにそれをつくった人に礼は言わないし、トイレを使うときに下水道をつくった人に礼は言わない。インフラを構築するということは、結果として提供することの規模感が日常性をはるかに越えていたり、そのシステムが漠としてつかみ難いために、直接の便益がつかみにくく、わかりにくい。そのくせ、サービスがなんらかの理由で破綻したり遅延しようものなら、徹底的に糾弾される。場合によっては社会の敵だとさえ言われかねない。かくも大変なことを担うのが土木屋なのだ。これでは割に合わないと考える若者が増えても少しもおかしくはない。
丹保氏はインタビューの最後でも、次のように土木屋を叱咤している。
「エンジニアは自分が死ぬ思いでやらないといけない・・中略・・土木学会の会長も務めた廣井勇は、自分が設計した鉄道の橋を列車が渡るときに、ちゃんと渡ってくれるだろうかと、初めから終わりまで橋のたもとで震えていたといいます。それくらいの緊迫感と恐れを今のエンジニアは持っているのでしょうか。」
命を刻むような努力を放棄しておいて、想定外などという甘ったれた言葉を弄するなということであろう。小生も技術屋の端くれとして、丹保氏のこの叱正をしっかり受けとめたい。
地熱発電、15年間の断絶 [講演を聞いて]
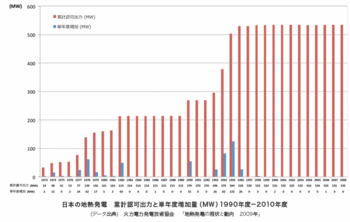 「地熱エネルギー開発の最新動向と地熱研究開発の必要性」弘前大学北日本新エネルギー研究所村岡洋文、東京大学エネルギー工学連携研究センター第14回CEEシンポジウムより
「地熱エネルギー開発の最新動向と地熱研究開発の必要性」弘前大学北日本新エネルギー研究所村岡洋文、東京大学エネルギー工学連携研究センター第14回CEEシンポジウムより石油などの地下資源が決定的に不足しているわが国は、とくにエネルギーについては、他国からそのほとんどを輸入によって賄わなければならない。エネルギーの自給率という指標でみるならば、ほとんどゼロに等しい状況にある。そうした環境下では、原発の停止のように、エネルギー構成の一角、しかも太い柱、が崩れる事態が一度生じると、これを急に代替することができないか、できたとしても多くの国富を国外に流出させることになってしまう。これは急ぎの料金だから、しっかりはずんで貰えますよねと足元を見られるのは必定であろう。
ところが、大事なことを見落としてはいませんかというのが、この村岡氏の講演だ。まず、そもそもわが国は、地熱資源大国であること。しかも、そのポテンシャルは世界第3位。狭い日本は誰にも常識だが、世界の陸域のわずか0.25%に過ぎぬ国土の上に、世界の活火山の7.56%もの活火山を擁しているという。米国、インドネシアに次ぐ世界の第3位の活火山を持ち、地熱資源量もわが国を含む上位3カ国が4位以下を大きく引き離している。にもかかわらず、開発されている地熱発電容量は世界の第8位(2010年)に止まっている。しかもこの10年で開発の進んでいるニュージーランドとアイスランドに相次いで抜かれている。
他にエネルギー資源を持たないわが国が、有力なポテンシャルを抱えていることを知りながら、なぜ開発が進まなかったのだろう。特に、1997年以降は電力開発も研究も途絶えており、世界の潮流からまったくかけ離れてしまっている。この点について、講演後の質疑で「失われた15年」の理由について、村岡氏は「原因はいくつかあるが、一つは財政危機で国の予算に余裕がなくなったこと、もう一つは電力供給の面で原子力がその中核を占めることが固まったこと。結果として、地熱発電はそれまでの開発援助によって実績も上げているので、独り立ちできると判断された」と回答している。
エネルギー政策の転換としては、1997年に地熱が「新エネルギー」から除外されたことが最も大きく、それとともに国の地熱政策予算が激減し、合わせて国立公園内での開発が事実上できなくなったことなどで、投資家が地熱発電開発への投資を躊躇する状況になったことが大きいという。
地熱開発は、それを止めてしまった日本は別として、それ以外の国では最新の技術開発が積極的に続けられている。特に注目すべきは、「涵養地熱システム(EGS)」の実用化が目前となっていることであろう。これは、地球の表面から10km近く深く掘り下がっていけば、世界中どこでも必ず温度が緩やかではあるが上昇するという点に着目し、資源開発で大深度掘削利用技術が進んだことを背景としたもの。深部の透水性の低い層まで掘削し、そこに注水し、そこで加熱された水を地表まで汲み上げる方式である。水のない温泉開発とでも呼ぶのが近いかもしれない。数年前にGoogleがこの開発に大きな投資をしたことで注目を集めているが、最大の特色は火山国でなくとも地熱発電が可能なことで、火山とはほとんど無縁なドイツではすでに大型のプロジェクトが複数動いているという。
実は、この地熱発電によって生み出される電力については、この7月から実施される日本版FIT(固定価格買取制度)の対象に入れられており、さらには環境面などの規制の緩和もあり、これで風向きが大きく変わり、15年ぶりに事業化が動き出すのではないか。特に地熱の潜在賦存量は東日本、特に東北に偏っており、この地域での今後の大きな伸張が期待できそうだ。
それにしても、15年は長い。誰がその償いをできるというのだろう。



